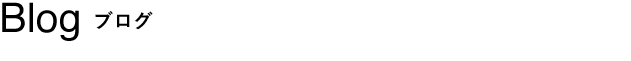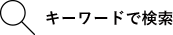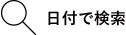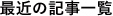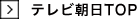- トップ
- ブログ
- 拝啓 長嶋茂雄様
- 2025年06月15日
しばらく時間が経ってしまった。
イスラエルがイランに大規模攻撃を仕掛けたり、反トランプのデモが全米を席巻したりと、世界はひどく落ち着かない。ニュースの伝え手として、いまはそこに目を向けるべきなのかもしれないが、後になって「毎週のようにコラムを書きながら、なぜ君はあのことに触れなかったのか」と野球の神様に怒られそうなので、やっぱりこの人のことを書く。6月3日に亡くなった長嶋茂雄さんのことだ。
ストッキングの履き方が素晴らしかった。いきなり細かいところで恐縮だが、昭和の野球少年はそういう細部に惹きつけられた。とにかくカッコよかったのだ。
ユニフォームのズボンとストッキングの境界線部分をどの高さにするかは、選手によってさまざまだ。そして長嶋さんの場合、ふくらはぎを丸ごと見せるでもなく、すっぽりとズボンで覆ってしまうのでもない、それはまさに「黄金比」とも言うべき絶妙の高さだった。下肢をきれいに見せるために、きっとズボンの折り返しの仕方にもこだわりがあったに違いない。ストッキングとアンダーストッキングの「黒と白」の比率もまた、絶妙としか言いようのないバランスだった。
マニアックついでにもうひとつ。バットの放り投げ方である。
右打者の長嶋さんは、ヒットを打つと、振り切ったバットを左手で放り投げる。するとそのバットは見事に「クルクルッ」と三塁線側に旋回していく。これがまたしびれるのである。
学生時代に僕も真似をしてみたのだが、長嶋さんに打力でかなうはずもない僕は凡打ばかりで、打った瞬間ションボリしてしまい、とてもバットを放り投げるどころではない。それに、たまにクリーンヒットを打ったとしても、自分の方がびっくりしてしまい、バットをどう投げたかまでは覚えていない。
三塁側に「クルクルッ」と飛んでいくあのバットの投げ方は、僕の見るところ、中畑清さんが一番の継承者ではないか。その中畑さんは長嶋さんの告別式で、「あなたは私の人生の全てです」と涙ながらに弔辞を述べていた。
僕らの世代は、立ち居振る舞いの一から十までが長嶋さんの影響下にあったと言っても過言ではない。
長嶋さんの現役引退は1974年(昭和49年)、僕が中学1年生の時だった。引退直後、書店には長嶋さんの選手としての足跡をたどる雑誌の特集などがずらりと並んだ。僕はそのうちの「長嶋茂雄・栄光の17年」(だったと思う)という一冊を、なけなしの小遣いで買い求めた。そしてそれから数か月の間、毎日のようにページをめくり、自分の生まれる前からスターだった彼のことを知ろうとした。いつしかその雑誌は表紙がとれ、ほとんど本の体裁を保たなくなったが、それでも常に僕の傍らにあった。
いま、そんな国民的ヒーローがいるだろうか?
「大谷翔平がいるじゃないか」と反論されそうだ。確かに、大谷選手はメジャー・リーグで、あの球聖ベーブ・ルースをしのぐほどの途轍もない活躍を見せているのであって、日米をまたぐファンの熱狂ぶりを含めて歴史に類を見ない。それは僕も最大の敬意を表するところだ。
一方で長嶋さんの「国民的ヒーローぶり」は、記録とは別次元のところで、おそらく今の時代では考えられないような光を放っていた。昭和の青春を送った僕には、その違いが分かる。
その理由を考えていくと、ひとつの結論に行き当たる。テレビである。僕がテレビ屋だからひいきして言うのではない。間違いなく、マスメディアとしてのテレビの普及が長嶋茂雄という不滅のヒーローを作り出す一因となったと僕は思う。
見る側と見られる側。SNS全盛の今の時代だって同じではないかと、若い世代は言うかもしれない。だが、見る側も見られる側も、熱意の総量が今とは圧倒的に違った。そんな時代に舞い降りた長嶋さんは、視聴者から寄せられる熱量をひとりで受け止め、画面越しに倍返しの光で投げ返してくれる人だった。超人的なヒーローだったのだ。
評論家の故・大宅壮一氏は、テレビの普及を「一億総白痴化」と評し、シャワーのように降り注ぐ映像が人々の想像力を奪うことを強く危惧したと言うが、テレビっ子として育った僕は、良い面だってあったと胸を張りたい。
テレビの映像文化は、あの悲惨な戦争の経験を伝え、平和を求める心を育む役割を担ったし、結果、民主主義の成長にだって強く貢献したと僕は思っている。そして一方では、長嶋さんのような、明るくハツラツとしていて、ファンに優しく人に優しく、熱血闘魂の燃える男で、ホームランを打ちながらベースを踏み忘れてアウトになってしまう天然ぶりで、良いときも悪いときもすべてをさらしてくれ、おそらく誰もがあんなふうになりたいというひとつの理想像を共有させてくれた。
長嶋さん自身、テレビを通じて人々を元気づける、そうした自分の役割を自認していたのだと思う。だからこそ、ストッキングの履き方では「ふくらはぎの黄金比」を実践し続けたし、ヒットを打ってバットを放り投げる角度だって、綿密な計算を怠らなかったのだと思う。のちに病を得てリハビリに取り組む時、「イチ、ニイ、イチ、ニイ!」と誰よりも大きな声を上げ、ほかの患者のお手本になったのも、「長嶋茂雄」であり続ける使命感が、本人を突き動かした面を否定できないと僕は思う。
長嶋さん。10年ほど前に一度、縁があって昼食をご一緒させていただきましたね。覚えていていただけたら光栄です。あなたはひたすら、客人である僕らを気遣っていらっしゃいました。当の僕は緊張して、その時の会話の内容をごく一部しか覚えていませんが、ご子息の一茂さんとの、東京六大学野球での対戦経験の話をさせていただき、あなたはとても興味深そうに聞いていらっしゃいました。
僕はいま、あなたが輝いたテレビの世界で生きています。世界は悩ましいニュースに溢れていますが、あなたのように強い光を放つヒーローや、希望を感じる出来事を伝えることも大事な仕事と考えています。世の中の森羅万象を引き受ける、ニュースの伝え手としての役割を、及ばずながらでも生真面目に全うしたいと思っています。
どうぞ、天国でゆっくりとお休みください。
(2025年6月15日)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)