 |





|
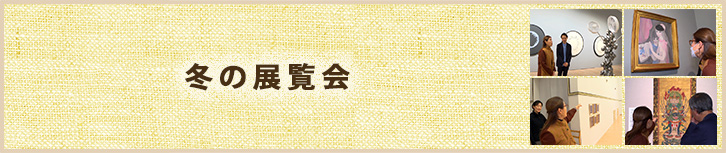
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2024年1月22日(月)
「和食の特別展」

 国立科学博物館で開催されている特別展「和食 〜日本の自然、人々の知恵〜」を紹介します。食材や歴史などの視点から和食の魅力に迫る展覧会です。
国立科学博物館で開催されている特別展「和食 〜日本の自然、人々の知恵〜」を紹介します。食材や歴史などの視点から和食の魅力に迫る展覧会です。見どころのひとつが、鹿児島県の「桜島大根」や島根県の「出雲おろち大根」など、形や色などに特徴のある25種類を厳選したダイコンのレプリカ展示です。日本はダイコンの種類が世界一で、知られている栽培品種だけで約800種類もあるそうです。ヨーロッパから弥生時代以前に日本に渡来し、地域の温度や土壌、人々の嗜好性などが重なって、約800種類もの栽培品種が誕生したと言われています。
また貝類の展示コーナーには、すべて本物の貝が標本展示されていて、生物としての姿を見ることができます。展示パネルで、寿司ネタとしてどの部位が使われているのか、を学ぶこともできます。さらに、和食の歴史を巡る展示では、歴史上の人物たちの食卓が再現模型で紹介されています。例えば「卑弥呼の食卓」は、季節は春の想定で、サトイモとタケノコと豚肉の煮物、マダイの塩焼きなど贅沢な内容になっています。
国立科学博物館「【特別展】和食 〜日本の自然、人々の知恵〜」
会期:2月25日(日)までHP:https://washoku2023.exhibit.jp/
2024年1月23日(火)
「マリー・ローランサン」

 アーティゾン美術館で開催中の「マリー・ローランサン―時代をうつす眼」を紹介します。
アーティゾン美術館で開催中の「マリー・ローランサン―時代をうつす眼」を紹介します。マリー・ローランサンは20世紀前半に活躍した画家で、パステルカラーの淡い色彩を使った作風が特徴です。40歳の頃に描いた代表作品が「二人の少女」。ピンクとブルーとグレーという“ローランサンらしい色”を使って、儚(はかな)げな印象の女性を描いています。1923年に描かれたこの作品は1925年には日本で紹介されましたが、当時の日本人にとっては、パリの最先端の芸術だったそうです。
ローランサンは、パブロ・ピカソなど様々な画家と交流しながら自分の画風を作っていったと言われています。20代後半は色々なことを実験的に試していた時期で、ピカソの横顔を描いた、この時期の作品も展示されています。
72歳で生涯を閉じるまで絵を描き続けたローランサンが、10年近い年月をかけて完成させた晩年の大作が「三人の若い女」です。晩年になると彼女の作品は鮮やかな色合いになり、女性の髪や首元には真珠のアクセサリーなども描かれています。
アーティゾン美術館「マリー・ローランサン ― 時代をうつす眼」
会期:3月3日(日)までHP:https://www.artizon.museum/exhibition_sp/laurencin/
2024年1月24日(水)
「豊嶋康子展」

 東京都現代美術館で開催中の「豊嶋康子 発生法──天地左右の裏表」の展覧会を紹介します。
東京都現代美術館で開催中の「豊嶋康子 発生法──天地左右の裏表」の展覧会を紹介します。豊嶋さんは、さまざまな制度や価値観、約束事に対して独自の視点で考えた作品を発表しています。
例えば「ジグソーパズル」という作品は、サグラダ・ファミリアの絵柄になる2000ピースのジグソーパズルを、線状にひとつずつ繋げたものです。豊嶋さんは、私たちがよく使ったり遊んだりするもののルールに則りながらも、少し逸脱することによって、“別の光を当てる”作品を制作しています。
豊嶋さんのデビュー作品のひとつが、「エンドレス・ソロバン」です。長さ約110mのそろばんが会場の壁をぐるりと取り囲んでいる作品です。そろばんが繋がって円環状になっているので、計算をし続けていくと最終的には自分が前に計算したものも自分で壊していく、という構図になり、答えを出そうとする行為が無限に壊していく行為にもなる、という矛盾をはらんだ作品です。
東京都現代美術館「豊嶋康子 発生法──天地左右の裏表」
会期:3月10日(日)までHP:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/toyoshima_yasuko/
2024年1月25日(木)
「オラファー・エリアソン展」
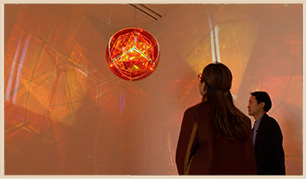
 麻布台ヒルズギャラリーで開催中の「オラファー・エリアソン展」を紹介します。
麻布台ヒルズギャラリーで開催中の「オラファー・エリアソン展」を紹介します。オラファー・エリアソンは、社会的課題への取り組みでも世界的に注目されているアーティストで、色や光など自然界を構成する要素を取り込んだ作品を発表しています。今回の展覧会のために制作されたのが、「呼吸のための空気」という新作。この作品は使われている素材にも大きな意味があり、焼却場の煙突から出る煙をフィルターでこして集めた、リサイクル素材の亜鉛で作られています。作品の上部には4つのファンがついていて、この風に当たることも、この作品を体験する重要な要素になっています。
光の反射を巧みに計算した作品が「蛍の生物圏 (マグマの流星)」。地球のあらゆる生命体が生きている、ということを連想させる作品です。3つの多面体を組み合わせた3層のガラス構造になっていて、内側にある多面体がモーターで回転し、外枠についたLEDライトが中心部を照らしています。部分的に反射したり色が変化したりするガラスを使っていることで、幻想的な光の動きをもたらす仕組みになっています。
麻布台ヒルズギャラリー 「【麻布台ヒルズギャラリー開館記念】オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期」
会期:3月31日(日)までHP:https://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsgallery/sp/olafureliasson-ex/
2024年1月26日(金)
「初公開の仏教美術」

 半蔵門ミュージアムで開催中の「初公開の仏教美術―如意輪観音菩薩像・二童子像をむかえて―」を紹介します。新たに加わった仏像を含めた初公開のものだけを集めた特集展示です。
半蔵門ミュージアムで開催中の「初公開の仏教美術―如意輪観音菩薩像・二童子像をむかえて―」を紹介します。新たに加わった仏像を含めた初公開のものだけを集めた特集展示です。平安時代中期につくられた如意輪観音菩薩坐像(にょいりんかんのんぼさつざぞう)は、京都・醍醐寺から2019年に寄贈され、修理を経て初公開されました。修理前の顔には木屎漆(こくそうるし)という材料が盛られ、別の目が彫られていましたが、それを取り除いた制作当時の姿を見ることができます。同じく醍醐寺から寄贈された、不動明王に仕える「矜羯羅童子(こんがらどうじ)」「制吒迦童子(せいたかどうじ)」の像も展示されています。平安時代後期の貴族の美意識がよくわかる作品です。
江戸時代に描かれた「刀八毘沙門天像(とうはちびしゃもんてんぞう)」は、8本の刀を手にしているので“刀八”と名付けられた毘沙門天像の絵画です。この名前は、中国由来の“兜跋(とばつ)毘沙門天”という毘沙門天になぞらえ、「トバツ」を刀8本の「トウハチ」に掛けたと言われています。
半蔵門ミュージアム「初公開の仏教美術―如意輪観音菩薩像・二童子像をむかえて―」
会期:4月14日(日)までHP:https://www.hanzomonmuseum.jp/exhibits/special.html







