 |





|
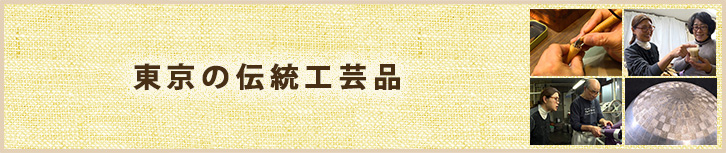
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2024年1月15日(月)
「東京手彫り印章」

 東京都は、風土と歴史の中で受け継がれてきた42の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。
東京都は、風土と歴史の中で受け継がれてきた42の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。その一つ「東京手彫り印章」は100年以上続く技法で、一握りの職人しか彫ることができません。この道37年の持木秀彦(もちき ひでひこ)さんに、「林家きく姫」という印章を作ってもらいました。
まずは「印稿(いんこう)」と呼ばれる設計図作りから。全体のバランスをよくするために「きく」という2文字を1文字として配置し、柔らかさを表現するため丸みのある書体でデザインしました。墨で文字の下書きをしたら、「荒彫り」の工程へ。印刀(いんとう)と呼ばれる専用の刃物で、文字だけを残してそれ以外の部分を削るように彫っていきます。刃先の違う印刀を使い分けながら、1mmほどの深さに彫り進めます。最後に、細かな仕上げをして完成です。
東京手彫り印章をはじめ、東京の様々な工芸品が展示・販売される「東京都伝統工芸品展」が、1月17日から21日まで開催されます。
秀美堂印房
HP:https://tokyohanko.jp/sbd.html
2024年1月16日(火)
「東京手植ブラシ」

 東京都が指定する「東京都伝統工芸品」の一つ「東京手植(てうえ)ブラシ」を紹介します。
東京都が指定する「東京都伝統工芸品」の一つ「東京手植(てうえ)ブラシ」を紹介します。東京手植ブラシは、馬や山羊などの毛を、職人が1つ1つ手で植えて作るブラシです。毛が密集していて、ブラッシングしやすいのが特徴です。この道19年の東京手植ブラシ職人・宇野三千代さんに、洋服ブラシの製作工程を見せてもらいました。
まずブラシの形の木の板に穴のあいた真鍮(しんちゅう)の型をのせて、墨で印をつけます。印に沿って板に穴をあけたら、毛を植えていきます。使用するのは馬の尻尾の産毛です。柔らかく弾力性があるので、デリケートな素材の衣類にも使えるそうです。穴の裏側からステンレス線を通して輪を作り、毛を二つ折りにして板に植えつけていきます。一本のステンレス線ですべての毛を植え付けるので、毛が抜けにくく、長く使うことができるそうです。
東京手植ブラシをはじめ、東京の様々な工芸品が展示・販売される「東京都伝統工芸品展」が、1月17日から21日まで開催されます。
宇野刷毛ブラシ製作所
HP:https://unobrush.jp/
2024年1月17日(水)
「東京銀器」

 東京都が指定する「東京都伝統工芸品」の一つ「東京銀器」を紹介します。
東京都が指定する「東京都伝統工芸品」の一つ「東京銀器」を紹介します。東京銀器は、地金(じがね)と呼ばれる純銀の板を金鎚などで叩き、様々な形を作り出す金属工芸品です。その技術を現代に受け継いでいる上川宗達(かみかわ そうたつ)さんに、製作工程を見せてもらいました。
東京銀器の製作で要となるのが、当て金(あてがね)という道具。当て金に合わせて叩いて形を作るため、製品の形によって使用する当て金を変えます。何度も何度も繰り返し金鎚などで叩くことで、理想の形に仕上げていきます。東京銀器の魅力の一つは美しい模様。「鎚目(つちめ)」や「ゴザ目」などの模様は、専用の金鎚で叩いてつけます。さらに細かい模様を施す場合には、鏨(たがね)を使うこともあります。小物入れに市松模様を入れる作業は2カ月ほどの時間がかかるそうです。
東京銀器をはじめ、東京の様々な工芸品が展示・販売される「東京都伝統工芸品展」が1月21日まで開催されます。
宗達アートクラフト
HP:https://www.soutatsukamikawa.com/
2024年1月18日(木)
「東京籐工芸」

 東京都が指定する「東京都伝統工芸品」の一つ「東京籐工芸(とうこうげい)」を紹介します。
東京都が指定する「東京都伝統工芸品」の一つ「東京籐工芸(とうこうげい)」を紹介します。東京籐工芸は、ヤシ科の植物を原材料に、椅子やかごなど、様々なものを作る伝統工芸です。この道28年、東京都伝統工芸士の木内秀樹さんに、椅子の製作工程を見せてもらいました。
まずは、籐を組み合わせて土台の骨組みを作ります。次に、座面の部分を編みます。籐は曲げたり編んだりする場合、そのままでは固く加工しにくいので、1時間ほど水につけてから使用します。柔らかくなった籐を使い、「目積(めせき)編み」という編み方で座面部分を編み上げていきます。土台に取り付ける工程では、座面が弛まないよう、一本一本締め込みながら釘で固定します。そうすることでクッション性と耐久性に優れ、座り心地の良い椅子が出来るそうです。
東京籐工芸をはじめ、東京の様々な工芸品が展示・販売される「東京都伝統工芸品展」が、1月21日まで開催されます。
木内籐材工業
HP:https://www.kiuchi-tohzai.co.jp/
2024年1月19日(金)
「東京無地染」

 東京都が指定する「東京都伝統工芸品」の一つ「東京無地染(むじぞめ)」を紹介します。
東京都が指定する「東京都伝統工芸品」の一つ「東京無地染(むじぞめ)」を紹介します。東京無地染は、柄や厚さが異なる白い絹織物を顧客の好みに応じて単色に染める技で、明治後半から大正にかけて始まりました。職人歴50年、東京都伝統工芸士の近藤良治(よしはる)さんに、製作工程を見せてもらいました。
東京無地染は、まず最初に約80℃のお湯に生地を浸し、付着した不純物を取り除きます。次に染料を調合します。基本的に「赤」「青」「黒」「紫」「黄」の5色であらゆる色を作り出します。今回は赤、黒、紫を使用して色見本と同じ色に染めました。出来上がりをイメージし、近藤さんの長年の勘で染料を見極めて調整します。染料ができたら、機械で生地を回転させながら染料につけて染めていきます。近藤さんは、10分おきに染めている生地と色見本を見比べながら、足りない染料を追加していきます。この工程を4、5回繰り返し、色見本通りの色に仕上げていきます。染め上がったら生地を水洗いし、乾燥させて完成です。
東京無地染をはじめ、東京の様々な工芸品が展示・販売される「東京都伝統工芸品展」が、1月21日まで開催されます。
近藤染工
HP:http://kondosenkou.com/
東京都伝統工芸品展
会期:1月17日(水)~21日(日)
時間:午前10時30分~午後7時30分
会場:新宿髙島屋11階 催会場
入場料:無料
HP:https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/events/2023/1219.html







