 |





|
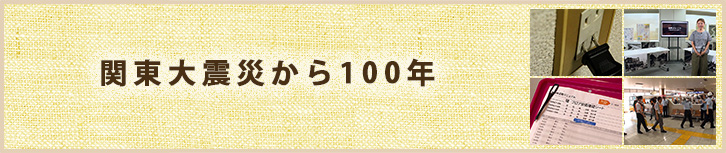
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2023年8月28日(月)
「大地震の揺れを体験」

 今年9月1日で「関東大震災」から100年を迎えます。そこで今週は大地震への備えなどを紹介します。
今年9月1日で「関東大震災」から100年を迎えます。そこで今週は大地震への備えなどを紹介します。東京都では災害に強いまちづくりを行う「TOKYO強靭化プロジェクト」を推進し、防災知識の普及・啓発などにも取り組んでいます。
1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災の死者・行方不明者は10万人を超え、国内の災害史上、最大の被害となりました。実際の災害を疑似体験できる「本所防災館」を林家きく姫が訪ね、当時の地震データを基に再現した関東大震災の揺れを体験しました。今の基準では震度7相当の揺れで、立っていることはできません。床にうずくまる低い姿勢を取って、身を守ることが大事です。
ビルの高層化が進んだ現在は、大地震の発生時に起きる「長周期地震動」にも注意が必要です。長周期地震動は高層階ほど揺れが大きくなる特徴があり、固定されていないコピー機や棚などが激しく動いてしまいます。家具などをしっかりと固定することが大切です。
本所防災館
HP:https://tokyo-bskan.jp/bskan/honjo/
2023年8月29日(火)
「復興デジタルアーカイブ」

 今年9月1日で「関東大震災」から100年を迎えます。
今年9月1日で「関東大震災」から100年を迎えます。東京都では「TOKYO強靭化プロジェクト」を推進し、災害に強いまちづくりのための様々な取り組みを行っています。その一環として東京都が先月公開したのが「復興デジタルアーカイブ」。パソコンやスマートフォンで震災当時の写真や映像を見ることができます。
HPで地図に表示されたアイコンを選ぶと、その場所で撮影された当時の写真などが表示されます。火災で焼け野原になった様子などがわかります。
関東大震災からの復興では、避難経路の確保や火事の延焼を防ぐために幅の広い道路が造られ、現代の“まちづくり”につながっています。都内50カ所以上で鉄筋コンクリートの小学校に隣接した、都民の避難場所となる公園も造られました。江東区にある「元加賀公園」もその一つです。
アーカイブでは、「被災直後」「復興中」「現在」の写真を比べて見ることもできます。
復興まちづくり 〜100年先も安心を目指して〜|東京都都市整備局
HP:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/tokyo-fukkou/index.html
2023年8月30日(水)
「感震ブレーカー」

 今年9月1日、発生から100年を迎える「関東大震災」では、地震の影響で大規模な火災が発生し、死亡原因の約9割が火災によるものでした。また東日本大震災で起きた原因が特定されている火災のうち、半数以上が電気による火災でした。電熱器具や、倒れた家具の下敷きになった電源コード、抜けかけたプラグなどが出火の原因になります。そのため、家の外へ避難する際には、ブレーカーを落とすことが大切です。しかし、災害の際にはブレーカーを落とす余裕がない場合も想定されるため、「感震ブレーカー」を取り付けることが推奨されています。
今年9月1日、発生から100年を迎える「関東大震災」では、地震の影響で大規模な火災が発生し、死亡原因の約9割が火災によるものでした。また東日本大震災で起きた原因が特定されている火災のうち、半数以上が電気による火災でした。電熱器具や、倒れた家具の下敷きになった電源コード、抜けかけたプラグなどが出火の原因になります。そのため、家の外へ避難する際には、ブレーカーを落とすことが大切です。しかし、災害の際にはブレーカーを落とす余裕がない場合も想定されるため、「感震ブレーカー」を取り付けることが推奨されています。大きな揺れを検知し、自動的にブレーカーを落とす「感震ブレーカー」は、さまざまなタイプがあり、自身の家庭環境に合わせたタイプを選んで設置することができます。分電盤にあらかじめ内蔵されている「内蔵タイプ」や、「後付けタイプ」、「簡易タイプ」に加え、通電を遮断したい機器を選んでコンセントに取り付ける「コンセントタイプ」などもあります。
出火防止対策|東京都防災ホームページ
HP:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028034/index.html
2023年8月31日(木)
「マンションの防災」

 今年9月1日で「関東大震災」から100年を迎えます。
今年9月1日で「関東大震災」から100年を迎えます。東京都では「TOKYO強靭化プロジェクト」を推進し、地震などから街を守る様々な取り組みを行っています。その一環として、災害対策に積極的なマンションを「東京とどまるマンション」として登録し、防災意識の向上を図っています。
「東京とどまるマンション」の登録基準は、災害発生から3日間を目安にマンション内で生活できる備えがあることなどです。「東京とどまるマンション」に登録されている「シャンボール三田」では、停電時でもエレベーターや廊下の照明など、マンションの共用部に電力を供給できる「非常用発電機」を設置しています。災害時の断水に備えた井戸や、井戸水を各フロアに送水する設備もあります。
“防災マニュアルの作成”も登録基準のひとつ。こちらのマンションで作成した防災マニュアルでは、発災時にマンション内にいる住民だけで対策本部を立ち上げる流れや、救護や建物の点検などを行うグループ分けの方法などをまとめています。
東京とどまるマンション
HP:https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku.html
2023年9月1日(金)
「帰宅が困難になったら」

 放送日の9月1日、10万人を超える死者・行方不明者を出し、国内の災害史上最大の被害となった関東大震災から100年を迎えます。
放送日の9月1日、10万人を超える死者・行方不明者を出し、国内の災害史上最大の被害となった関東大震災から100年を迎えます。現在東京都では「TOKYO強靭化プロジェクト」を推進し、災害に強いまちづくりのための様々な取り組みを行っています。その一環として、8月に大地震を想定した「帰宅困難者対策訓練」が行われました。
大地震が発生すると、交通機関は点検のために運行を停止します。そのため都内で約453万人の帰宅困難者が発生すると予測されています。災害発生直後は、救出救助の妨げになる場合があるため、むやみに徒歩で帰宅せず係員などの誘導に従って避難することが大切です。帰宅困難者は発災時から3日間被災した場所の付近に留まることが基本とされています。
帰宅困難者にとって一番大事なのは、3日間留まることができる「一時滞在施設」の情報です。そのため、駅周辺に設置してあるデジタルサイネージに表示された災害情報にアクセスする訓練も行われました。一時滞在施設は公共施設や学校のほか、民間企業などでも開設される場合があります。
帰宅困難者対策|東京都防災ホームページ
HP:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kitaku_portal/index.html







