 |





|
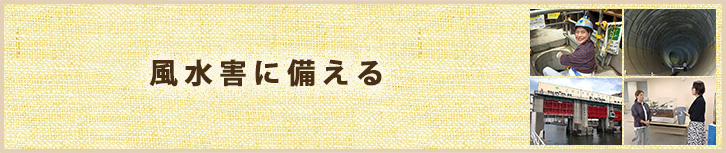
��1�T�ԕ��̓���͂�������
������������YouTube�ł�
2023�N6��19��(��)
�u�Z����̒n���g���l���v

 ��K�͂ȕ����Q��n�k�Ȃǂ̎��R�ЊQ����X����邽�߁A�����s�͗l�X�Ȏ{�݂���������uTOKYO���x���v���W�F�N�g�v�𐄐i���Ă��܂��B
��K�͂ȕ����Q��n�k�Ȃǂ̎��R�ЊQ����X����邽�߁A�����s�͗l�X�Ȏ{�݂���������uTOKYO���x���v���W�F�N�g�v�𐄐i���Ă��܂��B�L����E��ˉw�̋߂��ł́A�Z����̂��߂̍H�����i�߂��Ă��܂��B
10�N�O�A�������ł�1����50mm�̉J�ɑΉ��ł��銲���i�����������ǁj���ݒu����Ă��܂������A�z������J������A���̒n���170������Z����Q���������܂����B�����ŁA�r���\�͂����邽�߁A�n����40m�̏ꏊ�ɁA�J�����ꎞ�I�ɒ��߂鉺�����ǂ�H�����i�߂��Ă��܂��B��ˉw���珬�ΐ�A�����t�߂܂ő���������2.5km�́u��쑝�������v�ł��B
���̑��������́A���ɂ��銲���ƘA�����邱�Ƃɂ���āA�����I�ɂ�1����75mm�̍~�J�ɑΉ��ł���v��ł��B2024�N�x�ɉ^�p���J�n�����\��ł��B
�������ǂ̐Z����
HP�Fhttps://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/pdf/shinsuitaisaku.pdf
2023�N6��20��(��)
�u���q�여��̐��Q��v
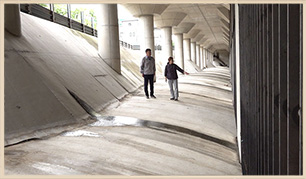
 ���R�ЊQ�ɔ����邽�ߓ����s�����i���Ă���uTOKYO���x���v���W�F�N�g�v�̐��Q����Љ�܂��B
���R�ЊQ�ɔ����邽�ߓ����s�����i���Ă���uTOKYO���x���v���W�F�N�g�v�̐��Q����Љ�܂��B���n��̔��q��i���炱����j����ł́A3�̎{�݂Ő�̑����ɑΉ����Ă��܂��B
1�ڂ́A�u��u��i�т��Ɂj���㗬���ߒr�i���傤�����j�v�B���i�̓e�j�X�Ȃǂ��ł�������ł����A��J�̎��Ɉꎞ�I�ɐ��߂�ꏊ�ɂȂ�܂��B��̐��ʂ��オ��A���i�����j�������������֗��ꍞ�ގd�g�݂ł��B25m�v�[����115�t���̐��߂��܂��B
2�ڂ͒n���ɐ��߂�^�C�v�́u��u�������ߒr�v�ł��B���ߒr�͍�����23m�A25m�v�[����700�t���̐��߂邱�Ƃ��ł��܂��B
3�ڂ́A�n����35m�̏ꏊ�ɂ���u���q��n�����ߒr�v�ł��B���a10m�A����3.2�q�̃g���l�������ߒr�����n��́u���W�����N�V�����v����ΐ_���܂ő����Ă��āA25m�v�[����700�t���̐��߂��܂��B
����ɁA���̃g���l���Ɗ����̒n���ɑ����Ă��钲�ߒr��A������v�悪�i�߂��A2025�N�x�̉ғ���ڎw���Ă��܂��B�A������Ƒ�������13�q�ƂȂ�A1����100�o�̏W�����J�Ɍ��ʂ����鍑���ő�̒n�����ߒr�ɂȂ�܂��B
���q�쒲�ߒr�Q
HP�Fhttps://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/yonken/koji2/chikacho.html2023�N6��21��(��)
�u�Ôg�E�����̑�v

 ���R�ЊQ�ɔ����邽�ߓ����s�����i���Ă���uTOKYO���x���v���W�F�N�g�v�̒Ôg�E��������Љ�܂��B
���R�ЊQ�ɔ����邽�ߓ����s�����i���Ă���uTOKYO���x���v���W�F�N�g�v�̒Ôg�E��������Љ�܂��B�`��́u�����Z���^�[�v�ł́A�����`��15�J���̐�����Ď����A���u���삵�Ă��܂��B���䎺�̃��C�����j�^�[�ɂ́A�u����v��u�h����v�Ȃǂ��}�b�v�ŕ\������Ă��܂��B�h����͒Ôg�⍂���őz�肳����6���̔g�ɂ��ς�����悤�ɑ����Ă��܂��B���H�����邽�߂ɖh���炪����Ȃ��ꏊ�ɂ͐����ݒu���A�������邱�ƂŒÔg�⍂����h���܂��B�������������Ă��A��J�Ȃǂ̉e���Ŗh����̓����̐��ʂ��オ�邱�Ƃ�����܂��B���̑�Ƃ��āu�r���@��v��ݒu���A�|���v�œ����̐����C�ɔr���ł���悤�ɂ��Ă��܂��B�]����ɐV�݂��ꂽ�u�C���r���@��v�ɂ͍��v9��̃|���v���ݒu����A25m�v�[����2�`3�b�ŋ�ɂ���r���\�͂�����܂��B
������Z���^�[�͍`��ƍ]����ɂ���A�ǂ���ł������r���@��Ȃǂ����u�ŊǗ��ł���o�b�N�A�b�v�̐����������Ă��܂��B
������Z���^�[
HP�Fhttps://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/yakuwari/takashio/center/
2023�N6��22��(��)
�u�Z��łł���Z����v

 ���R�ЊQ�ɔ����邽�ߓ����s�����i���Ă���Z��łł���Z������Љ�܂��B
���R�ЊQ�ɔ����邽�ߓ����s�����i���Ă���Z��łł���Z������Љ�܂��B�s�s���ɍ~�����J�͉�������ʂ��Đ��C�ɔr������܂����A��ʂ̉J�����ꍞ�݉������ǂ̔\�͂����ꍇ�A�u�����×��i�Ȃ������͂���j�v�ƌĂ��Z����Q�ɂȂ���܂��B�����ܑ͕�����Ă���ꏊ���������߁A�n�ʂɐ������ݍ��݂Â炭�A���Q��Q�z��7���ȏオ���̓����×��ɂ����̂ł��B
�����œ����s�����y��i�߂Ă���̂��u�J���Z���i����������Ƃ��j�܂��v�ł��B��Ȃǂɖ��ߍ���Őݒu���A�J�ǂ��ŏW�߂�ꂽ�J����n�ʂɐZ�������邱�Ƃʼn������ɗ��ꍞ�ސ������炷���Ƃ��ł��܂��B���̂ق��A����n�ʂɐ��ݍ��܂��錊���J���Ă���u�Z���ǁv�ƌĂ����̂�����܂��B�͌^���g���������ł́A�����̑��ʓI�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B
���J�ЊQ����킪�Ƃ����
HP�Fhttp://www.tokyo-sougou-chisui.jp/Pamphlet/wagayawomamoru_R4.pdf
2023�N6��23��(��)
�u�n���S�̐Z����v

 �l�X�ȐZ������s���Ă��铌�����g���̎��g�݂��Љ�܂��B
�l�X�ȐZ������s���Ă��铌�����g���̎��g�݂��Љ�܂��B���w�̂��ɁA�n��̎Ԍɂ���n���ɂȂ�����H������܂��B�^���������������A���H��ʂ�n���ɐ�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A������20cm�́u�h���Q�[�g�v�����u����ŕ߂��܂��B�n���̐��H���ɂ������d�g�݂̖h���Q�[�g���ݒu����Ă��܂��B
��q�����p����w�̏o�����ɂ́A�u�h�����v��u�~���i��������j�v�Ő���h���{����Ă��܂��B
�����Ȃǂɂ���n���S�́u���C���v�ɂ�����Ă��܂��B���C���̋��Ԃ̉��͋ɂȂ��Ă��Ēn���S�̍\���ɂȂ����Ă��܂����A���u����Ńt�^���܂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B��J�x��Ȃǂ��o�����́A���̃t�^��߂Đ������ꍞ�܂Ȃ��悤�ɖh���܂��B
����ɁA���j�^�[��}�C�N�Ȃǂ�ݒu�����A�ЊQ���̑��{���ƂȂ镔����݂��A�����Ƃ������ɐv���ɑΉ��ł���悤�A�W�҂��W�܂�P�������I�ɍs���čЊQ�ɔ����Ă��܂��B
�����Q��|�������g��
HP�Fhttps://www.tokyometro.jp/safety/prevention/wind_flood/index.html
TOKYO���x���v���W�F�N�g
HP�Fhttps://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/kyoujinkaproject/
�@







