 |





|
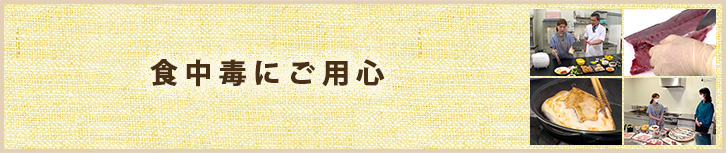
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2023年6月12日(月)
「食中毒予防の3原則」

 去年、全国で6856人の食中毒が確認されています。食中毒の原因は、肉や魚料理、弁当など様々。高温多湿になるこれからの時期は、特に注意が必要です。食中毒の症状は、下痢や腹痛、発熱などですが、重篤になると命にかかわることもあります。
去年、全国で6856人の食中毒が確認されています。食中毒の原因は、肉や魚料理、弁当など様々。高温多湿になるこれからの時期は、特に注意が必要です。食中毒の症状は、下痢や腹痛、発熱などですが、重篤になると命にかかわることもあります。食中毒の予防には、細菌を「付けない」「増やさない」「やっつける」の3原則が効果的です。1つ目の「付けない」のポイントは、手をよく洗うこと。また、調理で使った道具はしっかり洗浄し、さらに熱湯消毒することで細菌が死滅します。原則の2つ目は「増やさない」。細菌が増える原因の一つは肉や魚から出るドリップです。購入後は、他の食材にドリップが付かないように持ち運ぶことがポイントです。ポリ袋で2重に包み、保冷バッグや保冷剤を使い低温で持ち帰ると、細菌が増えにくくなります。持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫に入れることも大切です。
3つ目の「やっつける」のポイントは、肉などは中心部の温度が75℃の状態で1分以上加熱することです。
東京都健康安全研究センター
HP:https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/
2023年6月13日(火)
「魚の食中毒予防」

 魚を調理するときや食べるときに気を付けなくてはいけないのが、アニサキスによる食中毒です。
魚を調理するときや食べるときに気を付けなくてはいけないのが、アニサキスによる食中毒です。アニサキスは、白い糸のような寄生虫で、幼虫は体長およそ2cmから3cmです。サバをはじめ、アジやサンマ、イワシ、サケなどにも寄生しています。去年のアニサキスによる食中毒の発生件数は566件。ここ10年間で、およそ6倍に増加しています。中には、家庭で食べたイワシのマリネや、カツオのたたきでアニサキス食中毒になったケースもあります。アニサキスは、通常の料理で用いる酢やわさび、しょう油などでは死滅しません。
アニサキスは胃壁や腸壁に刺さって激しい腹痛を起こす寄生虫です。多くは胃アニサキス症で、食後2時間から8時間で症状が現れますが、医療機関で内視鏡検査を行い、アニサキスを摘出すれば痛みは治まります。
魚を生で食べるときは、内臓を全て取り除き、アニサキスがいないかを確認することが重要です。そして、内臓に近い身も大きく切り取ると、より安全です。またアニサキスは「冷凍」に弱く、魚の中心部までマイナス20℃で24時間以上冷凍すると死滅します。焼いたり煮たりする場合は、中心部を60℃で1分以上加熱すれば死滅します。
東京都健康安全研究センター
HP:https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/
2023年6月14日(水)
「鶏肉の食中毒予防」

 去年、全国で822人が、カンピロバクター食中毒になりました。これらの原因には、加熱が不十分な鶏肉が飲食店で提供されたケースが多くありました。カンピロバクターは鶏の腸管内に生息し、食肉処理の過程で肉につくと、食中毒の原因になります。カンピロバクター食中毒の症状は下痢や腹痛、発熱などです。通常は1週間程度で回復しますが、乳幼児や高齢者は重症化する恐れがあります。また非常に稀に、手足の麻痺や呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症する場合があります。カンピロバクター食中毒予防のポイントは、十分に加熱することです。目安は肉の中心温度が75℃で1分間加熱し続けることで、中心まで火が通り、肉の色が変わっていれば食中毒菌は死滅しています。調理で残った生の鶏肉は、キッチンペーパーでドリップを拭き取り、ラップなどで2重に包むことで、他の食材への二次汚染を防ぐことができます。
去年、全国で822人が、カンピロバクター食中毒になりました。これらの原因には、加熱が不十分な鶏肉が飲食店で提供されたケースが多くありました。カンピロバクターは鶏の腸管内に生息し、食肉処理の過程で肉につくと、食中毒の原因になります。カンピロバクター食中毒の症状は下痢や腹痛、発熱などです。通常は1週間程度で回復しますが、乳幼児や高齢者は重症化する恐れがあります。また非常に稀に、手足の麻痺や呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症する場合があります。カンピロバクター食中毒予防のポイントは、十分に加熱することです。目安は肉の中心温度が75℃で1分間加熱し続けることで、中心まで火が通り、肉の色が変わっていれば食中毒菌は死滅しています。調理で残った生の鶏肉は、キッチンペーパーでドリップを拭き取り、ラップなどで2重に包むことで、他の食材への二次汚染を防ぐことができます。女子栄養大学短期大学部
HP:https://www.eiyo.ac.jp/
2023年6月15日(木)
「牛肉の食中毒予防」

 去年全国で78人が、O(オー)157に代表される腸管出血性大腸菌で食中毒になっています。その主な原因は、牛肉です。O157は牛の腸管内に生息し、食肉処理の過程で肉につくと、食中毒の原因になります。O157による食中毒の症状は、激しい腹痛や下痢、血便などです。過去には、半生の肉総菜を食べて死者が出たケースもあります。
去年全国で78人が、O(オー)157に代表される腸管出血性大腸菌で食中毒になっています。その主な原因は、牛肉です。O157は牛の腸管内に生息し、食肉処理の過程で肉につくと、食中毒の原因になります。O157による食中毒の症状は、激しい腹痛や下痢、血便などです。過去には、半生の肉総菜を食べて死者が出たケースもあります。O157による食中毒が発生する原因の一つが、「二次汚染」です。肉を触った後に、そのまま野菜を触ってしまうと、肉についていたO157が野菜に移ってしまいます。調理を行う際には必ず手を洗い、調理で使った道具は洗浄後、熱湯で消毒することで細菌が死滅します。牛肉を加工したサイコロステーキなど成型肉の場合には、中にも菌がいると考えて、中心温度が75℃で1分以上焼くことが重要です。さらに、豚肉にも食中毒菌、ウイルス、寄生虫がいる場合があるので、しっかりと中心部まで加熱することが重要です。
女子栄養大学短期大学部
HP:https://www.eiyo.ac.jp/
2023年6月16日(金)
「お弁当の食中毒予防」

 弁当を作るときの食中毒予防について紹介します。
弁当を作るときの食中毒予防について紹介します。弁当の一番の問題点は、朝作って昼に食べるまでの間に食中毒菌が増えてしまうということです。
都内では「黄色ブドウ球菌」を原因とした弁当の食中毒も起きているので注意が必要です。黄色ブドウ球菌による食中毒の症状は、悪寒やおう吐、下痢など。黄色ブドウ球菌は手が触れることで他の食材に広がるため、弁当を作るときには必ず手を洗い、直接食材に触れないことが重要です。弁当を詰めるとき、ご飯は小皿にとり、保冷剤などの上にのせて、冷ましてから詰めましょう。加熱した総菜も、同様に熱をとり、カップで小分けにして詰めることで、水分が混じることや食中毒菌の増殖を防ぐことができます。また生野菜は水分が多く、他の食材に水分を与えてしまう可能性があるため、一緒に入れないことが原則です。茹でた野菜は、水分を十分に切ってから入れることが大切です。
女子栄養大学短期大学部
HP:https://www.eiyo.ac.jp/







