 |





|
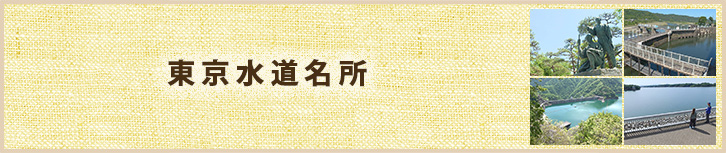
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2023年5月29日(月)
「小河内貯水池」

 東京都は7つの「東京水道名所」を選定し、水道施設の魅力を発信しています。
東京都は7つの「東京水道名所」を選定し、水道施設の魅力を発信しています。JR奥多摩駅からバスで20分の所にある「小河内(おごうち)貯水池(1957年完成)」は国内最大の水道専用貯水池です。多摩川の上流にある「水道水源林」と呼ばれる山に降った雨を飲み水にするために蓄えています。貯水池の深さは約140mで、都内で使われる約40日分の水を貯めることができます。遊歩道も整備された「小河内ダム」は人気の観光スポットにもなっており、ダムの展望台からは貯水池や高さ約150mのダム本体を見下ろすことができます。
そして貯水池の隣には、奥多摩の自然やダムの仕組みを遊びながら体験できる「奥多摩 水と緑のふれあい館」があります。こちらの施設では、小河内貯水池が建設される前、この場所にあった村の文化や歴史なども紹介しています。
東京水道名所「小河内貯水池」|東京都水道局
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kouhou/meisho/ogouchi.html奥多摩 水と緑のふれあい館
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kouhou/pr/okutama/
2023年5月30日(火)
「羽村取水堰」

 東京都は7つの「東京水道名所」を選定し、水道施設の魅力を発信しています。
東京都は7つの「東京水道名所」を選定し、水道施設の魅力を発信しています。JR青梅線「羽村駅」から徒歩10分の所にある「羽村取水堰(ぜき)」は多摩川の水を生活用水として引き入れ、「玉川上水」に送るための施設として1653(承応2)年に完成しました。堰の一部は「投渡堰(なげわたしぜき)」という、丸太や木の枝を束ねた構造になっています。上流の水位が上昇し氾濫の恐れがある時、投渡堰を壊して、水を下流に流すことによって氾濫を防いでいます。壊した投渡堰はその後、再び手作業で作り直します。堰の脇には“筏通場(いかだとおしば)”と呼ばれる、かつて木材を運んでいたいかだを通すための場所も残されています。羽村取水堰は、江戸時代から受け継がれる貴重な水道施設として「土木遺産」に登録されています。
東京水道名所「羽村取水堰」|東京都水道局
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kouhou/meisho/hamura.html
2023年5月31日(水)
「玉川上水」

 東京都は7つの「東京水道名所」を選定し、水道施設の魅力を発信しています。
東京都は7つの「東京水道名所」を選定し、水道施設の魅力を発信しています。多摩川から取り入れた生活用水を江戸市中に送るため造られた「玉川上水」は、江戸時代の初期、1653(承応2)年に完成した人工の上水道です。現在、羽村市の「羽村取水堰(ぜき)」から杉並区の「高井戸公園」付近まで地上の水路が続いています。造られた当時は新宿区の「四谷大木戸」まで約43kmありました。玉川上水の始まりの場所には、水路を造った功労者として「玉川兄弟」の像が建てられています。羽村取水堰から四谷大木戸まではわずかな高低差しかありません。2人は当時の測量器具を使い、わずか8カ月で100mごとに約21cmずつ掘り下げていくという精密な工事を成功させたと言われています。玉川上水の水は今でも、「村山・山口貯水池」や浄水場などに送られ、飲み水として使われています。
水路に沿って遊歩道が整備されている所も多く、都民のいこいの場として活用されています。
東京水道名所「玉川上水」|東京都水道局
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kouhou/meisho/tamagawa.html
2023年6月1日(木)
「村山・山口貯水池」

 東京都は7つの「東京水道名所」を選定し、水道施設の魅力を発信しています。
東京都は7つの「東京水道名所」を選定し、水道施設の魅力を発信しています。「西武園ゆうえんち」のそばにある「村山上貯水池(多摩湖)」、「村山下貯水池(多摩湖)」、「山口貯水池(狭山湖)」の周辺にはサイクリングも楽しめる遊歩道が整備され、多くの人たちが集まります。貯水池の水は「東村山浄水場」に送られ、都民の飲み水になっています。
3つの貯水池にある取水塔はそれぞれデザインが異なり、人々の目を楽しませています。村山下貯水池(1927年完成)にある取水塔の屋根は、丸い帽子の形をしています。3つの貯水池で最も古い村山上貯水池(1924年完成)にある取水塔の屋根は、四角い形をしています。そして3つの貯水池で最も大きい山口貯水池(1934年完成)にある取水塔の屋根は、とんがり帽子の形をしています。山口貯水池からは、気象条件が良いと、東京都最高峰の「雲取山(標高2017m)」をはじめとした山並みの景観が楽しめます。
東京水道名所「村山・山口貯水池」|東京都水道局
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kouhou/meisho/murayama.html
2023年6月2日(金)
「地域のシンボル」

 東京都は7つの「東京水道名所」を選定し水道施設の魅力を発信しています。
東京都は7つの「東京水道名所」を選定し水道施設の魅力を発信しています。JR常磐線「金町駅」から徒歩15分。映画「男はつらいよ」にたびたび登場する取水塔は、江戸川の水を金町浄水場へ送るための施設です。近くには「柴又帝釈天」もあり、多くの観光客が集まります。とんがり帽子の屋根が特徴の第二取水塔が造られたのは1941年。そして丸い帽子の屋根が特徴の第三取水塔は1964年の東京オリンピックの年に造られました。取水塔の設計を行ったのは東京都水道局の職員で、地域の人に親しんでもらえるように帽子のようなデザインにしたと言われています。
また東急田園都市線「桜新町駅」から徒歩7分の所にある「駒沢給水所の配水塔(1924年完成)」も、地域のシンボルとして親しまれています。施設の老朽化に伴い給水所としての機能は休止され、現在は非常用の給水槽として活用されています。王冠を模したデザインで「丘の上のクラウン」とも呼ばれ、6月7日までの水道週間の間、日没後に電飾で彩られます。
東京水道名所「金町浄水場の取水塔」|東京都水道局
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kouhou/meisho/kanamachi.html東京水道名所「駒沢給水所の配水塔」|東京都水道局
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kouhou/meisho/komazawa.html点灯期間:4月「桜新町さくらまつり」午後6時〜午後10時
6月1日〜7日「水道週間」午後6時〜午後10時
10月1日「都民の日」午後6時〜午後10時
12月31日 午後5時〜翌朝午前6時
1月1日〜3日 午後5時〜午後11時
東京水道名所|東京都水道局
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kouhou/meisho/







