 |





|
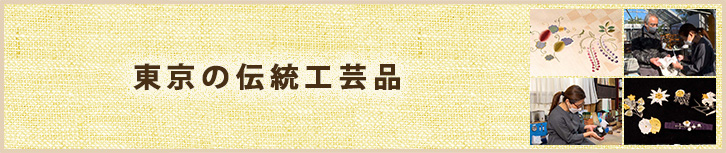
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2023年1月16日(月)
「江戸手描提灯」

 東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。
東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。そのひとつ「江戸手描提灯」は、江戸時代、提灯に屋号や家紋を描き込み、目印として使ったことから始まった工芸品。文字を太く大きく描くのが特徴です。
東京都伝統工芸士の村田修一さんに、手描きの工程を見せてもらいました。村田さんの仕事は、無地の提灯に文字や図柄を描くこと。最初に3本の突っ張り棒で提灯を広げた形に固定します。次に「ぶん回し」と呼ばれる、コンパスのような専門の道具を使って、位置決めを行います。ぶん回しの軸には針がついているので、これを提灯に刺して、家紋を描くための丸い印をつけたり、ひと文字ずつのサイズを決めたりしていきます。この印をもとに図案の下書きをし、細い筆で素描きと呼ばれる描き込みをした後、太い筆で家紋や文字の内側を塗り込みます。塗り込みをするときは提灯の骨に沿って絵の具を伸ばし、ムラがないように心掛けています。
「紋と文字のバランスの良さが江戸手描提灯の魅力」と村田さんは言います。村田さんの工房では、スマートフォンを提灯の中に収めて、光も音も同時に楽しめる現代風の提灯も製作しています。
泪橋大嶋屋提灯店
HP:https://www.namidabashi.com/
2023年1月17日(火)
「江戸刺繍」

 東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。
東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。そのひとつ「江戸刺繍」は、江戸時代に庶民の間で刺繍入りの着物が普及したことから始まった工芸品です。
東京都伝統工芸士の江上芳子さんに刺繍の技を見せてもらいました。江戸刺繍には絹糸を染めた釜糸(かまいと)を使用します。糸の色でグラデーションを作るので、江上さんは赤色だけでも50種類ほどの釜糸を用意しています。刺繍の柄や大きさによって釜糸を分け、そのつど、糸の太さを決めて、撚(よ)ってから使います。刺繍に使う針は、2.4㎝ほどの短い針。これは独特な刺繍作業台を使って布の上と下から効率よく針を操るためです。1つの作品が完成するのに1週間ほどかかるそうです。
江上さんは、友禅職人である夫・昌幸さんの反物に刺繍を施すこともあります。昌幸さんから刺繍に関する指示はなく、江上さんが自由に刺?をしているそうです。「江戸刺繍は絵と同じく、糸で自由に表現できるところが魅力」と江上さんは話していました。
江上工房
HP:https://egamikobo.com/
2023年1月18日(水)
「多摩織」

 東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。そのひとつ「多摩織」は、江戸時代に桑の生産地だった八王子を中心に始まった絹織物で、紡ぎ糸の素朴な手触りとシンプルな柄や色が特徴です。多摩織には、変り綴織(かわりつづれおり)、風通織(ふうつうおり)、お召織(おめしおり)、綟り織(もじりおり)、紬織(つむぎおり)の5種類があります。
東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。そのひとつ「多摩織」は、江戸時代に桑の生産地だった八王子を中心に始まった絹織物で、紡ぎ糸の素朴な手触りとシンプルな柄や色が特徴です。多摩織には、変り綴織(かわりつづれおり)、風通織(ふうつうおり)、お召織(おめしおり)、綟り織(もじりおり)、紬織(つむぎおり)の5種類があります。東京都伝統工芸士の澤井伸さんに、代表的な紬織の制作工程を見せてもらいました。多摩織は先に絹糸を染めてから布を織るのが基本です。今回は、乾燥させた桑の葉から煮出した染料を使って緑色の糸を作りました。紬織の糸の特徴は糸の所々にある“節”です。節によって糸に柔らかい風合いが出る、と澤井さんは言います。染め上げた糸は手織りの機械を使って縦糸を張り、そこに杼(ひ)と呼ばれる道具で横糸を絡めながら織っていきます。
手織りでは1日で2mほどしか織れないので、1つの反物が完成するのに早くても1週間ほどかかるそうです。
澤井さんの工房では、着物以外に、普段使いができる多摩織のストールなども制作しています。
澤井織物工場
住所:東京都八王子市高月町1181電話:042-691-1032
2023年1月19日(木)
「東京彫金」
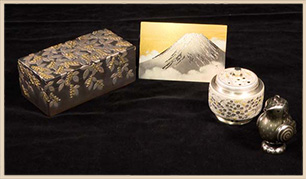
 東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。そのひとつ「東京彫金」は、江戸時代に広まり、調度品や飾り物として愛用されてきた工芸品です。
東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。そのひとつ「東京彫金」は、江戸時代に広まり、調度品や飾り物として愛用されてきた工芸品です。東京都伝統工芸士の小川真之助さんに彫金の工程を見せてもらいました。彫金で使う道具は、金槌と鏨(たがね)。鏨は彫金職人自らが作るもので、幅や角度、大きさなどによって1000本以上を使い分けているそうです。
彫金の主な材料は、金、銀、銅、鉄など。彫金制作ではまず、材料となる金属板を「ヤニ台」と呼ばれる松ヤニをつけた作業台に乗せて固定します。次に鏨を使って、「肉彫り」という技法で金属に凹凸を付けていきます。彫金には「片切り彫り」と呼ばれる日本で生まれた独特な技法もあります。これは、鏨の刃の片側を使って金属板を削り、日本画の筆がかすれるような味わいを出す技法です。
「繊細で、奥行きがあり、洒脱である。華美になり過ぎず、キラリと光るのが東京彫金の魅力」と小川さんは話していました。
小川彫金
HP:https://ogawachokin.com/
2023年1月20日(金)
「東京染小紋」

 東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。そのひとつ、「東京染小紋(そめこもん)」は、江戸時代に武士の正装・上下(かみしも)に模様を染めたことから始まり、やがて庶民に広まった、極めて小さい柄の染め物です。
東京都では、東京の風土と歴史の中で受け継がれてきた41の工芸品を「東京都伝統工芸品」に指定しています。そのひとつ、「東京染小紋(そめこもん)」は、江戸時代に武士の正装・上下(かみしも)に模様を染めたことから始まり、やがて庶民に広まった、極めて小さい柄の染め物です。東京染小紋を作り続けて60年の東京都伝統工芸士、青木啓作さんに、染小紋の作業工程を見せてもらいました。染小紋の柄のもとになるのが「型紙」です。その柄は、代表的な柄でサメの肌に似ている「鮫小紋」や、草木を模したものなど、実に様々なものがあります。そして染小紋では、染色するための色づくりが技の見せどころだといいます。青木さんは、いくつもの染料を丁寧に組み合わせて、納得する色を作っています。染料ができたら、型紙を反物に合わせ、その上に染料を乗せる「型付け」を行います。この時、ヘラの動き一つで仕上がりの生地にムラが出てしまうことがあるそうです。1枚塗ったら型紙を移動させ、「星」と呼ばれる小さな目印をたよりに型紙の位置を合わせます。最後に、染めた布を蒸して色を固定し、水で洗えば完成です。
青木さんは「細い柄を生かした作品を、世の中に出していければうれしい」と話していました。
青木染色研究所
住所:東京都八王子市叶谷町1773-5電話:042-622-5612
東京都伝統工芸品展
会期:1月18日(水)〜23日(月)
時間:午前10時30分〜午後7時30分
23日(月)は午後6時まで
会場:新宿騠島屋 11階 催会場
入場料:無料







