 |





|
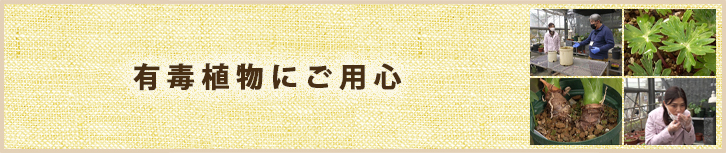
��1�T�ԕ��̓���͂�������
������������YouTube�ł�
2022�N4��11��(��)
�u�R�̌�H�@�v

 �l�X�ȐA�����萶���n�߂邱�̎����A�R�ɂ�������ȗL�ŐA���ɒ��ӂ��K�v�ł��B�����ŁA�����s��p�A�����ŎR�ƗL�ŐA������������|�C���g���f���܂����B
�l�X�ȐA�����萶���n�߂邱�̎����A�R�ɂ�������ȗL�ŐA���ɒ��ӂ��K�v�ł��B�����ŁA�����s��p�A�����ŎR�ƗL�ŐA������������|�C���g���f���܂����B�u�Z���v�Ǝ��Ă���̂��L�ŐA���́u�h�N�[���v�ł��B��H����ƁA�����f�≺���A�������Ȃǂ������N�����܂��B
��������|�C���g�͗t�́g�ɂ����h�B���������t���y������łɂ�����k���ƁA�Z���͓��L�̍��肪���܂����A�h�N�[���͍��肪���܂���B�����āu�t�L�m�g�E�v�Ƃ悭���Ă���̂��A�萁��������̗L�ŐA���u�n�V���h�R���v�B��H����ƁA�����f�₱�A�ċz��~�Ȃǂ̏d�ĂȏǏ�������N�����܂��B��������|�C���g�́g�\�ʂ̖сh�B�t�L�m�g�E�̕\�ʂɂ͔����Ȗт������Ă��܂����A�n�V���h�R���ɂ͂قƂ�ǂ���܂���B
�u�I�I�o�M�{�E�V�i�E���C�j�v�ƗL�ŐA���́u�o�C�P�C�\�E�v�́A�t�̌`���悭���Ă��܂��B��H����ƁA�����₨���f�A�������Ȃǂ̏Ǐ�������N�����܂��B��������|�C���g�͗t�́g�͗l�h�B�I�I�o�M�{�E�V�́A���S�̐��i�喬�j������ː���Ɉ͂��悤�Ȗ͗l�ł����A�o�C�P�C�\�E�͗t�̕t���������[�Ɍ������ĕ��s���̂悤�Ȗ͗l�ɂȂ��Ă���̂ŁA�������邱�Ƃ��ł��܂��B
�����s��p�A���� ��C�������̒�������́A�����������Ȃ��ꍇ�́u�̂�Ȃ��E�H�ׂȂ��E�l�ɂ����Ȃ��v�Ƃ������f���K�v���Ƙb���Ă��܂����B
2022�N4��12��(��)
�u�R�̌�H�A�v

 �R�́u�j�����\�E�v�ƌ����ڂ����Ă���̂��A�L�ŐA���́u�g���J�u�g�v�ł��B����ĐH�ׂĂ��܂��Ɖ����₨���f�A�葫�̂܂ЂȂǂ̏Ǐ�������N�����A�ň��̏ꍇ�A���Ɏ���P�[�X������܂��B��������|�C���g�́A�g�Ԃт�̐F�h�B�j�����\�E�͏t�ɔ����Ԃ��炫�A�g���J�u�g�͏H�Ɏ��F�̉Ԃ����܂��B
�R�́u�j�����\�E�v�ƌ����ڂ����Ă���̂��A�L�ŐA���́u�g���J�u�g�v�ł��B����ĐH�ׂĂ��܂��Ɖ����₨���f�A�葫�̂܂ЂȂǂ̏Ǐ�������N�����A�ň��̏ꍇ�A���Ɏ���P�[�X������܂��B��������|�C���g�́A�g�Ԃт�̐F�h�B�j�����\�E�͏t�ɔ����Ԃ��炫�A�g���J�u�g�͏H�Ɏ��F�̉Ԃ����܂��B�u���~�W�K�T�i�V�h�P�j�v���g���J�u�g�Ƃ悭���Ă���R�ł��B��������|�C���g�́A�t�́g�ꍞ�݁h�B���~�W�K�T�͗t�̐ꍞ�݂��A��̂Ђ�̂悤�Ȍ`�ł����A�g���J�u�g�̗t�ɂ͐ꍞ�݂��[�������Ă��܂��B
�u�M���E�W���j���j�N�v�ƊԈ���₷���̂��A�u�C�k�T�t�����v�̎�t�ł��B�萶���n�߂邱�̎����A�悭���Ă���̂Œ��ӂ��K�v�ł��B����ăC�k�T�t������H�ׂĂ��܂��ƁA�����f�≺���Ȃǂ̏Ǐ�������N�����A�d�ǂ̏ꍇ�͎��Ɏ���P�[�X������܂��B��������|�C���g�͗t�́g�ɂ����h�B�t���y�����݁A�ɂ�����k���ƁA�M���E�W���j���j�N�̓j���j�N�̂悤�Ȃɂ��������܂����A�C�k�T�t�����͓��ɂɂ��������Ȃ��Ƃ������Ƃŋ�ʂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
2022�N4��13��(��)
�u�Ϗܗp�A���̌�H�v

 ���{�����ōł������A���̌�H���̂��A�u�j���v�ƊԈႦ�āu�X�C�Z���v��H�ׂĂ��܂��Ƃ������̂ł��B�X�C�Z������H����ƁA�����f�≺���Ȃǂ̏Ǐ�������N�����܂��B��������|�C���g�́A�g�ɂ����h�ł��B�j���̗t���y�����ނƓ��L�̂ɂ��������܂����A�X�C�Z���͂ɂ��������܂���B�j���ƃX�C�Z���͌����ڂ��ƂĂ����Ă��邽�߁A�����ꏊ�ł͍͔|���Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��ƂĂ���ł��B
���{�����ōł������A���̌�H���̂��A�u�j���v�ƊԈႦ�āu�X�C�Z���v��H�ׂĂ��܂��Ƃ������̂ł��B�X�C�Z������H����ƁA�����f�≺���Ȃǂ̏Ǐ�������N�����܂��B��������|�C���g�́A�g�ɂ����h�ł��B�j���̗t���y�����ނƓ��L�̂ɂ��������܂����A�X�C�Z���͂ɂ��������܂���B�j���ƃX�C�Z���͌����ڂ��ƂĂ����Ă��邽�߁A�����ꏊ�ł͍͔|���Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��ƂĂ���ł��B���|�A���Ƃ��Ďs�̂���Ă���u�O�����I�T�v���L�ŐA���̂ЂƂB�肪�o��O�̋����́A�u���}�C���v�Ɏ��Ă��邽�߁A���ӂ��K�v�ł��B����ĐH�ׂĂ��܂��ƁA���M�₨���f�A����̋@�\�s�S�Ȃǂ̏Ǐ�������N�����A�ň��̏ꍇ�A���Ɏ���P�[�X������܂��B��������|�C���g�́A�g�Ђ����h�B���}�C���ɂ͑S�̂ɂЂ��̂悤�ȍ��������Ă��܂����A�O�����I�T�̋����ɂ͂���܂���B�܂����}�C���͂��肨�낷�ƔS��C������܂����A�O�����I�T�̋����͂��肨�낵�Ă��S��C���o�Ȃ��Ƃ����̂������ł��B
�t�ɉԂ��炩����u�J�����C�i�W���X�~���v�́A���̖��O�ɘf�킳��₷���L�ŐA���ł��B�W���X�~�����Ɏg����ԂƊԈ���Ĉ���ł��܂��A�H���ł��N���������Ⴊ����܂��B�W���X�~�����Ɏg����̂́A�}�c���J�̔����Ԃł����A�J�����C�i�W���X�~���͉��F���Ԃ��炩���܂��B
2022�N4��14��(��)
�u���̌�H�v

 ���Ɏ��Ă���L�ŐA���ɂ����ӂ��K�v�ł��B
���Ɏ��Ă���L�ŐA���ɂ����ӂ��K�v�ł��B�u�T�g�C���v�Ƃ悭���Ă���L�ŐA�����u�N���Y�C���v�B�N���Y�C���ƃT�g�C���̗t�͔��ɂ悭���Ă��āA���Ƃł���������̂�������߁A���ɒ��ӂ��K�v�ł��B��H����ƁA���̒�����ꂽ��A�ݒɂȂǂ̏ǏN�����肵�܂��B�܂��A�s��܂����肵�����Ȃǂɐ��ݏo�ė���`�ɐG���ƁA�畆�����N�������Ƃ�����܂��B��������|�C���g�́A�g�����̌`�h�B�T�g�C���͂����܂��ɂȂ��Ă��܂����A�N���Y�C���͖_��ɂȂ��Ă��܂��B
�u�S�{�E�v�Ƃ悭���Ă���̂��A�L�ŐA���u�`���E�Z���A�T�K�I�v�̍��B��H����ƁA�����f��ċz�̗���Ȃǂ̏Ǐ�������N�����܂��B��������|�C���g�͍��́g��v���h�B�S�{�E�̍����@�ێ��Ő܂�ɂ����̂ɑ��A�`���E�Z���A�T�K�I�̍��͔�r�I�܂�₷���̂������ł��B�t�́h�������h�ɂ��Ⴂ������A�S�{�E�̗t�́A�n���̍��̕������璼�ڐ����Ă��܂����A�`���E�Z���A�T�K�I�̗t�͌s�̕������琶���Ă��܂��B
�����s��p�A���� ��C�������̒�������́A�����������Ȃ��ꍇ�A�u�̂�Ȃ��E�H�ׂȂ��E�l�ɂ����Ȃ��v�Ƃ������f���K�v���Ƙb���Ă��܂����B
�����s�̃z�[���y�[�W���́u��������v�ł́A�L�ŐA���̌���������������Ă���w�ߘa3�N�x �H�̈��S�s���u���g����H�ׂ���H�L�ŐA���̌��������u���h�x�̓�����A5��9���܂ŃI�����C���Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B
�ߘa3�N�x�@�H�̈��S�s���u��
�u����H�ׂ���H�L�ŐA���̌��������u���v5��9���܂Ŕz�M
�����s�����ی���HP�Fhttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/forum/tominkoza/tominkozar3-4.html
2022�N4��15��(��)
�u��p�A�����̖����v
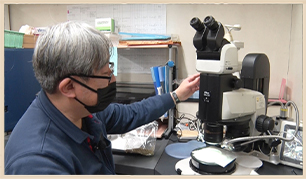
 �����s�ɂ��铌���s��p�A�����ł́A��������i�Ɏg����750��ވȏ�̐A�����͔|���A��p�A���̐������m���̕��y�Ȃǂ��s���Ă��܂��B
�����s�ɂ��铌���s��p�A�����ł́A��������i�Ɏg����750��ވȏ�̐A�����͔|���A��p�A���̐������m���̕��y�Ȃǂ��s���Ă��܂��B�͔|�������ł́A��ɐA���̊ӕʎ������s���Ă��܂��B�s�̂���Ă��錒�N�H�i�ȂǂɁA�{���͈��i�ł����g���Ȃ��悤�Ȍ��ޗ��̐A�������݂��ĂȂ����A���������g���Ċm�F���Ă��܂��B�Ⴆ�A���ޗ��Ɂu���C�{�X�v�ƋL�ڂ���Ă��钃�t���ӕʂ���ꍇ�A�������Ŋg�債�����t�����C�{�X�̕W�{�ƌ���ׂȂ���A���f���Ă����܂��B�A���̕W�{��5000�_�ȏ�B�����i�K�œ������ς����̂ɂ��Ή��ł���悤�ɁA�W�{�Ɏg���A���������ō͔|���Ă��܂��B
�܂�������p�A�����ł́A�@���ŋK������Ă���u�P�V�v�͔̍|�����ʂɍs���Ă��܂��B�P�V����Ƃ��u�A�w���v�́A���ɖړI�ŗp�������×p�����q�l�̌����Ƃ��ė��p����Ă��܂��B�P�V�����ō͔|����Ă���̂́A��w�E��w�n�̊w���ɑ��Č��C���s�����߂ł�����܂��B��N5����{����ɂ́A���J�̃P�V�̉Ԃ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�����s��p�A����
�Z���F�����s�����s������21-1
�d�b�F042-341-0344
HP�Fhttps://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/lb_iyaku/plant/
���ŐV�̊J������HP�ł��m�F��������
�@







