 |





|
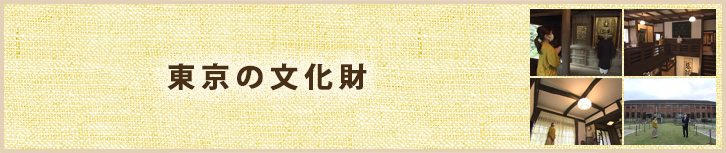
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2021年10月25日(月)
「猪方小川塚古墳」

 今年新たに東京都の史跡に指定された、狛江市にある「猪方小川塚(いのがたおがわづか)古墳」。7世紀半ばに造られたと言われる円形型の古墳で、現在は公園として整備され、ガラス越しに実物の石室を見学することができます。石室の壁面は多摩川の“泥岩(でいがん)”を積み上げて作られていて、ノミのような工具で加工した痕跡も残されています。狛江市では、これまでに約70の遺構や古墳などが見つかっており、付近一帯が大昔から人が暮らしやすい環境だったと考えられています。これまで狛江市では、5世紀から6世紀に造られた、頂上に埋葬するタイプの古墳が確認されていましたが、この猪方小川塚古墳は狛江市で初めて発見された「横穴式石室古墳」です。この周辺の地域が、別の場所から新たな技術を持った人々がやってくることを繰り返しながら発展してきたことが伺える、歴史の変遷を考える上でも大変貴重な古墳とされています。
今年新たに東京都の史跡に指定された、狛江市にある「猪方小川塚(いのがたおがわづか)古墳」。7世紀半ばに造られたと言われる円形型の古墳で、現在は公園として整備され、ガラス越しに実物の石室を見学することができます。石室の壁面は多摩川の“泥岩(でいがん)”を積み上げて作られていて、ノミのような工具で加工した痕跡も残されています。狛江市では、これまでに約70の遺構や古墳などが見つかっており、付近一帯が大昔から人が暮らしやすい環境だったと考えられています。これまで狛江市では、5世紀から6世紀に造られた、頂上に埋葬するタイプの古墳が確認されていましたが、この猪方小川塚古墳は狛江市で初めて発見された「横穴式石室古墳」です。この周辺の地域が、別の場所から新たな技術を持った人々がやってくることを繰り返しながら発展してきたことが伺える、歴史の変遷を考える上でも大変貴重な古墳とされています。古墳から出土した鉄製の矢尻や耳飾りなどの副葬品は、10月30日に公園内で特別に公開される予定です。
猪方小川塚古墳公園
住所:東京都狛江市猪方3-21-29電話:電話03-3430-1111(狛江市役所)
HP:https://www.komae.ed.jp/index.cfm/12,990,58,html
※駐車場はありません
特別公開
10月30日(土)午前10時〜午後3時副葬品の展示や解説などが行われます
※建屋の中には入れません
2021年10月26日(火)
「木造大日如来坐像」

 八王子市にある龍見寺(りゅうけんじ)は1598年に創建されたと言われる名刹で、東京都指定有形文化財の「木造大日如来坐像(だいにちにょらいざぞう)」が安置されています。境内の奥深くに建てられた大日堂は1381年に建立され、寺が開かれる前から仏像が置かれていたと伝えられています。ここで、普段は公開されていない“秘仏”を特別に見せてもらいました。「木造大日如来坐像」は平安時代末期に作られたと言われ、仏像の表面には、当時施された“金”が今もそのまま残されています。細身の体や、柔和な顔、半眼の目などに当時の作品の特徴が良く表れているそうです。専門家によると、衣の柔らかな表現が特に秀逸で、作者が判明すれば国宝に値するとも評されています。この仏像は、10月31日のみ特別に公開されます。
八王子市にある龍見寺(りゅうけんじ)は1598年に創建されたと言われる名刹で、東京都指定有形文化財の「木造大日如来坐像(だいにちにょらいざぞう)」が安置されています。境内の奥深くに建てられた大日堂は1381年に建立され、寺が開かれる前から仏像が置かれていたと伝えられています。ここで、普段は公開されていない“秘仏”を特別に見せてもらいました。「木造大日如来坐像」は平安時代末期に作られたと言われ、仏像の表面には、当時施された“金”が今もそのまま残されています。細身の体や、柔和な顔、半眼の目などに当時の作品の特徴が良く表れているそうです。専門家によると、衣の柔らかな表現が特に秀逸で、作者が判明すれば国宝に値するとも評されています。この仏像は、10月31日のみ特別に公開されます。龍見寺
住所:東京都八王子市館町1630電話:042-664-1630
HP:https://www.ryukenji.jp/
特別公開
10月31日(日)午前10時〜正午・午後2時〜4時
2021年10月27日(水)
「日本民藝館」

 目黒区にある日本民藝(みんげい)館は、暮らしの中の日用品などに美術的な価値を見いだす「民芸運動」の提唱者、柳宗悦(やなぎむねよし)によって1936(昭和11)年に建てられた美術館で、1万7000点以上の作品が収蔵されています。展示品の一つ、囲炉裏で使用される「自在鉤(じざいかぎ)」。名もなき職人による凝ったデザインと、使い込むことで生まれた独特の風合いが、その美術的価値を高めています。建物自体にも民芸の美的感覚が反映されている日本民藝館は、「民芸運動」の活動拠点としての文化的価値が認められ、今年新たに東京都の有形文化財に指定されました。木造2階建ての建物の外観は和風建築の美しさを表現する漆喰の「蔵造り」ですが、入口を入った正面には洋館を思わせる大きな階段があり、和洋折衷の空間になっています。また、階段の手すりや柱、窓枠、展示ケースなどのあらゆる角が“面取り”されていて、細部にわたり職人の手仕事を見ることができます。全ての部屋に障子を設置し、柔らかな外光で暖かい空間を作っていることも特徴の一つで、この空間自体を楽しむ客も多くいるそうです。日本民藝館の担当者は、「多くの人に通ってもらい使い込まれることで、美しさが磨かれていく美術館」と話しています。
目黒区にある日本民藝(みんげい)館は、暮らしの中の日用品などに美術的な価値を見いだす「民芸運動」の提唱者、柳宗悦(やなぎむねよし)によって1936(昭和11)年に建てられた美術館で、1万7000点以上の作品が収蔵されています。展示品の一つ、囲炉裏で使用される「自在鉤(じざいかぎ)」。名もなき職人による凝ったデザインと、使い込むことで生まれた独特の風合いが、その美術的価値を高めています。建物自体にも民芸の美的感覚が反映されている日本民藝館は、「民芸運動」の活動拠点としての文化的価値が認められ、今年新たに東京都の有形文化財に指定されました。木造2階建ての建物の外観は和風建築の美しさを表現する漆喰の「蔵造り」ですが、入口を入った正面には洋館を思わせる大きな階段があり、和洋折衷の空間になっています。また、階段の手すりや柱、窓枠、展示ケースなどのあらゆる角が“面取り”されていて、細部にわたり職人の手仕事を見ることができます。全ての部屋に障子を設置し、柔らかな外光で暖かい空間を作っていることも特徴の一つで、この空間自体を楽しむ客も多くいるそうです。日本民藝館の担当者は、「多くの人に通ってもらい使い込まれることで、美しさが磨かれていく美術館」と話しています。日本民藝館
住所:東京都目黒区駒場4-3-33電話:03-3467-4527
HP:https://mingeikan.or.jp/
2021年10月28日(木)
「柳澤家住宅」

 世田谷区にある「柳澤家住宅」は“民芸建築”を今に伝える貴重な建物として国の有形文化財に登録されています。約600坪の敷地の奥に、通常は公開されていない15坪ほどの家屋があります。書道家の柳澤君江の住居として1951年に建てられ、暮らしの日用品などに美術的な価値を見いだす「民芸運動」の美的感覚が建築に取り入れられています。木造平屋建ての外壁には漆喰が使われ、玄関は石が敷かれた土間風の造りになっています。玄関を上がると8畳の居間。居間は板張りの上に絨毯が敷かれた洋風の雰囲気ですが、床の間や湾曲した梁など和風の要素も取り入れられています。このように洋間の中に和の伝統を入れることも民芸建築の特徴と言われています。居間の隣は、小上がりになった4畳半の和室。段差を設けることで、居間で椅子に座る人と、和室で畳に座る人の目線の高さが合うように工夫されています。古民家の知恵や文化が大きな財産として残されている柳澤家住宅は、10月30・31日の2日間、特別に公開されます。
世田谷区にある「柳澤家住宅」は“民芸建築”を今に伝える貴重な建物として国の有形文化財に登録されています。約600坪の敷地の奥に、通常は公開されていない15坪ほどの家屋があります。書道家の柳澤君江の住居として1951年に建てられ、暮らしの日用品などに美術的な価値を見いだす「民芸運動」の美的感覚が建築に取り入れられています。木造平屋建ての外壁には漆喰が使われ、玄関は石が敷かれた土間風の造りになっています。玄関を上がると8畳の居間。居間は板張りの上に絨毯が敷かれた洋風の雰囲気ですが、床の間や湾曲した梁など和風の要素も取り入れられています。このように洋間の中に和の伝統を入れることも民芸建築の特徴と言われています。居間の隣は、小上がりになった4畳半の和室。段差を設けることで、居間で椅子に座る人と、和室で畳に座る人の目線の高さが合うように工夫されています。古民家の知恵や文化が大きな財産として残されている柳澤家住宅は、10月30・31日の2日間、特別に公開されます。柳澤家住宅
住所:東京都世田谷区大原1-26-1電話:03-3556-0031(柳澤君江文化財団)
HP:https://www.facebook.com/yanagisawakimie/
特別公開
10月30・31日 午前10時〜午後4時(最終入場:午後3時30分)
2021年10月29日(金)
「日本初の近代下水道施設」

 日本初の近代下水道施設として国の重要文化財に指定されている「旧三河島汚水処分場ポンプ場施設」。隅田川の中流にあり、1922(大正11)年に運用が開始されました。現在は運用を終えていますが、長い間、下水を地上の浄化施設に送る役割を果たしてきました。広い敷地の中ほどに「沈砂池(ちんさち)」と呼ばれる大きな溝があります。下水に含まれる土砂類を沈ませ、取り除くための施設で、この技術は現在の処理施設にも用いられています。その奥にあるのはポンプが設置されている大きなポンプ室。日本人の技師が設計した建物は強度を保つために鉄筋コンクリート造りですが、当時、下水道技術では最先端だったヨーロッパにならい、外壁にレンガ風のタイルをあしらっています。建設当時は「ゐのくち式渦巻ポンプ」という、日本独自に開発した毎秒約1tの汲み上げ能力を持つポンプが設置されていました。技術の進歩と共に新しいポンプに入れ替えられ1999年まで運用が続けられました。一方、建物自体は一度も建て替えられることなく、当時のままの姿を残しています。さらに当時使われていた、下水道や地下施設も公開されています。
日本初の近代下水道施設として国の重要文化財に指定されている「旧三河島汚水処分場ポンプ場施設」。隅田川の中流にあり、1922(大正11)年に運用が開始されました。現在は運用を終えていますが、長い間、下水を地上の浄化施設に送る役割を果たしてきました。広い敷地の中ほどに「沈砂池(ちんさち)」と呼ばれる大きな溝があります。下水に含まれる土砂類を沈ませ、取り除くための施設で、この技術は現在の処理施設にも用いられています。その奥にあるのはポンプが設置されている大きなポンプ室。日本人の技師が設計した建物は強度を保つために鉄筋コンクリート造りですが、当時、下水道技術では最先端だったヨーロッパにならい、外壁にレンガ風のタイルをあしらっています。建設当時は「ゐのくち式渦巻ポンプ」という、日本独自に開発した毎秒約1tの汲み上げ能力を持つポンプが設置されていました。技術の進歩と共に新しいポンプに入れ替えられ1999年まで運用が続けられました。一方、建物自体は一度も建て替えられることなく、当時のままの姿を残しています。さらに当時使われていた、下水道や地下施設も公開されています。旧三河島汚水処分場ポンプ場施設
住所:東京都荒川区荒川8-25-1電話:03-6458-3940(東京都下水道サービス)
HP:https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/business/b4/guide/s-mikawa/07-01/index.html
見学受付(東京都下水道サービス)
HP:https://www.tgs-yoyaku.jp/mikawashima/※見学には、電話またはインターネットでの予約が必要です
東京文化財ウィーク2021
電話:03-5320-6862(東京都教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当)
HP:https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/week.html







