 |





|
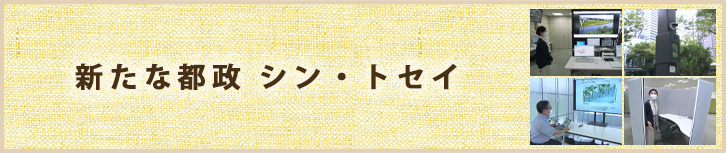
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2021年9月20日(月)
「デジタル化の推進」

 東京都では「シン・トセイ」と銘打ち、行政手続きや防災、混雑緩和など、さまざまなサービスを向上させるため「デジタル化」を活用した都政の構造改革を進めています。
東京都では「シン・トセイ」と銘打ち、行政手続きや防災、混雑緩和など、さまざまなサービスを向上させるため「デジタル化」を活用した都政の構造改革を進めています。都庁では、デジタル化を進める一環として「未来型オフィス」を設置しました。従来の書類に囲まれたオフィスと違い個人専用のデスクはなく、働く場所を自由に選ぶことができるオープンスペースになっています。ペーパーレス化も進んでいて、「シン・トセイ」の取り組みを始める前の2019年7月時点と比べFAX使用量は約95%削減されました。
また、さまざまな行政手続きをオンライン化することで、都民がどこからでも都庁にアクセスできる「バーチャル都庁構想」という取り組みも行っています。
このほか、道路の混雑状況をデジタルデータ化し混雑緩和に繋げるプロジェクトや、最新の通信技術を活用した農業の遠隔支援、河川や港湾の状況をリアルタイムで配信する防災情報の発信など、さまざまな分野でデジタル化を進めています。
2021年9月21日(火)
「デジタル化で混雑緩和」

 東京都では、デジタル化や通信技術の整備を始めとした都政の構造改革を進めています。
東京都では、デジタル化や通信技術の整備を始めとした都政の構造改革を進めています。この一環として混雑緩和に向けた様々な取り組みがあります。都庁周辺の歩道には、センサーで人の流れなどを解析する「スマートポール」が設置され、時間帯別の歩行者数やマスクの装着率などを分析したり、歩行者と自転車の判別や、歩行者の年代の解析などを行っています。これらの検証を活かし、自動配送ロボットの運用も期待されています。また、3Dのデジタルマップで都市部を再現し、混雑緩和に向けた街づくりに活かすプロジェクトもあります。さらにスマートフォンアプリ「都営交通アプリ」では、都営地下鉄の車両別の混雑予測を知ることができます。
都営交通アプリ
HP:https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/app.html2021年9月22日(水)
「最先端の農業支援」

 東京都が行っている都政の構造改革の一環として、デジタル化による農業支援の研究が行われています。
東京都が行っている都政の構造改革の一環として、デジタル化による農業支援の研究が行われています。そのひとつが東京の限られた農地の中で収穫量を増やす研究。東京都農林総合研究センターでは、デジタル化による遠隔システムで作物を栽培する施設を開発しました。作物の生育状況に合わせ温度や湿度、二酸化炭素の濃度などを自動で制御することで、例えばトマトは、ほぼ1年中収穫が可能になり、畑栽培に比べ5倍以上の収穫量があるそうです。施設内には遠隔操作が可能な高解像度カメラが複数設置されていて、作物の栄養状態や生育状況を見守ることができます。さらに、現場にいる人が「スマートグラス」という端末を使うことで、離れた場所にいる人が、通話しながら葉の裏側など見えにくい部分を確認することができます。
農業に関わる人の高齢化が進む中、東京都では、このような農業支援の研究によって、新たに農業に従事した人でも安定した収穫が得られるよう研究に力を入れています。
東京型スマート農業プロジェクト
HP:https://www.tokyo-aff.or.jp/site/smartagri/2021年9月23日(木)
「防災情報の発信」

 東京都は、都政の構造改革「シン・トセイ」の一環として、河川の氾濫や高潮など防災情報の発信力を強化しています。東京都では今年6月から、都民の的確な避難を促すため、YouTubeに「東京都水防チャンネル」を開設し、河川に設置した監視カメラのリアルタイムの映像を24時間配信しています。集中豪雨などで河川の水位が急激に上昇した際、河川の様子を見に行くことは非常に危険なため、この配信を利用してもらいたいと東京都の担当者は話しています。また、高潮災害に対応するため、YouTube「東京都高潮防災チャンネル」も開設し、24時間、潮位の状況が確認できる映像の配信も行っています。
東京都は、都政の構造改革「シン・トセイ」の一環として、河川の氾濫や高潮など防災情報の発信力を強化しています。東京都では今年6月から、都民の的確な避難を促すため、YouTubeに「東京都水防チャンネル」を開設し、河川に設置した監視カメラのリアルタイムの映像を24時間配信しています。集中豪雨などで河川の水位が急激に上昇した際、河川の様子を見に行くことは非常に危険なため、この配信を利用してもらいたいと東京都の担当者は話しています。また、高潮災害に対応するため、YouTube「東京都高潮防災チャンネル」も開設し、24時間、潮位の状況が確認できる映像の配信も行っています。さらに東京都のホームページでは、想定できる最大規模の高潮による氾濫が起きた時に、それぞれの地域がどのくらい浸水するかを表示した、高潮災害の予測マップを公開しています。
東京都水防チャンネル
HP:https://www.youtube.com/channel/UCaydvLwWthLMbfKLEQSY2UQ東京都高潮防災チャンネル
HP:https://www.youtube.com/channel/UCHasOi3-m3IgOy0OBvm85qA高潮リスク検索サービス
HP:https://bp1.basepage.com/pub/hazard/map.html
2021年9月24日(金)
「キャッシュレス化」

 東京都が取り組む都政の構造改革「シン・トセイ」の一環として、都税などのキャッシュレス化が進んでいます。スマートフォンを利用しての都税納付は、すでに可能になっています。都税の納付書のバーコードを民間の決済アプリで読み取ることで、簡単に支払い手続きができるというものです。さらに、水道・下水道料金もスマートフォンの決済アプリで納付することができます。また、都立施設でもキャッシュレス化が進められ、現在42の都立施設で入場料や利用料をクレジットカードや電子マネーで支払うことができます。東京都では来年3月までに78の都立施設でキャッシュレス化を完了する予定で、スポーツ施設などの予約もオンラインでできるように整備を進める予定です。
東京都が取り組む都政の構造改革「シン・トセイ」の一環として、都税などのキャッシュレス化が進んでいます。スマートフォンを利用しての都税納付は、すでに可能になっています。都税の納付書のバーコードを民間の決済アプリで読み取ることで、簡単に支払い手続きができるというものです。さらに、水道・下水道料金もスマートフォンの決済アプリで納付することができます。また、都立施設でもキャッシュレス化が進められ、現在42の都立施設で入場料や利用料をクレジットカードや電子マネーで支払うことができます。東京都では来年3月までに78の都立施設でキャッシュレス化を完了する予定で、スポーツ施設などの予約もオンラインでできるように整備を進める予定です。都税の支払い方法
HP:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/common/tozei_nouzei.html水道・下水道料金の支払い方法
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/ryokin/shiharai/シン・トセイ 都政の構造改革ポータルサイト
HP:https://shintosei.metro.tokyo.lg.jp/







