 |





|
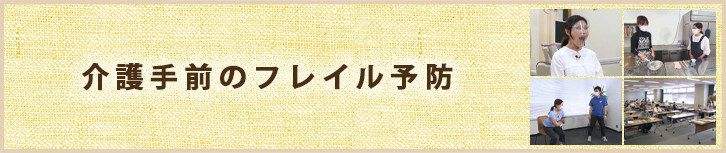
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2021年7月5日(月)
「運動・栄養・社会参加」

 年齢と共に気力や体力が低下し、介護が必要になる直前の状態を“フレイル”と言います。「1kmを休まずに歩けない」「家の中でつまづくことがある」「転ぶことが怖くて外出を控えている」などに当てはまる場合、フレイルの可能性があります。
年齢と共に気力や体力が低下し、介護が必要になる直前の状態を“フレイル”と言います。「1kmを休まずに歩けない」「家の中でつまづくことがある」「転ぶことが怖くて外出を控えている」などに当てはまる場合、フレイルの可能性があります。筋力が衰え、基礎代謝が低下し食欲がなくなることで栄養不足に陥り、さらに筋力が衰えるという悪循環に陥ります。フレイルの予防には、適度な運動で筋力を保ち、食欲を増進させ、十分な栄養を摂ることで筋力を維持するという良い循環が大切です。
また栄養面から悪循環に陥る場合もあります。「食欲がない」「よく噛まなくても食べられるメニューが多い」「半年間で体重が3kg以上減少」などに当てはまる場合は注意が必要です。
フレイルの予防には、人や社会と関わる「社会参加」も大切だと言われています。フレイルは早期に対応することで健康な状態に戻ることが可能です。「運動」「栄養」「社会参加」をバランスよく続けていくことが大切です。
2021年7月6日(火)
「タンパク質をとる」

 フレイルの予防には、筋肉や骨など体の組織を作るのに必要な“タンパク質”をしっかりと摂ることが大切です。例えば体重50kgの人の場合、1日に必要なタンパク質を摂るための食材の目安は、豚ロース50g、鮭の切り身一切れ、納豆1パック、卵1個、牛乳コップ1杯。これらすべてを摂る必要があります。食材によってタンパク質の種類が異なるため、できるだけ多くの品目を食べるのが理想です。高齢になると“硬い”“脂っこい”などの理由で敬遠されがちな肉ですが、簡単なひと工夫で食べやすくする調理法を教えてもらいました。鶏肉を袋に入れ、すりおろした玉ねぎやニンニク、しょうがと、はちみつなどを混ぜた合わせ調味料に30分ほど漬けこみます。弱火で5分程蒸し焼きにし、中まで火を通せば出来上がりです。
フレイルの予防には、筋肉や骨など体の組織を作るのに必要な“タンパク質”をしっかりと摂ることが大切です。例えば体重50kgの人の場合、1日に必要なタンパク質を摂るための食材の目安は、豚ロース50g、鮭の切り身一切れ、納豆1パック、卵1個、牛乳コップ1杯。これらすべてを摂る必要があります。食材によってタンパク質の種類が異なるため、できるだけ多くの品目を食べるのが理想です。高齢になると“硬い”“脂っこい”などの理由で敬遠されがちな肉ですが、簡単なひと工夫で食べやすくする調理法を教えてもらいました。鶏肉を袋に入れ、すりおろした玉ねぎやニンニク、しょうがと、はちみつなどを混ぜた合わせ調味料に30分ほど漬けこみます。弱火で5分程蒸し焼きにし、中まで火を通せば出来上がりです。一度作れば1カ月ほど冷凍保存ができる“味付けそぼろ”もおススメです。牛・豚・鶏など、好きなひき肉を使い、ご飯やおかゆ、冷やっこなどに乗せることで毎日手軽にタンパク質を補うことがでます。
2021年7月7日(水)
「噛む力・飲み込む力を鍛える」

 フレイルの予防にはバランスの良い食事が大切ですが、普段から軟らかいものばかり食べていて、噛む力・飲み込む力が衰えると十分な栄養が摂れずフレイルになりやすいといわれています。こめかみと頬に手を当て奥歯を噛んだ時、顔の筋肉が動かない場合、フレイルの可能性があります。
フレイルの予防にはバランスの良い食事が大切ですが、普段から軟らかいものばかり食べていて、噛む力・飲み込む力が衰えると十分な栄養が摂れずフレイルになりやすいといわれています。こめかみと頬に手を当て奥歯を噛んだ時、顔の筋肉が動かない場合、フレイルの可能性があります。衰えた筋肉を改善するための運動があります。まずは口を大きく開く動きと、しっかりと奥歯を噛む動きを繰り返し、噛む力を鍛えます。次に舌をできるだけ伸ばす運動。舌を動かすと喉の筋肉が刺激され、飲み込む力を鍛えることに繋がります。そして額に手を当て、押し合うように力を入れる運動でも喉の筋肉を鍛えることができます。さらに“ブクブクうがい”や“ガラガラうがい”を 普段よりも長く、多めに行うことで顔の筋肉が刺激され、フレイル予防に効果があるといわれます。
2021年7月8日(木)
「毎日の運動」

 家にいる機会が多くなり運動量が減るとフレイルになりやすいと言われています。予防には運動を習慣づけ、筋力を維持することが大切です。東京都健康長寿医療センター研究所と慶応義塾大学の共同開発で、スマートフォンを使い、家の中で楽しみながら運動を続けられる「運動カウンター」というアプリを作りました。
家にいる機会が多くなり運動量が減るとフレイルになりやすいと言われています。予防には運動を習慣づけ、筋力を維持することが大切です。東京都健康長寿医療センター研究所と慶応義塾大学の共同開発で、スマートフォンを使い、家の中で楽しみながら運動を続けられる「運動カウンター」というアプリを作りました。LINEアプリで二次元コードを読み取ると、「運動カウンター」を“友だち”に追加する画面になり、“友だち”に追加するとすぐに利用することができます。トーク画面に移ると「つまさきあげ」や「かかとあげ」など、フレイルの予防に効果的な、主に足の筋肉を鍛える8つの運動が表示されます。行いたい運動のイラストに触れるとその運動の説明と動画が送られ、運動の姿勢などを確認しながら実践できるようになっています。運動を終えると、実践した回数を記録することができます。記録を付けるとアプリ内で植物が育ち、1週間のうち5日以上運動できれば花を咲かせることができます。
運動カウンター
HP:https://www.healthy-aging.tokyo/top#h.ve9d1qqtxz1t運動カウンター・二次元コード
HP:https://line.me/R/ti/p/%40587yehld
2021年7月9日(金)
「社会参加で健康づくり」

 フレイルの予防には「運動」や「栄養」のほか、人や社会と繋がりを持つ「社会参加」が大切だと言われています。家にいる機会が多い今、高齢者が交流できる場をどうやって作るかが課題になっています。
フレイルの予防には「運動」や「栄養」のほか、人や社会と繋がりを持つ「社会参加」が大切だと言われています。家にいる機会が多い今、高齢者が交流できる場をどうやって作るかが課題になっています。先月、大田区ではフレイル予防の指導者を養成する講座が開かれました。参加者は、高齢者が集まる様々な市民グループなどでリーダーを務めている人達です。講座では、参加者が家族や友人、グループのメンバーにフレイル予防のポイントをしっかり伝えられるように、筋力を保つ運動などを実践を交えながら学んでいました。
この講座には、コロナ禍で外出などが難しい中、リーダーにフレイル予防を広めてもらい、地域の高齢者が交流や社会参加できる機会を作る狙いもあります。この日参加していた地域のシニアグループのリーダーを務める女性は、講座で学んだことを高齢者との交流のきっかけにしたいと考え、「訪問や対面が難しい中、ひとりで暮らしている人に電話などでコミュニケーションを繋げていきたい」と話していました。
東京都介護予防・フレイル予防ポータル
HP:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kaigo_frailty_yobo/index.html







