 |





|
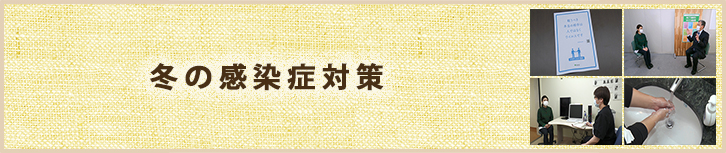
2020年12月7日(月)
「マスクで予防 新型コロナ」

 11月から感染者数が増加している新型コロナウイルス。都立墨東病院の感染症科の医師によると、湿度や気温が下がると、ウイルスが空気中に漂う時間が長くなり、感染リスクが上がるそうです。感染予防の基本的な対策は「マスクの着用・手洗い・“密”を避ける」です。特に乾燥する冬場は飛沫が飛びやすくなるため、マスクの着用が欠かせません。マスクを着用することで飛沫を70%減らせるというデータもあるそうです。また冬場は、換気の頻度が減ることも感染リスクの増加に繋がるため、室温18℃以上、湿度40%以上を目安に、1時間に5〜10分程度の換気が推奨されています。
11月から感染者数が増加している新型コロナウイルス。都立墨東病院の感染症科の医師によると、湿度や気温が下がると、ウイルスが空気中に漂う時間が長くなり、感染リスクが上がるそうです。感染予防の基本的な対策は「マスクの着用・手洗い・“密”を避ける」です。特に乾燥する冬場は飛沫が飛びやすくなるため、マスクの着用が欠かせません。マスクを着用することで飛沫を70%減らせるというデータもあるそうです。また冬場は、換気の頻度が減ることも感染リスクの増加に繋がるため、室温18℃以上、湿度40%以上を目安に、1時間に5〜10分程度の換気が推奨されています。また、SNSなどで感染者に対して心無い書き込みがされたり、医療関係者やその家族が差別を受ける事例があります。東京都では、新型コロナウイルス感染症に関連した差別や人権侵害などについての相談窓口を設置しています。
東京都人権プラザ 一般相談
電話:03-6722-01242020年12月8日(火)
「新型コロナ 感染拡大防止」

 感染の拡大が続く新型コロナウイルス。東京感染症対策センターの専門家に、家庭や職場など感染リスクの高い場面での対策を聞きました。
感染の拡大が続く新型コロナウイルス。東京感染症対策センターの専門家に、家庭や職場など感染リスクの高い場面での対策を聞きました。家庭内で感染者が出た場合、感染者と家族の部屋を分け、互いにマスクを着用し、話す時間も15分以内にするなど対策が必要です。トイレや洗面台など共有して利用する場所や、ドアノブなど手に触れる場所の消毒も有効です。そして職場や学校なども感染リスクが高い場所です。特に休憩時間中、気が緩みマスクを外して会話をすることで感染するケースがあるそうです。さらに会食時は人との距離が近く、マスクを外して食事をします。大声を控え、会話をする時はハンカチで口を覆うなど対策が大切です。また病院などでの感染を避けるため、受診する前に電話相談することが大切です。東京都ではかかりつけ医がいない場合などの相談窓口を設置しています。
東京都発熱相談センター
電話:03-5320-45922020年12月9日(水)
「インフルエンザ」

 例年冬場に流行し、突発的な高熱や全身の倦怠感などを引き起こすインフルエンザ。今年は新型コロナウイルスへの対策により、インフルエンザの感染者が少ないと言われています。これは感染経路が似ているため、新型コロナウイルスの予防策がそのまま応用できるからだそうです。予防にはマスクはもちろん、手洗いも重要です。せっけんやハンドソープを使い流水で手洗いすることで、手についたウイルスの数が1万分の1に減ると言われています。また“リラックス・睡眠・適度に運動”などウイルスに対する免疫力を高める生活習慣も大切です。そしてインフルエンザの発症や重症化を抑える予防接種も重要です。特に高齢者の場合は予防接種により死亡リスクが約5分の1になると言われています。予防接種の効果は、接種してから約2週間後にあらわれ、5カ月間続くと言われています。
例年冬場に流行し、突発的な高熱や全身の倦怠感などを引き起こすインフルエンザ。今年は新型コロナウイルスへの対策により、インフルエンザの感染者が少ないと言われています。これは感染経路が似ているため、新型コロナウイルスの予防策がそのまま応用できるからだそうです。予防にはマスクはもちろん、手洗いも重要です。せっけんやハンドソープを使い流水で手洗いすることで、手についたウイルスの数が1万分の1に減ると言われています。また“リラックス・睡眠・適度に運動”などウイルスに対する免疫力を高める生活習慣も大切です。そしてインフルエンザの発症や重症化を抑える予防接種も重要です。特に高齢者の場合は予防接種により死亡リスクが約5分の1になると言われています。予防接種の効果は、接種してから約2週間後にあらわれ、5カ月間続くと言われています。2020年12月10日(木)
「ノロウイルス」

 冬場に流行するノロウイルス感染症。嘔吐や下痢などを引き起こし脱水症状がひどくなるため、回復力の弱い子どもや高齢者は重症化しやすく、また吐物をのどに詰まらせ窒息する危険性もあるため注意が必要です。ノロウイルスは感染力が強く、わずかな量でも感染します。ノロウイルスに汚染された食品を加熱不十分な状態で食べるなど、口からウイルスが侵入することで感染することが多いと言われています。ノロウイルスは熱に弱いため、食材の中心温度が85〜90℃になるよう90秒以上加熱したり、調理器具を熱湯消毒することが推奨されています。また吐物を処理する際に感染するケースもあるため、処理をする時は手袋をつけ、処理後の手洗いや処理に使ったタオルなどを洗濯する前に熱湯消毒することも重要です。テーブルや床など嘔吐した場所の消毒も欠かせません。ノロウイルスに対しては通常のアルコール消毒では十分な効果が得られないため、ノロウイルスの消毒に効果がある“次亜塩素酸”の使用が有効です。
冬場に流行するノロウイルス感染症。嘔吐や下痢などを引き起こし脱水症状がひどくなるため、回復力の弱い子どもや高齢者は重症化しやすく、また吐物をのどに詰まらせ窒息する危険性もあるため注意が必要です。ノロウイルスは感染力が強く、わずかな量でも感染します。ノロウイルスに汚染された食品を加熱不十分な状態で食べるなど、口からウイルスが侵入することで感染することが多いと言われています。ノロウイルスは熱に弱いため、食材の中心温度が85〜90℃になるよう90秒以上加熱したり、調理器具を熱湯消毒することが推奨されています。また吐物を処理する際に感染するケースもあるため、処理をする時は手袋をつけ、処理後の手洗いや処理に使ったタオルなどを洗濯する前に熱湯消毒することも重要です。テーブルや床など嘔吐した場所の消毒も欠かせません。ノロウイルスに対しては通常のアルコール消毒では十分な効果が得られないため、ノロウイルスの消毒に効果がある“次亜塩素酸”の使用が有効です。2020年12月11日(金)
「発熱時の見きわめ方」

 少し体調を崩しただけでも新型コロナウイルスの感染が心配になる今。風邪のような症状が出た時にどうすればよいか、都立墨東病院の感染症科の医師に聞きました。“微熱”や“せき”など、初期段階で新型コロナウイルスか他の感染症かを判別するのは難しいため、受診のタイミングがポイントになります。普段健康な成人の場合、風邪であれば3〜4日目をピークに徐々に改善しますが、症状が続く場合は新型コロナを疑い、医療機関に電話で相談することが大切です。高齢者や持病がある人の場合は、軽い症状でも早期にかかりつけ医に相談することが重要です。早い段階で新型コロナだと分かれば、承認済みの薬を使うことで重症化を抑える効果が期待できます。特に高齢者の場合、“熱”や“せき”などの症状がはっきりしない場合もあり、“食欲がない”など普段との違いに周りの人が気づくことも大切です。
少し体調を崩しただけでも新型コロナウイルスの感染が心配になる今。風邪のような症状が出た時にどうすればよいか、都立墨東病院の感染症科の医師に聞きました。“微熱”や“せき”など、初期段階で新型コロナウイルスか他の感染症かを判別するのは難しいため、受診のタイミングがポイントになります。普段健康な成人の場合、風邪であれば3〜4日目をピークに徐々に改善しますが、症状が続く場合は新型コロナを疑い、医療機関に電話で相談することが大切です。高齢者や持病がある人の場合は、軽い症状でも早期にかかりつけ医に相談することが重要です。早い段階で新型コロナだと分かれば、承認済みの薬を使うことで重症化を抑える効果が期待できます。特に高齢者の場合、“熱”や“せき”などの症状がはっきりしない場合もあり、“食欲がない”など普段との違いに周りの人が気づくことも大切です。東京都発熱相談センター
電話:03-5320-4592東京都福祉保健局
HP:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/







