 |





|
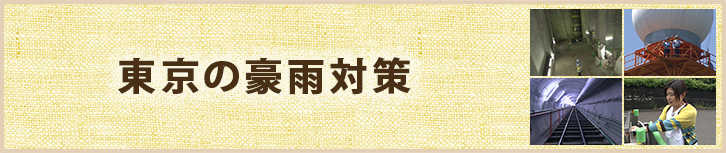
2018年6月11日(月)
「渋谷駅地下の巨大貯留施設」

 再開発が進む渋谷駅東口の地下では雨水を貯留する巨大な施設を建設中です。渋谷の地形はその名の通り谷になっていて、大量の降水があると渋谷駅構内や周辺では浸水被害が発生しています。工事現場の地下に降りていくと、地下約13m地点に到着します。ここでは地下鉄やJRの駅につながる予定の東口地下広場の建設が行われています。この真上には暗渠にした渋谷川が流れています。更に下へと螺旋階段を下りていくと、地下約25m地点に大きな貯留施設が広がっていました。この施設は1時間75mmの豪雨に対応しており、完成すると25mプール13杯分に匹敵する約4000トンの雨水を貯留することが可能となります。渋谷駅前の地下にこのような巨大な施設があるとは驚きです。再開発で広い場所が確保できたからこそ、巨大な雨水貯留施設を作ることができたのです。2020年の稼動を目指して工事が進められています。
再開発が進む渋谷駅東口の地下では雨水を貯留する巨大な施設を建設中です。渋谷の地形はその名の通り谷になっていて、大量の降水があると渋谷駅構内や周辺では浸水被害が発生しています。工事現場の地下に降りていくと、地下約13m地点に到着します。ここでは地下鉄やJRの駅につながる予定の東口地下広場の建設が行われています。この真上には暗渠にした渋谷川が流れています。更に下へと螺旋階段を下りていくと、地下約25m地点に大きな貯留施設が広がっていました。この施設は1時間75mmの豪雨に対応しており、完成すると25mプール13杯分に匹敵する約4000トンの雨水を貯留することが可能となります。渋谷駅前の地下にこのような巨大な施設があるとは驚きです。再開発で広い場所が確保できたからこそ、巨大な雨水貯留施設を作ることができたのです。2020年の稼動を目指して工事が進められています。2018年6月12日(火)
「下水道の役割を知る」

 東京都虹の下水道館は、下水道管の役割や水環境の大切さを楽しみながら学べる東京都の施設です。下水道というと生活排水の処理のイメージがありますが、雨水の処理も、浸水から街を守るための重要な役割です。館内に入るとまず、内径約2mの実物大の下水管模型「どかんビジョン」が。大雨が降ったときには満杯になることもあるそうです。都内には内径8.5mの大きさの下水管もあるそうです。下水管に流れた雨水はポンプ所まで運ばれ、そこから水再生センターへ送られますが、多量な雨水の場合はそのまま海や河川へ放流されます。中央監視室のコーナーでは、ポンプ操作の体験ができるようになっています。水位と雨の動きを見比べながら複数のポンプを操作することができ、楽しみながら中央監視室の仕事が分かるようになっています。
東京都虹の下水道館は、下水道管の役割や水環境の大切さを楽しみながら学べる東京都の施設です。下水道というと生活排水の処理のイメージがありますが、雨水の処理も、浸水から街を守るための重要な役割です。館内に入るとまず、内径約2mの実物大の下水管模型「どかんビジョン」が。大雨が降ったときには満杯になることもあるそうです。都内には内径8.5mの大きさの下水管もあるそうです。下水管に流れた雨水はポンプ所まで運ばれ、そこから水再生センターへ送られますが、多量な雨水の場合はそのまま海や河川へ放流されます。中央監視室のコーナーでは、ポンプ操作の体験ができるようになっています。水位と雨の動きを見比べながら複数のポンプを操作することができ、楽しみながら中央監視室の仕事が分かるようになっています。6月は浸水対策強化月間でパネル展示を行っています。
虹の下水道館
住所:江東区有明2-3-5 有明水再生センター5階電話:03-5564-2458
開館時間:午前9時30分〜午後4時30分
※入館は4時まで
休館日:月曜(祝日の場合は翌日)
HP:http://www.nijinogesuidoukan.jp/
2018年6月13日(水)
「東京アメッシュ」

 東京アメッシュは下水道局が配信するリアルタイムの降雨情報が分かるサービスです。訪れたのは稲城市にある稲城レーダー基地局。高台に建てられたレーダー塔を梯子で昇ること約10分、レーダーが置かれている地上60mの高さからは遠くに新宿高層ビル群を見ることが出来ます。ここからレーダーが半径80キロの範囲を観測、港区の施設と合わせて2カ所で東京都全域をカバーしているそうです。次に訪れたのは東京都下水道局北部下水道事務所。この施設の屋上に地上雨量計が設置されています。地上雨量計は天秤のような構造になっており、片方に雨水が0.5mm貯まると、ししおどしのようにカタンと倒れるようになっています。この倒れた回数から1時間の降水量を計測しています。レーダーと地上雨量計で得られた降雨情報は中央情報処理装置でまとめられ、東京アメッシュのデータが作られます。東京アメッシュの情報は5分毎に更新され、一般の方もスマートホンやPCで利用することができます。お出かけや洗濯などの参考として便利な東京アメッシュ。是非チェックしてみてください。
東京アメッシュは下水道局が配信するリアルタイムの降雨情報が分かるサービスです。訪れたのは稲城市にある稲城レーダー基地局。高台に建てられたレーダー塔を梯子で昇ること約10分、レーダーが置かれている地上60mの高さからは遠くに新宿高層ビル群を見ることが出来ます。ここからレーダーが半径80キロの範囲を観測、港区の施設と合わせて2カ所で東京都全域をカバーしているそうです。次に訪れたのは東京都下水道局北部下水道事務所。この施設の屋上に地上雨量計が設置されています。地上雨量計は天秤のような構造になっており、片方に雨水が0.5mm貯まると、ししおどしのようにカタンと倒れるようになっています。この倒れた回数から1時間の降水量を計測しています。レーダーと地上雨量計で得られた降雨情報は中央情報処理装置でまとめられ、東京アメッシュのデータが作られます。東京アメッシュの情報は5分毎に更新され、一般の方もスマートホンやPCで利用することができます。お出かけや洗濯などの参考として便利な東京アメッシュ。是非チェックしてみてください。東京アメッシュ
HP:http://tokyo-ame.jwa.or.jp/(東京アメッシュサイト)
2018年6月14日(木)
「田柄川地下の浸水対策」

 現在、板橋区の田柄川緑道の地下では全長4.2kmの第二田柄川幹線工事が行われています。
現在、板橋区の田柄川緑道の地下では全長4.2kmの第二田柄川幹線工事が行われています。1958(昭和33)年9月の台風22号で氾濫した田柄川は、現在暗渠となり田柄川幹線として利用されています。
しかし、2005(平成17)年9月に大雨で浸水被害が発生。田柄川幹線の更に下に新たな幹線工事が始まりました。
工事現場の地下18mに降りると、内径3.5mの大きな幹線が現れます。中を進んで行くと幹線が大きくカーブしていることが分かります。これは上部を流れる田柄川幹線と同じ形に、カーブも合わせて工事が進められているためです。約1時間歩くと、工事の先端部分に到着します。先端部では大きなシールドマシンと呼ばれる掘削機が穴を掘り、セグメントと呼ばれる下水管の内側となる部品をはめ込んで組み立てていきます。1日に10m〜14m程掘り進んでいるそうです。
完成すると1時間50mmの豪雨に対応できるそうです。
2018年6月15日(金)
「浸水への備え」
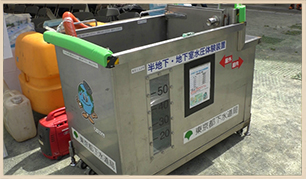
 大雨やゲリラ雷雨で浸水した場合、ドアにかかる水圧がどれほどなのか知っていますか?
大雨やゲリラ雷雨で浸水した場合、ドアにかかる水圧がどれほどなのか知っていますか?実際にその水圧を体験できる装置が“水圧くん”です。水深20cmの場合にかかる水圧は14.0kgで、女性でも扉を押すと少し抵抗があるくらいでドアは開きます。しかし、水深40cmになると水圧は4倍の56.0kgにもなり、女性や子ども、高齢者には開けるのが難しくなります。
港区と消防署、東京都下水道局などで行われた合同水防訓練では、水圧くんが展示され実際に体験する方々も。また訓練で作っていたのが家屋などへの浸水を軽減する「土のう」や「水のう」。「簡易水のう」は家庭にあるゴミ袋で簡単に作ることができます。45リットル入りのゴミ袋の半分から半分弱ほど水を入れ、口をしばると完成です。袋を二重にすると更に丈夫になります。いくつか作り、浸水を防ぎたい場所に並べておくことで簡易的な止水ができます。また、段ボールにいれることで高さも出て、浸水をより軽減できます。
■東京都下水道局総務部広報サービス課
電話:03-5320-6515
HP:http://www.gesui.metro.tokyo.jp/







