 |





|
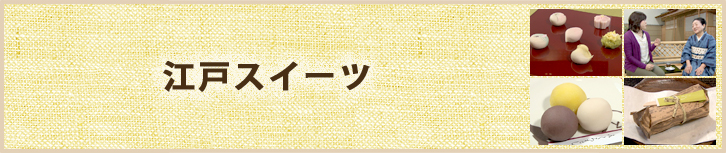
2014年4月7日(月)
「榮太樓總本鋪 甘名納糖」
 江戸末期の1857年創業の榮太樓總本鋪。157年の歴史を誇る榮太樓が、創業時から作り続けているのが甘名納糖。一般的に甘納豆と呼ばれるものの元祖と言われています。
江戸末期の1857年創業の榮太樓總本鋪。157年の歴史を誇る榮太樓が、創業時から作り続けているのが甘名納糖。一般的に甘納豆と呼ばれるものの元祖と言われています。材料は皮が硬く、江戸時代には専ら赤飯などに用いられた金時大角豆。普段あまり利用されない豆を安く仕入れ、多くの人においしい菓子を…という初代の思いが込められているそうです。材料も製法も当時のままで手間暇かかるため、限定生産。販売は本店のみです。
榮太樓總本鋪 日本橋本店
住所:東京都中央区日本橋1-2-5電話:03-3271-7785
営業時間:午前9時30分〜午後6時
定休日:日曜、祝日
HP:http://www.eitaro.com/
2014年4月8日(火)
「塩瀬総本家 本饅頭」
 室町時代の1349年創業の塩瀬総本家。中国から日本に来た林淨因が奈良に住み、饅頭を作って売り出したのがその始まりと言われています。その後、室町幕府第8代将軍・足利義政から直筆の看板も贈られました。
室町時代の1349年創業の塩瀬総本家。中国から日本に来た林淨因が奈良に住み、饅頭を作って売り出したのがその始まりと言われています。その後、室町幕府第8代将軍・足利義政から直筆の看板も贈られました。塩瀬総本家の看板商品は大和芋を使った皮で包んだ志ほせ饅頭。代々受け継がれてきた秘伝の味です。また、志ほせ饅頭と並ぶもう一つの看板商品が本饅頭。徳川家康が1575年の長篠の戦いに出陣する際、献上されたそうです。
塩瀬総本家 本店
住所:東京都中央区明石町7-14電話:03-3541-0776
営業時間:午前9時〜午後7時
定休日:日曜、祝日
HP:http://www.shiose.co.jp/
2014年4月9日(水)
「向島 言問団子」
 江戸末期創業の向島言問団子。隅田川にかかる言問橋の名前の元となった老舗団子屋です。植木職人の外山佐吉が茶菓子として団子をふるまったのがその始まりで、店名は平安時代の歌人、在原業平が隅田川で詠んだとされる和歌“名にし負はばいざ言問はむ都鳥…”に由来するそうです。
江戸末期創業の向島言問団子。隅田川にかかる言問橋の名前の元となった老舗団子屋です。植木職人の外山佐吉が茶菓子として団子をふるまったのがその始まりで、店名は平安時代の歌人、在原業平が隅田川で詠んだとされる和歌“名にし負はばいざ言問はむ都鳥…”に由来するそうです。名物の言問団子は小豆餡と白餡と味噌餡の三色。食感が命のため賞味期限は当日限り。店内には言問団子を愛した、宇野千代さんら女流作家の寄せ書きも…。
向島 言問団子
住所:東京都墨田区向島5-5-22電話:03-3622-0081
営業時間:午前9時〜午後6時
定休日:火曜
HP:http://kototoidango.co.jp/
2014年4月10日(木)
「麻布青野総本舗 鶯もち」
 江戸末期の1856年創業の麻布青野総本舗。創業当時の六本木は大名下屋敷や神社仏閣があり、狸もいたそうです。
江戸末期の1856年創業の麻布青野総本舗。創業当時の六本木は大名下屋敷や神社仏閣があり、狸もいたそうです。麻布青野総本舗で最も歴史あるのが豆大福。塩味を効かせ甘さを抑えた逸品です。そして一番人気が鶯もち。松尾芭蕉が詠んだとされる一句“鶯をたづねたづねて阿左布まで”に因み、昭和28年に4代目の青野平九郎さんが作りました。舞台俳優だった平九郎さんの兄に、「楽屋で汚さず食べられる菓子を」と頼まれ考案したそうです。
麻布青野総本舗
住所:東京都港区六本木3-15-21電話:03-3404-0020
営業時間:午前9時30分〜午後7時
※土曜、祝日は午後6時まで
定休日:日曜
HP:http://www.azabu-aono.com/
2014年4月11日(金)
「福島家 上生菓子」
 150年以上続く巣鴨の和菓子屋、福島屋。季節を表現した上生菓子が並びます。
150年以上続く巣鴨の和菓子屋、福島屋。季節を表現した上生菓子が並びます。春の上生菓子、染井吉野は桜の花びらとお酒を入れるひょうたんのデザインを組み合わせ、お花見を表現したもの。製法は創業当時から受け継がれ、様々な道具や技法を使って繊細な上生菓子が作られます。また1867年に初代が作ったと言われる、420ものお菓子の絵が描かれた見本帳も残されていて、見本帳を元に再現された上生菓子も販売されています。
福島家
住所:東京都豊島区巣鴨2-1-1電話:03-3918-3330
営業時間:午前9時〜午後7時30分
定休日:水曜







