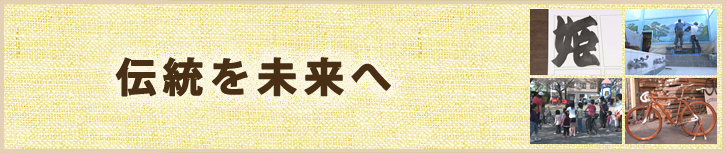|




 |
2011年5月9日(月)
寄席文字の魅力

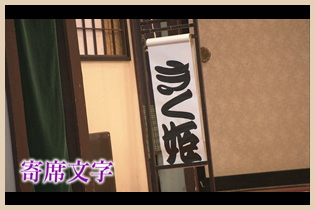
落語の寄席などで目にする「寄席文字」。
江戸時代には、貼られた紙がビラビラとなびくことから“ビラ字”と呼ばれていました。
書家の春亭右乃香さんに、寄席文字の書き方を教わりました。
右乃香さんは大学時代に落語研究会に所属し、寄席文字の第一人者、
橘右近さんの勉強会に参加し、その魅力にひかれ、弟子入りしました。
寄席文字は、お客さんが隙間なく入るように、太く隙間なく書くことが特徴です。
春亭右乃香さんによる
寄席文字の講座については
毎日文化センター(03-3213-4768)まで 寄席文字の講座については
講座名「江戸の文字とデザイン」
2011年5月10日(火)
和綴じの魅力
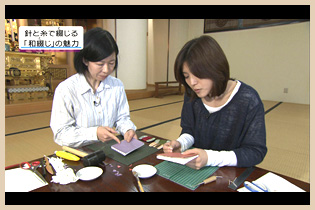 きょうは「和綴じ」。
きょうは「和綴じ」。針と糸で束ねる“和綴じ”は、平安時代に考案されたと言われる製本技術です。
台東区にある緑泉寺の青江住職は、写経会で使った和紙を、
“本にしたら愛着がわくのでは”と考え、
豆本作家の蔦谷さんと一緒に、『和綴じで綴じる写経入門』講座を始めました。
きく姫も体験しました。
和綴じで綴じる写経入門』講座については
浄土真宗東本願寺派 緑泉寺(03-3841-0076)まで
HPにて告知も行っています「彼岸寺」
2011年5月11日(水)
銭湯絵師
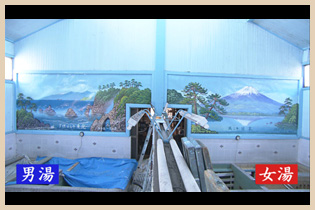 きょうは銭湯のペンキ絵を描く「銭湯絵師」。
きょうは銭湯のペンキ絵を描く「銭湯絵師」。中島盛夫さんはこの道47年。銭湯のペンキ絵は、
大正時代に都内の銭湯で描かれたのが始まりと言われています。
中島さんに6年前に弟子入りした、田中みずきさん。
彼女は、空や雲、松などを描くことを任されています。
銭湯絵師 中島さん・田中さんの活動については、
田中みずきさんのブログで紹介
田中みずきさんのブログで紹介
2011年5月12日(木)
街頭紙芝居
 きょうは「街頭紙芝居」。
きょうは「街頭紙芝居」。昭和初期には、都内に2000人近くいたと言われている紙芝居業者。
デジタルコンテンツクリエーターの佐々木遊太さんは、
国立市を中心に街頭紙芝居を行っています。
その、佐々木さんの街頭紙芝居を、きく姫も子どもたちと一緒に楽しみました。
“即興紙芝居”も人気です。
佐々木遊太さんの活動については
ささき製作所2011年5月13日(金)
木製の自転車
 きょうは「木製の自転車」。
きょうは「木製の自転車」。“SANOMAGIC”。 船大工の佐野末四郎さんは、
“江戸時代から続く船大工の技術を形にして残したい”と、
2007年に木製の自転車を製作しました。
木製の自転車はロードレース用。
ひとつひとつ手作業でつくるため、1台を作るのに約3カ月かかります。
サドルの下の部分を作る作業を見せていただきました。