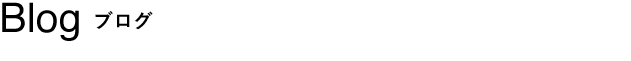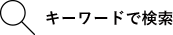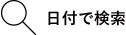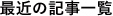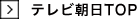- トップ
- ブログ
- 勝者なき選挙
- 2025年07月21日
参議院選挙の結果が出た。与党である自民・公明の両党は合わせて目標の50議席に届かず、負けた。これで衆議院に続いて参議院でも少数与党に転落である。自民党は劣勢が伝えられた選挙区で議席を死守したところもあったが、1人区では明らかに力負けしたところが目立った。一方、公明党は支持母体の創価学会の集票力の減退が止まらない。自公は大敗と言える。
では野党は勝ったのか。僕はそう思わない。
立憲民主党は現状維持だった。与党が沈んだのに野党第1党が議席を伸ばせない。それどころか、比例代表では4位に沈んだ。選挙区では茨城選挙区の敗北がショックだったのではないか。定員2のこの選挙区は、自民と立憲の指定席、つまりは無風区と見られていた。なのに、立憲は新興勢力の参政党に負けて3位に甘んじ、議席を失った。有権者は2議席ある中で1議席も立憲に与えることを許さなかったのだ。このことが象徴するように、今回の参院選は、立憲にとっての敗北の選挙だったと僕は考える。
共産党の衰退も激しい。改選議席の半分にも届かなかった。
では国民民主党はどうなのか。改選議席の4倍を超える躍進である。去年の衆議院選挙に続いて大いに議席を伸ばした。「手取りを増やす夏」というキャッチコピーは、物価高に苦しむ現役世代の胸に刺さった。定員7の東京選挙区では、自民も立憲も果たせなかった公認候補2人の当選を実現した。比例代表では得票数で自民党に次いで2位へと浮上した。
しかし、国民はこれで勝利と言えるのか。僕はそうは思わない。国民に問われるのは、むしろ「これから」だからである。
「選挙ステーション」の放送中、玉木雄一郎代表に率直に聞いた。「自公の連立政権に加わり、総理大臣を取りに行ってはどうですか」。
これにはひとつの前提がある。与党が衆参において少数に転じた中、野党系が力を結集すれば与野党逆転による政権交代が起きる可能性は理論的にはある。しかし、現実には野党は多党化が進み、リベラルから保守までその主張はあまりに幅広く、ひとつにまとまるのはほぼ不可能という前提である。
質問の場面に戻る。やや挑発的な問いかけに、玉木代表はすこし言いよどんだように思えた。そして、石破政権の間は連立を組むことはないと明言した。いわゆる「年収の壁」の引き上げや、ガソリン減税といった与党との政策合意を、石破政権は守らなかったからだという。信義の問題だから譲れないということだろう。
だが、あくまで石破茂氏が総理大臣を続ける限り、ということであり、「今後の自民党内政局を見極めたい」とも玉木氏は語った。トップが替わり、自らが訴える政策の実現がある程度担保されるのであれば、連立政権入りもありうるという考えと受け取った。
僕が「連立政権に加わってはどうか」と言ったのは、別に国民民主をひいきしているからではない。責任政党としての、それこそひとつの責任の取り方だと思うからだ。
今回の参院選で、確かに有権者は自公による石破政権に鉄槌を下した。しかし、日本の政治がより不安定になり、混乱することを望んでいるわけではないはずだ。あくまで、よい政治を行ってほしいと願っているだけだ。
では、躍進した政党が果たすべき役割は何か。それは、帆にはらんだ有権者の期待を形にすることであり、そのためには政権与党になることが一番の近道だ。
実は同じ質問を、立憲民主党の小川淳也幹事長にもぶつけてみた。与党第1党と野党第1党が連立政権を作ることを「大連立」と呼ぶ。小川幹事長は、「大連立は、いわゆる日本有事や、極めて大規模な災害などの場合に限られる」として、自公政権との大連立を言下に否定した。あくまで選挙によって第一党になり、政権の獲得を目指すのが筋だという。
しかし僕は食い下がった。「物価高、トランプ関税のごり押し。これはある種の有事ではないか」。しかし、小川幹事長は原則を崩すことはできないという。本当にそんな場合なのか。「危機的状況」という言葉を何度も繰り返して選挙を戦ってきたのはあなた方ではないのか。
「危機的状況」を強調して大躍進したのが参政党だ。この政党の実体はまだわからないことが多いが、コツコツと地方組織を固めてきた生真面目さは評価できそうだ。しかし、その主張は危うさをはらむ。そのひとつが女性にまつわる神谷宗幣代表の一連の発言だ。「高齢の女性は子どもを産めない。若い女性に子どもを産みたいという社会状況を作らないといけないが、働け、働けとやり過ぎた」と彼は繰り返した。
「生物学的に当たり前のことを言ったまでだ」と神谷代表は説明した。だが、その説明をそのまま受け入れる自分がいるとすれば、それは少し待った方がいい。そもそも子どもを産む、産まないはその人それぞれの生き方の選択の問題である。また、産みたいと思っても仕事との両立が難しくて悩む人も多いし、子どもが欲しくても残念ながら授からない人がいる。
そうしたセンシティブな問題に対し、政治家が上から目線で女性の生物学的特徴を殊更にいうのはあまりに傲慢だ。標的となる人たちを傷つけることにもなる。何より、余計なお世話と言っていい。
排他的だと批判された外国人政策にしても然りだが、難しい問題を一刀両断に言語化して見せるテクニックには気を付けた方がいい。それによって、「言いにくいことを言ってくれた」と留飲を下げる人がいれば、それと同じだけ、あるいはそれ以上、傷ついたり苦しい思いをする人がいる。そこに委細構わず、世の中に潜在的にある怒りや不安に火をつけて回る政治手法を「ポピュリズム」と言う。番組中に僕が神谷代表に「あなたの手法はポピュリズムではないですか」とたずねたのは、そこに懸念を覚えたからだ。
国民に対して説得力を持ったメッセージを発することは政治家の資質として重要だ。しかし、説得力を保ちつつ抑制的に言葉を発することはもっと重要だと思う。神谷代表にはいまのところその姿勢が欠けているように見える。幅広い国民を包摂する政治活動は、ファンミーティングとは違うのだ。
大躍進した参政党は勝利したのか。その評価をする段階ではないだろう。スタートラインに立ったまでだ。大事なのは、これからこの新興政党がどのような政治手法を取り、どの道を歩むのかだ。
さて、最後に大敗した自民党の今後である。もともと低すぎるとも言われた与党50議席の勝敗ラインを、石破総理は割りこんでしまった。しかし、石破総理は退陣を否定した。
政治家の出処進退は自分で決めることなので、僕がどうこう言うことは控えたい。ただ、確実に言えるのは、自民党に対して突き付けられた今回の選挙結果は、単なる表紙を変えれば済むレベルではないということだ。
今回は岩盤保守層が参政党に、リベラルな保守層が国民民主党に流れた、などと分析してみても、ではそうした層が次に自民党に戻って来ると考えるのは甘い。いくつかの選挙戦を取材して感じたのだが、今回、自民党は逆風に負けたのではない。逆風すら吹いていなかった。自民党の周辺には、ただ冷たい風が漂っていただけだった。
石破総理は番組中のインタビューで、物価高対策は減税でなく、給付金とする理由などを延々と述べた。頭の中は選挙戦の最中のままのようだ。政権を引き続き運営するのなら、民意を踏まえて新たな政策の選択肢を持つべきだ。他党に対して協力を呼びかけ、新たな連立の道を模索することは当然だと考える。国民は自説に拘泥する脆弱な政権など望んではいないのだ。
(2025年7月21日)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)