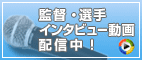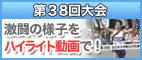全日本大学駅伝とは
大学駅伝の歴史
全日本大学対抗駅伝は、1970年3月、産声を上げた。
当時すでに、1920年スタートの箱根駅伝が伝統のある大学駅伝として知られる存在であった。しかしそれはあくまで関東学連の主催であり、関東の大学生しか出場できない。全国の学生長距離ランナーは、地方出身者であろうとも関東の大学を目指してしまうわけだ。全国の大学が参加できる、真の日本一決定戦を開催できないものか、そんな思いを持つ人は少なくなかった。
そんななか、当時の東海学連会長・梅村清明氏は、熱田神宮〜伊勢神宮を走る駅伝の復活を考えていた。昭和12年から同23年まで、第2次大戦による3年間の中断を除く8回、東海学生駅伝として行われたそのレースは「参宮駅伝」として人気を博していた。日本の中心に位置する東海エリアで、大学駅伝日本一決定戦として、参宮駅伝を再生させようというのだ。
そして時を同じくして、朝日新聞名古屋本社に東海地区でのイベントを企画する動きがあった。愛知県下での印刷再開が戦後20周年を迎えていたのだ。東海学連OBであり同新聞の波藤雅明記者は、全国大学駅伝の企画提案をした。梅村氏と波藤氏は愛知一中陸上部の先輩後輩の間柄であり、話は一気に加速した。
そしてスタートしたのが、全日本大学対抗駅伝だった。
しかし、障害も少なくなかった。箱根駅伝より格上となる駅伝に関東学連としては抵抗感があったし、当時は高度経済成長の真っ只中。車の通行を規制して、スポーツを執り行うのは否定的な意見も多かったのだ。その2つとも、粘り強い交渉によって、解決していった。当時最強だった日体大が参加を決めたことも大きかった。
1970年〜1979年
第1回は、6地区学連の20校が参加、8区間118kmで競技された。国道をなるべく避けたコース設定で、近鉄電車を横切るため、4区間ずつ前後半に分割されていた。
記念すべき初代王者は、予想通り日体大だった。後半雪が降るという、天候的にもレース展開的にも激しいレースとなったが、結果的には2位を5分近く離して勝利だった。
そして、2位には福岡大が食い込んだ。箱根駅伝への特別参加を何度も願い出、そのつど却下されてきた経緯があり、日大、大東大など関東の大学を抑えたこの結果は、全日本大学対抗駅伝の開催意義を高めたといえるだろう。
その後、第2回以降は、1月の開催に変更された。第2回〜第3回と制したのは、初代王者。日体大の3連覇を見ることとなった。そしてその牙城を崩したのは大久保初男などを擁した大東大で、第4回から第7回まで4連覇とあっさりライバル越えを果たす。しかし第8回〜第9回は再び日体大が連覇し、第11回でも王座に復帰する。このとき日体大には中村孝生と新宅雅也という名ランナー2枚を揃えていたのだった。
第10回大会では、近鉄電車との平面交差を解消し、前後半の分断のない7区間109.4kmでの開催となった。そして、記念すべきこの大会は、史上初の快挙がなされる。福岡大が初優勝を果たしたのだ。高校までの有望選手は関東の大学に進みがちなので、この優勝は地方大学には格別の意味があったのだ。こつこつと選手を育て上げてきた金森勝也監督の指導には、賞賛の声が上がった。福岡大はこの後、翌年の2位を経て、第12回、第13回と通算3回の優勝を果たしている。これは現在も関東勢以外の最多優勝である。
1980年〜1988年
第11回〜第20回も、日体大を軸に優勝争いは展開された。この間、日体大が6勝、福岡大が2勝、大東大が1勝。そしてもう1勝は、京都産業大学だった。同校が優勝したのは第17回。それまで14回連続出場ながら最高は7位。一気に駆け上がった快挙だった。現在に至るまで、福岡大を除く関東以外の学校が全日本を制したのは、このときだけである。また、第12回〜14回、後のマラソン世界王者谷口浩美が日体大のエースとして出場。第14回大会ではアンカーとして、優勝に貢献した。
第20回記念大会は、現在の日程である11月第1日曜が開催日となった大会だった。出場校も20から23に増えた。オツオリ(山梨学大)ら留学生の活躍も、この大会から始まることになる。優勝は最多の11回目となる日体大。現在もこの最多勝記録は生きているが、日体大の優勝は、このとき以来遠ざかっている。
1989年〜1997年
第21回〜第29回は、全日本大学対抗駅伝がメジャーな存在になっていった時期といえる。その立役者的存在が早大だ。第24回、初出場初優勝を果たしたのを皮切りに4連覇。スーパースター渡辺康幸を中心に花田、櫛部、武井、小林正、小林雅など、名ランナーを次々輩出。マヤカ、中村祐二などを擁した山梨学大と名勝負を繰り広げた。そして、早大の4連覇後、続いて2連覇を果たしたのが神奈川大だ。早大のようなスター選手はいなかったが、全員が力を合わせた総合力で頂点に立った。
またオープン参加としてアイビーリーグ選抜が参加したのは、第22回からだった。
1998年〜2005年
第30回から前回の第37回までは、駒大を中心とした展開となる。
第30回、後にマラソン日本最高記録を塗り替える藤田敦史がライバル三代(順天大)、古田(山梨学大)らをしのぐ区間賞をとるなど見どころたっぷりの展開で、駒大初優勝。藤田が抜けた翌年以降も、王者としての地位を固め、第31回、33回、34回、36回と日本一に輝いていく。
そんな中、第32回には名門順天大が、全日本初優勝を果たしている。後半に逆転するという、順天大らしい勝ち方だった。第35回は東海大が制した。大学三大駅伝初めての制覇、創部46年目の歓喜だった。前回、第37回を制したのは日大だ。エース・サイモンが2区で区間新を出し、他選手も安定した力を発揮。第23回の初優勝以来、2度目の栄冠に輝いた。
40回大会を目前にし、脈々と築かれる「真の大学日本一決定戦」の歴史。「強い関東」のプライド、そして、それに負けじと挑む全国の大学の激しい切磋琢磨が、日本長距離界の新たな未来を作り続けていく。
2006年
第38回は、東海大が地区予選落ちという波乱の展開の末、本大会を迎える。優勝候補には日大、日体大、順大などが挙げられたが、飛びぬけた存在はなく混戦が予想された。
そしてふたを開けると、ニューカマーの活躍が目立った。1区は城西大1年・高橋優太が、2区は日大1年・G.ダニエルが、区間賞の走りによりトップで襷をつなぐ。さらに、1区こそ12位ながらじりじり順位を上げ4区でトップに立ったのが、1年生を3人出場させ4年生はゼロで臨んだ駒大だ。
連覇への執念を見せる日大と、「目標は3位以内」という無欲の駒大が、混戦を抜け出し一騎打ちの様相に。
勝負を決したのは、6区だった。11月とは思えない暑さの中、後退する日大に対して、6区7区と区間賞の駒大がスパート。安定感抜群の襷リレーを見せ、そのままトップでゴールテープと切った。
最終区でドラマを見せたのが、山梨学大2年のM・J・モグスだ。第27回大会で早大・渡辺康幸(現早大監督)が作った56分59秒という伝説の記録を大きく上回る56分31秒。11位スタートから6人抜きでシード権獲得。優勝の駒大と同様、大きなインパクトを残した。
2007年
第39回は、伊達秀晃(4年)、佐藤悠基(3年)の2枚看板を擁する東海大が優勝候補筆頭、5000m13分台のスピードランナーを多く揃える駒大が対抗馬と目されていた。また、この年は何十年に一度と言われる学生ランナー活況の年であり、これまで伊勢路の主役を飾ってきた「四天王」と言われる4年生のエースランナーが顔を揃えるハイレベルな戦いが予想された。
いきなり驚かせたのが、日大G・ダニエル(2年)の1区起用。区間タイ記録の快走で、日大が先手を取る。2区は、駒大・宇賀地強(2年)、順大・松岡佑起(4年)、東海大・佐藤悠基(3年)、早大・竹澤健介(3年)のトップ選手による激戦となり、最後は竹澤が世界陸上代表の意地を見せ区間新記録を樹立。さらに4区では、中大・上野裕一郎(4年)が気迫のこもった走りで7人ごぼう抜きをみせた。
優勝候補筆頭の東海大が調子に乗れない中、安定した力で1区3位、2区2位、3区1位と順位を上げていったのが駒大だった。誰一人ブレーキになることなく、3人が区間賞を獲得、3区以降トップを譲らぬ圧勝で2連覇で7度目の優勝を飾った。
最後に驚かせたのが最終8区、山梨学大のM・J・モグス(3年)。13位で襷を受けると、ゴール手前の参道で6位日大をかわし、計7人抜きの爆走。大逆転でシード権を獲得した。前年の大記録をさらに約1分更新する、55分32秒の区間新記録で走り抜けたのだった。