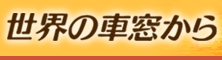   |
|
|
|
|
| トップページ > 撮影日記ページ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
撮影日記1
もう10年以上前のことだが、スリランカの友人と話したことがあって、彼は「スリランカで鉄道の旅なんて危険でできない。夜の列車に乗っていると石が飛んでくるし、銃撃されることもある」と言ったのだが、私は冗談で大げさに言っているのかと思ってつい笑ってしまい、彼をものすごく怒らせてしまったことがある。 スリランカと言えば、美しい海と宝石のイメージ。だが、少し前まで、ニュースを賑わすのは内戦の話題ばかりだった。7万人以上の犠牲者、29万人の避難民を出したといわれる内戦は2009年にようやく終結。鉄道の旅ができる時代が戻ってきた。 コロンボは、まばらに建つ高層ビルと、広い道路、そしてイギリスが建てた新古典主義っぽい建物が印象的。交通量は多く、人通りも多い。紀元前から交易港として知られていたというが、16世紀にはポルトガルが進出。シナモンを始めとするスパイスが魅力だった。彼らはコロンボの港周辺に城塞を築く。その城塞は19世紀に、島の支配を完了したイギリスによって取り壊されてしまったが、「フォート」という地名は今も残っているし、鉄道の中心も「フォート駅」。 最初に目指すのは、南部の都市ゴール。スリランカの人は「ガレ」というように発音する。2時間43分かかる予定。印刷された時刻表というものがないのが不都合だが、列車の本数が限られているので普通の利用者からすれば重要なことではないのかもしれない。
|
|
|
|
|
|
|
|
撮影日記2
スリランカにやってきたヨーロッパの国々は、良港を求め、城壁を築いて町を守った。スリランカの王が皆ヨーロッパ勢力に好意的だったわけではないし、帝国主義時代だったので、お互いに襲撃する機会を狙ってもいたのだろう。本国と同じような町を建設して、それを囲むように城壁を築いていくヨーロッパ勢力。東海岸のトリンコマリーやバッティカロアにも城壁が残っているし、島の最南端に近いマータラにも城壁があるが、ひときわ威風堂々と大規模な城壁に目を見張らされるのは西海岸のゴール。一番高くて分厚い城壁の部分はイギリスが作ったものだから、比較的新しく、海からの攻撃に対する防御よりも、陸からの攻撃に対する防御を重視した結果だという。 さて、次に乗車するのは、コロンボから東のキャンディに向かう路線。「キャンディ」という地名は子どものころから印象深かったが、今回知ったことは、キャンディはCandyではなく、さらに驚いたことは、スリランカの人の呼び方(シンハラ語)は「マハ・ヌヴァラ」で全然違うということだった。じゃあ「キャンディ」って何なの?と聞いてみると、「山」を意味する「カンダ」という言葉から外国人が勝手につけた名前なのだそう。ありがちな話。 コロンボとキャンディの間は、ICEで移動。インターシティ・エクスプレス。そういう列車が存在すること自体が意外な感じ(失礼)だったが、実際に乗ってみると、他の長距離列車との違いはほとんど感じることができなかった。
|
|
|
|
|
|
|
|
撮影日記3
キャンディは、スリランカがイギリスの植民地支配になる前の、最後の王朝の都。高地にあり、地の利を生かして敵の侵入を長い間防いできたが、1815年に滅亡した。スリランカの様々な王国の歴史には御家騒動が常につきまとっていたようで、そこに諸外国がつけ込むスキがあったようだ。交易戦略上、絶好の位置にあり、良港に恵まれていて、様々なスパイスを産出するという、スリランカの恵まれた諸条件はまた、皮肉なことに外敵に狙われる条件でもあったのだ。 キャンディ最大の見どころは、仏歯寺。文字通り、ブッダの歯を祀った寺。この歯は、ブッダが荼毘に付された際に弟子のひとりが手に入れたものとされているのだが、やがて王権の象徴となっていく。つまり、仏歯を手に入れたものが王位につくことができるということで、仏歯をめぐる戦争なども起きるようになったらしい。言い伝えによれば、やがて、この歯はこっそりとスリランカへもたらされたのだという。スリランカの仏教を信じる人々にとって、この歯はものすごい崇拝の対象のようだ。 キャンディから、線路はさらに奥へと進んでいく。次の目的地はマータレー。ちょうど、下校時刻と重なって、列車の中は制服姿の子どもたちがいっぱい。無邪気にカメラに向かって目立とうとする男の子たちに対して、すました表情で無関心を装いつつも、さりげなく髪の毛や服装を直さずにはいられない女の子たち。どちらも微笑ましい。 終点のマータレーは、思い描いていたよりもかなり大きな町だった。でも、終点まで乗ってきた人は10人に満たないほど。
|
|
|
|
|
|
|
|
撮影日記4
よく撮影では、朝夕を「魔法の時間」みたいな呼び方をするけど、スリランカでもやっぱりそれを感じることになった。午前3時半にキャンディを出発する列車でバドゥッラに向かう。どうしてこんな不便な時間に出発するのかは聞きそびれた。コロンボから、キャンディ、そして丘陵地帯を結ぶ路線が、スリランカの鉄道ではもっとも古い部分。もともとイギリスは、丘陵地帯のプランテーションで栽培したお茶の葉を、コロンボに運ぶために鉄道を建設したのだ。 キャンディを出発した列車は、真っ暗な中を走ること2時間以上。6時が近づいてくると、空が白み始め、ようやくあたりの様子が見えてくるようになる。森と茶畑が交互に現れるようになり、やがて日が昇ると斜面を覆い尽くすお茶の葉が、キラキラと輝きだす。ものすごく美しい。そこかしこには、茶摘みの人たち。朝、ちょうど作業が始まる時間なのだそうだ。 ところで、スリランカの列車では、物売りがせわしなく行き来する。なかでもよく聞かれるのが「ワデワデワデワデワデ」という声で、これはワデというお菓子を売っているのだ。カレー風味の厚手のクッキーのような菓子。大きいものだと、ひとつ20ルピー。ルピーは大雑把に言って1円の感覚。20ルピーというのが目安のようで、茹でたトウモロコシもひとつ20ルピー。ロルツというカレー風味の野菜ドーナッツのようなものも20ルピー。オレンジも20ルピーで売られていた。例外は、ヘラプという、木の葉に餅のようなものを包んだお菓子で、これは10ルピーだった。 というように、かなりいろいろなものがあるので、ひもじい思いをすることはない。が、どれも、とりたてて美味しいというわけではないのが残念なところ。お茶の産地だけに、紅茶売りの出現が期待されるところだが、それはなかった。 やがて、眼下には、雄大な山岳風景が広がる。険しい斜面のほとんどにお茶の木が植えられているのが、またすごい。日本の棚田や、ヨーロッパのブドウ畑をちょっと思い出す風景。ものすごい生産量だろうな。
|
|
|
|
|
|
|
|
撮影日記5
朝は、空気が凛として冷たく乾いていて、気温は20度に満たず、すこぶる快適だったが、日が高くなって気温が上がってもなかなか爽快。これがスリランカ高原地帯の魅力なのか。車窓には岩山がそびえ立ち、滝がとどろき落ちて、冒険気分が盛り上がる。やがて列車は、紅茶の産地として名高いヌワラ・エリヤ付近へ。植民地時代にはリトル・イングランドと呼ばれていたというヌワラ・エリヤでは、湖水地方を思い出すような風景の中で、イギリス人たちは、ゴルフやテニス、シカ狩りなどをおこなって余暇を過ごしていたそうだ。 昔読んだ本によると、イギリス人も元々はコーヒー好きだったそうで、ロンドンにもカフェ隆盛時代というのがあったという。だが帝国主義の覇権を争う中で、ライバルたちを利するコーヒーから紅茶への転換が行われたのだとか。そこまでするのかな。 さて、そのスリランカ山岳地帯だが、今も観光客にとても人気があるようだ。考えてみればスリランカは、海で楽しんで、遺跡を見学し、山を歩いたり、滝で泳いだりして、最後は紅茶や宝石をお土産に買うという、かなり欲張りで充実した休暇を過ごすことのできるお得な場所なのかもしれない。 そういうわけで、実はこの、ノロノロと走るオンボロ列車も、観光名所のひとつになっていて、ヌワラ・エリヤに近いナヌ・オヤ駅から、高原リゾート的なバンダラウェラや、スイスを連想させる山が美しいエッラなどの間を乗車する観光客は多い。この区間だけ、突然に列車はほぼ満席となり、英語、フランス語、オランダ語などが飛び交うようになる。 やがて、観光客たちが降りてしまうと、何だか車内はほっとした雰囲気につつまれる。そして、ゆっくりと終点のバドゥッラに向かって高度を下げていく。終点のバドゥッラは、植民地時代にはお茶をはじめとする、産物の集積場として栄えた町だという。この位置からであれば、南のゴールや、東海岸へ出るにも便利なので都合がよかったのかもしれない。今では、これといった特色のない地方都市という印象だが、やっぱりそれなりの活気には溢れていて、市場の前を盛んにトゥクトゥクと呼ばれるオート三輪のようなタクシーが行き交っている。ちなみにトゥクトゥクにメーターはないそうだが、1km乗るのに50ルピー(約37円)くらいというのが料金の目安だと教えてもらった。さすがに鉄道よりだいぶ高い。
|
|
|
|
|
|
|
|
撮影日記6
次に向かうのは、北部の都市、アヌラーダプラ。海、山とこの国の魅力を見てきて、次はいよい偉大な仏教遺跡を見学しようというわけ。ちなみに、コロンボから北へ向かう線路には、海岸沿いに真北へと向かいプッタラムという町へ通じているものもあるのだが、今回は見合わせた。 アヌラーダプラは、紀元前4世紀から1400年近くにわたってスリランカの都が置かれていた場所。その数字を見て、スリランカの歴史に改めて目を見張る思いがする。ここの遺跡は、仏塔の巨大なものが主体で、それぞれを取り上げてみると、大きいばかりでちょっと地味。もっとも、今残っているのは、南インドからの侵略者たちに破壊され、後に再建されたものだそうで、往時には今よりもずっと大きな仏塔があったのだという。そこまで大きければ、或いはインパクトも違ったかもしれない。でも、これはアヌラーダプラの遺跡がしょぼいという意味ではない。この遺跡は広大で、かつてとても大きな町があったことがわかる。大きな宮殿や僧院が建ち並ぶ様子はものすごく壮観だったことだろう。数万人に達したと推定される人口を支えるために、土木技術を駆使して作られた貯水池や灌漑設備は現在も残っているものがたくさんあるという。公園や、病院、教育施設なども充実した、すばらしい都市が2000年もの昔に存在したことは本当に驚きだ。そして、アヌラーダプラは今でも大切な巡礼地のひとつとして、スリランカの人々の中に生き続けている。 この日の列車に乗っていたのは、もちろん、アヌラーダプラにお参りに行く人が多かったのだが、他に結婚式の帰りだという人も多かった。何でも、この前日はとても縁起のよい日だったのだという。日本でいう大安吉日のようなものだろうか。他には、親戚の家でのパーティーからの帰りという乗客。週末ともなると、スリランカでは親戚を招いてのパーティーがよく開かれるようだ。
|
|
|
|
|
|
|
|
撮影日記7
スリランカの東海岸は、西や南に劣らぬ美しいビーチが続く。だが、観光客には長い間遠い存在だった。理由はスリランカの、1980年代から続いた内戦だ。北部と東部は、反政府軍の勢力が強かった地域。しかし、今、車窓に広がる田園風景を見ていると、そんなことが嘘のように、平和で穏やかに感じられる。時にはゾウが姿を見せることもあるという、ちょっとアフリカのサバンナと似た低木の生い茂るエリアなどもあり、真剣に窓の外を見つめてしまったが、カワセミの仲間が何回か見えただけだった。 1400年近くにわたって栄えた、スリランカ最初の都アヌラーダプラが、南インドからの侵略によって陥落した後、首都となったのがポロンナルワで、ここもまたスリランカを代表する仏教遺跡のひとつになっている。アヌラーダプラがスケールの大きさで迫るのに対して、ポロンナルワには仏像や彫刻、寺院の跡などが残っているのが特徴だ。もちろん、仏像の多くは壊されてしまっているが、それでも往事の姿を想像できる程度には残っている。なかには、ブッダの歯が納められていた建物の跡というのもある。ブッダの歯というと、キャンディの仏歯寺を思い浮かべてしまうが、スリランカの王権の象徴として仏歯は代々受け継がれてきたもの。王は、都に必ず歯を納めた寺院を建設しなければならなかったのだ。 大いに栄えたというポロンナルワだが、やがて13世紀に入ると衰えて、再び南インドの勢力に破壊されてしまう。そこで当時の王が遷都した先が、ヤーパフワという、巨大な岩の上だった。高さ100メートル近いと言われる岩の上に城塞を築いて、攻め寄せる敵から守りぬこうという作戦。 東海岸の都市、トリンコマリーとバッティカロアは、どちらも天然の良港で、町は、水に囲まれるように存在している。駅にも、町にも、街道沿いにも、自動小銃を持った兵士の姿が目立つようになった。でも、あまり緊張感は感じられない。平和が、当たり前の日常になりつつあるからだろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|