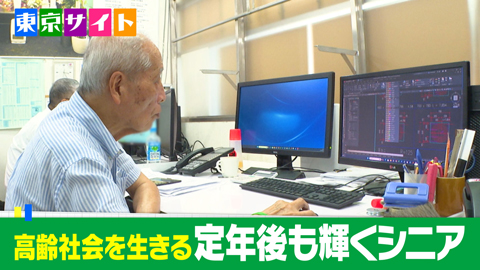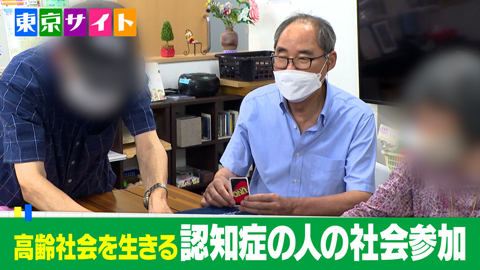バックナンバーBACKNUMBER
高齢社会を生きる
-
2024年9月16日(月)
『楽しく元気に!シニア劇団』
-
9月16日の「敬老の日」にちなみ、今週は高齢社会について考えます。
シニア劇団「かんじゅく座」は、所属するメンバーは全員60歳以上。2006年に俳優の鯨エマさんが立ち上げました。当時は、団塊世代の人たちがどうやってセカンドライフを過ごすかが話題になっていたそうです。
毎年春には劇場公演、秋には高齢者施設などや、時には島しょ部でも公演をしています。稽古は2チームに分かれ、毎週水曜日と金曜日に行っています。稽古場で「パントマイム」のレッスンを行う様子を取材しました。パントマイムのアーティストを特別講師に招き、課題を演じて指導を受けます。74歳の女性は「ダメ出しされても楽しい」と生き生きした表情。82歳の女性は「この年になってから親友と呼べるほどの仲間がいるのはすごく良いことだと思う」と楽しそうに語りました。かんじゅく座
HP:https://kanjukuza.com/
-
2024年9月17日(火)
『定年後も輝くシニア』
-
定年後も正社員として働ける会社を紹介します。
足立区にある「横引シャッター」は、1986年に創業し、横に引くシャッターの設計・製造・施工までを行っている会社です。社員29人のうち9人が65歳以上で、高齢者が約3分の1を占めています(2024年8月時点)。定年は70歳と決まってはいますが、定年後も正社員のままで働くことができる運用を行っています。
70歳を超えて入社した社員もいます。設計担当の男性社員は、5年前、77歳の時に正社員として入社しました。一級建築士の資格を生かして、シャッターの設計を行っています。市川社長は、「積極的に高齢者を採用しているわけではなく、欲しいと思った人がたまたま高齢者の枠にはまっていただけ」だと話しています。
また、この会社では、段差をスロープにしたり階段に手すりを付けるなど、高齢者が働きやすい環境づくりも行っています。定年70歳を超えた社員は、それぞれの体調やライフスタイルに合わせて勤務日数や勤務時間を選択することができます。横引シャッター
HP:https://www.yokobiki-shutter.co.jp/
-
2024年9月18日(水)
『認知症を考える』
-
東京都では、認知症の症状がある高齢者の数は49万人を超え、2040年には約57万人まで増加すると推計されています。今回は、認知症について考えます。
「東京都健康長寿医療センター」を訪ね、認知症について粟田医師に教えてもらいました。認知症とは、何らかの脳の病気によって認知機能が低下し、日々の生活に支障が出る状態のことです。認知症の種類で、最も多いのが「アルツハイマー型認知症」です。アルツハイマー型認知症の人の脳は、記憶に関係する「海馬」を含めて全体的に萎縮してきます。
早い段階から認知症の症状に自分で気付くことも大切です。粟田医師も監修した「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」は東京都のホームページで公開されています。初期に見られる症状などのチェックができ、医療機関への受診や検査のきっかけとして活用することができます。
東京都は、認知症検診などを行う区市町村に補助を行っています。2023年度は21の自治体が検診を実施しました。自分でできる認知症の気づきチェックリスト|東京都福祉局
HP:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/checklist/index.html
-
2024年9月19日(木)
『認知症の人の社会参加』
-
認知症の人が社会参加できる取り組みを紹介します。
1972年に入居が始まった板橋区の「高島平団地」。現在、この団地がある高島平2・3丁目では65歳以上の人口が4割を超え高齢化が進んでいます(2024年8月時点の資料から算出)。
認知症の人を含む地域の高齢者を支える拠点として2017年に開設されたのが、団地の一角にある「高島平ココからステーション」です。認知症であってもなくても誰でも自由に無料で利用することができ、地域の人たちと会話を楽しんだり、ゲームをしたり、アート教室(要予約)に参加したり、認知症の人の孤立を解消する社会参加の場にもなっています。
開室日には、保健・医療・福祉・心理などの専門職員が交代で常駐し、認知症専門の精神科医師や内科医師などがいる日(月4〜7回)には、個別に相談できる体制(予約優先)も整えています。高島平ココからステーション
HP:https://www.facebook.com/t.cocokara.st/
-
2024年9月20日(金)
『認知症の人を支える』
-
認知症の人を支えるプログラムを紹介します。
青梅市にある高齢者の介護施設「福わ家(ふくわうち)」では、「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」というサービスを行っています。このサービスは、認知症の人が少人数で共同生活をし、日常生活を可能な限り自立して送れるように介護スタッフがサポートするものです。
この施設では、認知症ケアの質の向上に役立つ「日本版BPSDケアプログラム」を1年ほど前から導入しています。オンラインシステムを活用し、認知症の人に見られる「妄想」や「幻覚」などの症状(BPSD)を“見える化”して介護スタッフが話し合い、利用者1人1人のニーズに合ったケアを目指します。症状の背景要因を議論して、適切なケアを目指すことで、認知症の人の表情が目に見えて変わってきているといいます。チームで同じ目標に向かってケアを行えることはスタッフの喜びにもつながっているそうです。地域ケアサポート館「福わ家」
HP:https://www.kokohiro.jp/fukuwauchi