今週は結婚式に流したいクラシック音楽の新しいスタンダードを選んでみました。これまで結婚式のクラシックといえば、メンデルスゾーンの劇音楽「夏の夜の夢」の一曲である「結婚行進曲」、そしてワーグナーのオペラ「ローエングリン」に登場する「結婚式」が二大定番。ファンファーレで始まるメンデルスゾーンの「結婚行進曲」はいかにも華やか。一方、ワーグナーの「結婚行進曲」には厳粛な雰囲気があります。どちらも最高の名曲ですが、クラシックを使うならほかの選択もありうるのでは。ということで、選ばれたのが今回の5曲でした。
チェロの佐藤晴真さんが新郎新婦入場の曲として選んだのは、バッハの無伴奏チェロ組曲第1番の前奏曲。これは納得ですね。組曲の冒頭に置かれる始まりの音楽ですから、入場にふさわしい曲だと思います。
ピアノの田所光之マルセルさんがウェディングケーキ入刀の場面に選んだのは、シューマンの「献呈」。シューマンが妻となるクララに捧げた曲集の一曲です。シューマン夫妻の結婚は、クララの父の猛反対があったため、裁判沙汰の末に実現しました。なぜ反対されたかといえば、クララが天才ピアニストとして名声を築いていたのに対し、シューマンはこの時点でほとんど無名の音楽家だったから。格差婚だったんですね。
Cocomiさんが新郎新婦の再入場の音楽に選んだのは、チャイコフスキーの弦楽四重奏曲第1番の第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」。すがすがしく爽やかな演奏でした。
両親への手紙の場面の音楽には、佐藤晴真さんがウォルトンの「弦楽のための2つの小品」の第2曲「やさしき唇にふれて、別れなん」を選んでくれました。深く、しみじみとした味わいがありました。
最後に演奏されたのは、新郎新婦退場の場面として、フォーレの「レクイエム」より「サンクトゥス」。「レクイエム」とは意外な選択でしたが、なるほど、この神聖な曲調はぴったりかもしれません。
飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)

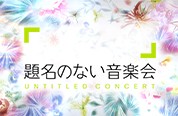 公式サイト
公式サイト