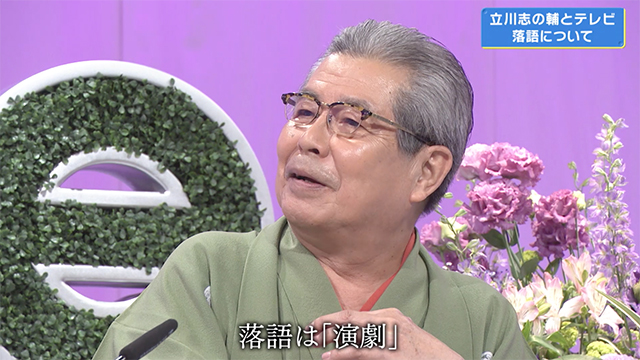バックナンバー
立川志の輔さんとテレビ 前編
八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)
【ナレーション】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)
【ゲスト】立川 志の輔(落語家)
【VTR出演】三宅裕司(喜劇役者)
春風亭昇太(落語家)
落語家・立川志の輔さんにお話を伺いました。

<プロフィール>
1954年 富山県生まれ
1976年 明治大学卒業
1983年 立川談志門下入門
1990年 立川流真打ち昇進
<落語との出会い>
今、思いますと、お亡くなりになりました
人間国宝の柳家小さん師匠あたりが
テレビでやっていらっしゃったんでしょう。
その小さい白黒のテレビを
うちのおじいちゃんが観ながら笑っているんです。
じいさんをじいさんが観ているんですけど、
その後ろで孫が観て。
じいちゃんはテレビの中のじいちゃんを観て笑っているという…
このテレビの中のおじいちゃんも相当面白いこと言っているんだろうな。
というのがたぶん、落語というスタイルを観た最初じゃないかなと思っています。

<明治大学落語研究会>
最初から落研に入るつもりだったんですか?
いや、そうじゃなくて、
キャンパスをぼんやり歩いていると
上級生から「これちょっと今から行くところ、本当面白いよ」
と言われてついていったら、
105号室に100人から150人ぐらいの新入生がいた。
入ってしばらくすると、その人たちが、同じ瞬間に全員がド~ンと笑う。
教壇のところに座布団を敷いて、
それこそ、2年先輩の三宅裕司さんだったかが喋っている落語に、
これだけの若い人たちが同時に反応するというのは
「あ、これか、落語は。じいちゃんが笑っていた。
テレビの中で観ていたじいちゃんがやっていた、これが落語か」
そんな感じですね 落語との出会いは。

<先輩・三宅裕司>
「この場にいる人間の全員が笑わなきゃダメなんだ」
という三宅さんの中の法則があるんですよ。
「10人なら10人いる時に、
たとえその中の1人のあまり褒められた話をするわけじゃない、
どっちかというと悪口に近い話をしたとしても、
その本人も笑って初めてジョークなんだ、冗談なんだ。
その言われた本人が嫌な顔するんじゃ冗談じゃないんだ。
その言われた本人すらも笑うっていうのがいいんだ」
っていう、もう学生時代から
そういうことを考えていたというのはすごいですよね。
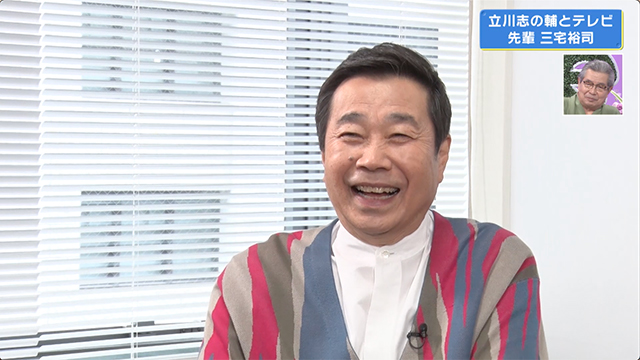
<三宅裕司さんから見た後輩・立川志の輔>
落語は全然下手ではなかったですよね、もちろん。
印象的だったのは
声が大きくて、とにかく明るい分、すごく得しているな、と。
お客さんをぐっと惹きつけるから。
志の輔の落語は、わりと自分の喋り方で喋っていたような気がしますね。
いい具合に声がちょっとかすれていて、
何か「のどの薬」のCMが将来来るな!という感じ。
― 志の輔さんの実力を認めていた三宅さん。
落語研究会で伝統ある高座名、
紫紺亭志い朝(しこんていしいちょう)を志の輔さんに譲りました。
大学卒業後も交流はつづき、
三宅さんが70歳を迎えた年には
後輩の渡辺正行さんと3人で「志い朝の会」を開催。
三宅裕司
会場が新橋演舞場ですよ!? すごすぎますよ。
志の輔に聞いたら、
新橋演舞場は、談志師匠と2人で親子会というのをやって以来だと。
談志師匠との親子会の次が「志い朝の会」ですよ。
緊張しまくって、高座に上がってから気が付いたんですよ。
「あっ、これ舞台と違う、落語だ」って。
そこからね、めちゃくちゃ緊張して、
ポーンと台詞が飛んだり…グッチャグチャになったんですね。
でもね、満席になったのは本当に志の輔のおかげなんですよ。
志の輔が出てくれて、しかも志の輔はヒザ(トリ前の出番)ですよ。
僕はトリで、その前に
「ちょっと志の輔、お客さんあっためといてくれ」と言ったら、
あっためすぎですよ!すごい噺をしやがって。
もうお客さん、みんな感動しちゃって。いい経験させてもらいました。
― 三宅さんのお話、いかがですか?
三宅さん、1つ大事なことを忘れているようで。
新橋演舞場を選んだのは、自分だということを忘れてますよね。
何を言ってるんだとw
まぁでも、本当に満員のお客さんで。
三宅さんが、古今亭志ん朝師匠が大好きで、志ん朝師匠の「うなぎの幇間」を
コピー状態ですよ。
志ん朝師匠が乗り移ったように。
学生時代から落語が上手でしたけど。
う~ん、
私は三宅さんの落語が上手だったと褒めているのに、
なんで「下手ではなかったですよね」って、あの、なんて言うんですかね。
あの言葉の選び方ねw
<劇団員・会社員を経て落語の道へ>
この6年が本当に回り道で無駄だったなと、
落語家になった最初はそう思いました。
師匠の談志も履歴書を見て、
「卒業して養成所に入って役者を目指しました…ダメでしたか。
広告・サラリーマンやりました…ダメでしたか。
どこへ行ってもダメなので、落語家にでもなりましょうかっていう
そういう了見だろう?どっかそこら辺りをうろうろしてろ」
っていうのが最初の言葉だったんですよ。
それくらいに回り道に見えたんですけど、
落語家になったのが28歳で、普通よりも6年ぐらい遅れた。
その遅れた分が何か、
今の落語を作ってくれているような気はしています。
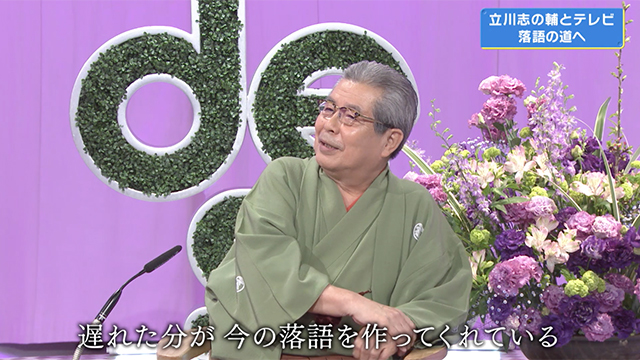
<師匠・立川談志>
それを一番後ろの当日券で観ていた時。
最後に師匠が「芝浜」をやっていた時にどんどん涙が流れてきて、
この人の落語は違うな、落語とかなんとかじゃなくて、
立川談志っていう人が喋っている。
ずっと高座に立川談志っていう人がいるっていう…
不思議な人だなと思って、
この人のところへ行ったら、ひょっとすると
遅れて入る自分を何とかしてくれるかもしれないと
思って入門したんですけど、
約半年後に談志が突然「俺は出る」と。
最初に聞いた時は、どこの落語会に出るのか?と思ったんですけど、
「落語協会を出る」と。
そういう意味では、養成所に入って、広告の世界に入って、
落語界に入ってまで、まだその先も曲がるのか…って。
でもそれがなにか、すべて面白かったですね。
談志曰く、
「お前は実験第1号だ。寄席がなくても落語家になれるのか、
落語ってできるのかっていうのは、とりあえずお前は試しだ。
何とかしろ」
― VTR 1990年、当時36歳で出演した「徹子の部屋」
談志師匠が落語協会を脱退することについて語っていました。
よく喋ると男ですねw
30数年前と喋ってる内容は同じですよね?
ですから、あのVTRを先に観とけば、僕、喋る必要なかったですよねw
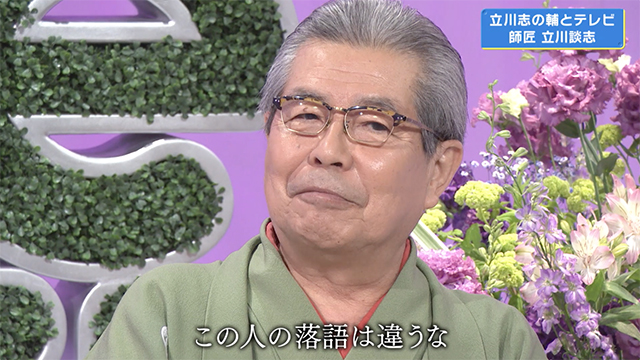
<「新作落語」誕生秘話>
昔、使い切りカメラってありましたよね。
女性のスタッフが何かを一生懸命いろんなものを撮っているんですよ。
あまりにも撮っているものに脈絡がないので、
「それ何を撮っているの?」って聞いたら
「いえいえ、フィルムが余っているものですから」って言うんですよ。
「余ったら余っているまんま、撮りたくて撮ったものを
すぐに持って行って現像した方がいいんじゃないの?」
って言ったら「いや、もったいないですから」と。
女性的な考えでいうと、何かが使い切ってないともったいないと思う、
そういうことが男はわりと何か大雑把で、
「いいんだよ、2枚しか撮ってなくたって、
その2枚撮りたいために買ったんだから。
いいよ、早く写真屋さんに持っていけよ」っていう、
ああ、こういうことなんだと思った時から作り上げていったら
作品が1つ出来上がった。
女房がスーパーに買い物に行って2,450円の買い物して
さあ、それでお金を払おうと思ったら
「今、3,000円お買い上げの方にハンドタオル プレゼント」
って書いてあると、「あぁ!」と思って「ちょっと待ってて」と言って、
その周りにあるもので、なんとか3,000円にしようと思う。
そしてハンドタオルを貰って家へ帰ってくる。
その大したことのないハンドタオルを亭主が見て、
「お前、何考えてるんだ?」と。
「なんで余計なものを買ってくるんだ?」
「だって3,000円にしないと」
「いや、しなくたっていいじゃない?」
「いや、しないとハンドタオルがもらえないもの」っていう、
なんともいえない亭主と女房の考え方の違いが
ものすごい何か今の笑いというか、「生活の笑い」を生んだので、
新作を作ってみて自分で面白いと思った。
たまたま女性スタッフが使い切りカメラをそういうふうにしててくれたことが
ものすごいヒントになったんです。
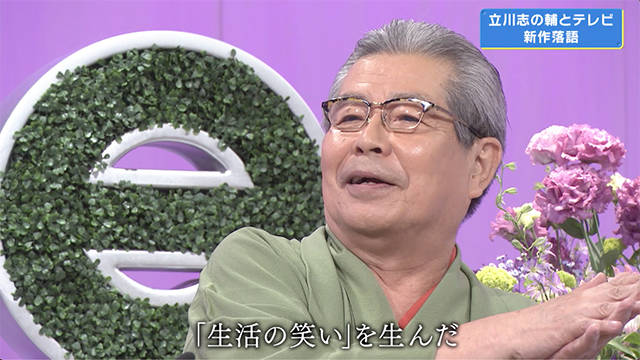
<春風亭昇太が分析する志の輔の落語>
落語家って色々なタイプがあるんですけど、
志の輔さんは演出家タイプの落語家さんなんですよ。
俯瞰で落語を観ることができる落語家さん。
僕たちって落語家だから落語のストーリーは全部分かっている。
だから省略しようとするんですよ。わかってるから。
志の輔さんっていうのは、外から落語を観られる人なんで、
観客目線の落語ができるんですね。
丁寧なんです。
マクラとかも聞いていると、
これから話す噺の概要は、ストーリーじゃないんだけど、
「これからこういう話をしますよ」というのは、
もうマクラで1回喋っているんですよ。
このあと喋る落語について、この噺はこういう風に観てください。
こういう感じで聴いてくださいっていうのを
マクラで何となく伝えているんですよ。
だから、お客さんはすごい分かりやすく、
その話にすっと入っていける。
― VTRを観て
全て見抜かれておりますw

<落語とは>
落語は「お笑い」じゃないと思っています。
1人の人間のお話を15分や20分聴いていく時には、
時々笑わないと聴いていられないんでしょう。
笑うことで次の笑うところまでの間に
お客さんは緩和して、そしてまた緊張して緩和して
緊張して緩和してやっていくものですから、
「演劇」なんですよね。
お笑いのために話ができているというよりは、
奥さんは、真剣にハンドタオルが欲しいから、
あとの残りのものを買い物をするっていうのは
ふざけてやっているわけじゃなくて、とても日常的に、
ハンドタオルがタダでもらえるんだったら、
あと550円何か買おうと思う。
そのおかしさっていうのを客観的に観て、
それをお芝居仕立てで1人で右左でやっているというだけで。
そういう考えで落語をやっていることは確かですし、
そうやっていくと、ちょっと今までの、いわゆる古典落語を、
師匠や兄弟子や仲間に教わってやっていく伝統のやり方、作り方と
また全然たぶん違うことをやっていたんだと思いますね。