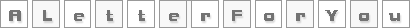
| |
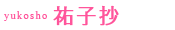
|
 |
Vol.61 「雪だるま」 (2004/02/23) |
 |
20年前、福岡に住んでいた頃。
生まれて初めて積もった雪を見た。
早く外に出たいのに、ミトンをはめているせいでドアノブがうまくつかめない。
「滑るから気をつけてね」
辺り一帯が、白い画用紙を敷き詰めたように平坦だった。
色も音も時間さえも閉じ込められている。
何の躊躇もなく小さな足跡を付けていく妹の後を、慌てて追いかけた。
雪をせっせと運び、おもちゃのスコップでぺたぺたと形を整え、その雪肌を南天の赤い実で飾る。
夕闇に浮かび上がる、雪だるまの大きなシルエット。母が呼びに来るまで、黙々とその作業は続いた。
急に心配になったのは、熱い湯船に浸かっている時だった。
雪だるまが溶けてしまう。
しきりに「もう一度見に行こう」と誘う妹に、なぜか返事をすることが出来なかった。
あんな大きな雪だるまを作らなければ良かった。
雪だるまの赤ちゃんだったら、家の冷凍庫に入るのに。
そうすれば、溶けることもない。
雪だるまは日につれて少しずつ溶けていった。
「ごめんね」でもなく「さようなら」でもない。
崩れ落ちていく小石の目鼻がまるで泣いているようで、
幼稚園の行き帰り、なるべくその場所を見ないように走って通り過ぎた。
それでも幾月か経てば、雪だるまを溶かしたはずの日差しに私はうっとりとまどろみ、
菜の花のお浸しが食卓に並ぶと、うららかな春の訪れを家族で喜んだ。
四季は巡る。
次の季節を迎える時は、忘れるのではなく、また会えると思えばいい。 |
|
|
|
| |
|