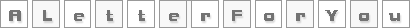
| |
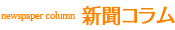
|
 |
Vol.12 「行き交う箱」 (2005/01/15) |
 |
「村上さん、お正月は帰省した?」
「今年は帰らなかったんです…」
1月4日、仕事始めの午前3時。
ドライヤーの熱風音が響くメイク室で、寝ぼけ眼でスタイリストさんと言葉を交わす。
「私、年末年始はゆっくりお休みして来ちゃった」
すっかり晴れやかな彼女は、青森に帰っていたそうだ。
確かに、実家のこたつで蜜柑を片手にごろごろしないと、お正月を迎えた感じがしない。
新年早々、実家からは荷物が届いた。
ダンボールを開けると、密閉容器に入ったお雑煮やお煮しめ、
数の子、祝い箸などがぎっしりと詰まっていた。
「祐子へ」と記された封筒を開封すると、梱包品の詳細が記されている。
「お雑煮は、すぐにお鍋に移し変えて、火を通して下さい」
そして、最後の数行には。
「今年のお正月は、一人いないので、少し静かでした」
荷物の中には、毎回必ず手紙が入っている。
高校生の時以来、親元を離れて暮らしている。
これまでに行き交ったダンボールの数は、計り知れない。
季節ごとの衣服や、頂きもののバスタオル。
今でも実家には、予め私の住所が記入された送り状が束になって常備されている。
そう言えば、私がまだ幼かった頃も、祖母から母へと荷物が送られてきていた。
開封する時の懐かしいような照れくさいような喜びは、一人暮らしをするまで分からなかった。
スタイリストさんのご実家からも、荷物が定期的に届くらしい。
「いつも、りんごと、手作りの蓬餅を送ってくれるよ」
「うちは、手作りの苺ジャムかなぁ」
出勤前の、慌しい起き抜け。
熱い紅茶にたっぷりと入れて、母の味に起こしてもらっている。
年末年始は特に、宅配便のトラックを頻繁に見掛けた。
配達しているお兄さんたちの深緑のジャンパーを、気付けば私は目で追いかけている。
荷物が届けられる場所、そして、その中に詰められたもの。
食べるもの、着るもの、必要なもの、大切なもの。
最近は「クール便」もすっかり浸透して、生ものも当たり前に遅れるようになった。
送れるものが増えるほど、それだけ、たくさんの気持ちも。
送ってくれる、誰かがいるからこそ。
思いが詰まったダンボールは、今日もどこかの玄関に届く。
(「日刊ゲンダイ」1月15日発刊) |
|
|
|
| |
|