 |





|
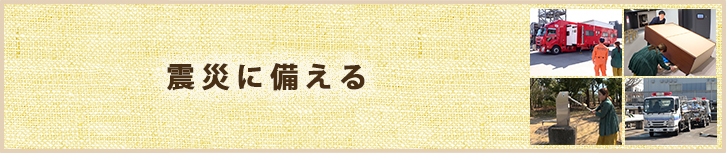
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2024年4月1日(月)
「即応対処部隊」

 今週は、能登半島地震の被災地で東京都が行った支援活動や、震災への備えについて紹介します。
今週は、能登半島地震の被災地で東京都が行った支援活動や、震災への備えについて紹介します。東京消防庁では、進入困難な被災地に通常の消防隊より先に入って現地の情報収集を行い、後続の救助部隊の指揮を執る「即応対処部隊」を編成しています。能登半島地震では、東京消防庁からのべ1200人以上の隊員が派遣されましたが、その中で即応対処部隊は、道路が寸断され孤立した沿岸地域の情報収集を行いました。
即応対処部隊は、上空から被災状況を調べられるドローンや、水深1.2mの浸水地でも走行可能な特殊車両などを備えており、大地震や風水害などを想定した訓練を日々行っています。
東京消防庁「即応対処部隊」
HP:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/tfd/hp-kyuujyoka/soku/
2024年4月2日(火)
「応急給水活動の支援」

 東京都は大地震などによる断水に備え、30台の給水車を都内各地に配備しています。能登半島地震の被災地では、この給水車による応急給水活動のほか、給水車がいない時間帯でも利用できる組み立て式の水槽を設置したり、路上に水道管を仮設したりするなどの復旧支援が今も続いています。これまで東京都からは、約1300人の水道関係者が被災地に向かいました。
東京都は大地震などによる断水に備え、30台の給水車を都内各地に配備しています。能登半島地震の被災地では、この給水車による応急給水活動のほか、給水車がいない時間帯でも利用できる組み立て式の水槽を設置したり、路上に水道管を仮設したりするなどの復旧支援が今も続いています。これまで東京都からは、約1300人の水道関係者が被災地に向かいました。また東京都は、災害に備えて「水道緊急隊」という部隊を編成しています。24時間365日の勤務体制を敷いていて、首都直下地震が起きた時に水を3日以内に供給するという特別な任務を負っています。能登半島地震でも、発生直後に現地に向かった部隊のひとつです。
東京都水道局は、大地震などを想定した訓練を年間450回以上行い、水の備蓄なども呼び掛けています。
東京都水道局の災害対策
HP:https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/suidojigyo/shinsai/
2024年4月3日(水)
「精神医療の支援チーム」
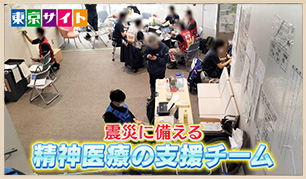
 東京都災害派遣精神医療チーム「東京DPAT(ディーパット)」を紹介します。
東京都災害派遣精神医療チーム「東京DPAT(ディーパット)」を紹介します。東京DPATは、災害時に東京都から派遣され、被災者の精神的なケアや支援を行う医療チームで、都立病院をはじめ、民間医療機関の精神科の医師や看護師など約300人で構成されています。2018年に発足し、能登半島地震が初めての災害派遣となりました。現地では活動拠点を能登町役場に置き、被災者の状態や避難所の情報などを他の派遣医療チームと共有しながら、各地の避難所を回りました。被災のストレスなどにより精神的な不安を抱え、夜眠れなくなったり、生活リズムが崩れてしまった被災者に寄り添い、親身になって話を聞くことによって“心のケア”を行いました。
この支援活動をした看護師の水津(すいづ)さんは、「支援者の負担も大きく、支援する側にもケアや配慮が必要だ」と感じたそうです。また東京都の担当者は「災害時など大きなストレスがかかる時は誰にでも“心の不調”が起きる可能性があるため、そうした不調に配慮することも大事」と話しています。
東京DPAT
HP:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/chusou/dpat/dpat.html
2024年4月4日(木)
「もしもの時の救出体験」
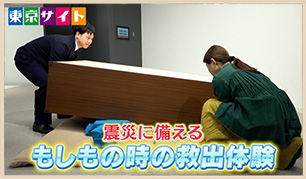
 墨田区にある「本所防災館」で、大地震が起きた時に私たちに何ができるのかを学びます。
墨田区にある「本所防災館」で、大地震が起きた時に私たちに何ができるのかを学びます。本所防災館には大地震の揺れを再現できる設備などがあり、自然災害に関する体験学習ができます。先月、この施設に、新たに「救出救助コーナー」が開設されました。大地震が起きた時の住宅の様子を再現したスペースや、家具に挟まれた人を助け出す体験コーナー、家具の固定方法を学べるコーナーなどがあり、災害時に自分の命を守り、周りの人とお互いに助け合う方法を学ぶことができます。
約80kgの家具に挟まれた「人(人形)」を助け出す体験では、家具を持ち上げてできた隙間に、硬い木の板や厚めの雑誌などを差し込む方法のほか、車のジャッキなどを使って家具を持ち上げる体験ができます。東京消防庁の担当者は、「万が一、大切な人や近所の人に命の危険がある場面に遭遇した時、“自分には何もできない”という後悔がないように、事前の備えや助ける方法などを学んでもらいたい」と話しています。
本所防災館
HP:https://tokyo-bskan.jp/bskan/honjo/
2024年4月5日(金)
「防災公園を知ろう」

 災害時に救助活動の拠点や避難場所として活用される「防災公園」を紹介します。
災害時に救助活動の拠点や避難場所として活用される「防災公園」を紹介します。東京都は、63カ所(2024年3月現在)の都立公園を「防災公園」として位置付け、電気や水道などライフラインが絶たれた中でも利用できる設備を整えています。
防災公園のひとつ、都立木場公園を訪ねました。公園入り口の、避難場所であることを示す看板は、ソーラー発電によって夜間も点灯しています。断水時、木場公園では手動式のポンプで貯水槽の水をくみ上げることができます。この水は、飲むことはできませんが、手洗いやトイレなどに使用できます。また木場公園には、停電状態でも施設の管理者が操作することで、飲み物を取り出すことができる「災害救援自動販売機」が設置されています。このほか、上下水道が使えない時に利用できる災害用トイレや、停電時でも明かりがつく防災用の照明、災害時にかまどとして利用できる「かまどベンチ」なども設置されています。
防災公園を知ろう|東京都公園協会
HP:https://www.tokyo-park.or.jp/special/bousai/index.html







