 |





|
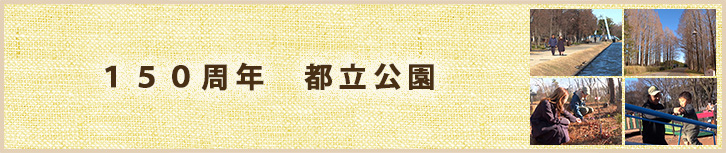
��1�T�ԕ��̓���͂�������
������������YouTube�ł�
2024�N2��12��(��)
�u���������v

 1873�N�A���{�ɓs�s�������x�����肳��A�����ɂ͏���Ȃ�5�J���̌������a���B���ł͑����̓s���������l�X�̌e���̏�ƂȂ��Ă��܂��B
1873�N�A���{�ɓs�s�������x�����肳��A�����ɂ͏���Ȃ�5�J���̌������a���B���ł͑����̓s���������l�X�̌e���̏�ƂȂ��Ă��܂��B�u���������v��1965�N�J���B23����ōő�̖ʐς��ւ�A�s���B��̐����̌i�ς��������ł��B
�����́u�������i���������߁j�v�Ƃ������ߒr�ɉ����đ����Ă��܂��B�������͍]�˖��{8�㏫�R ����g�@�̖��ɂ��A���Q�h�~�A�_�Ɨp���̊m�ۂ�ړI�ɁA���͂̐�������~�߂đ����܂����B
�����ɐ������鐶�����̂ɂ��Ă̗l�X�ȓW�����݂���̂��u���ӂ̐������̊فv�B7������8���ɂ����Č������}���鐅���u�I�j�o�X�v�̎�����̗t���W������Ă��܂��B���a���l�̔w��قǂ�����傫�ȗt�ł��B�I�j�o�X�́A�S�̂��s���Ƃ��ɕ����Ă��āA���ꂪ�S�̊p�̂悤�Ɍ����邱�Ƃ��炻�̖������������ł��B
�����s�ł́A�s�������J��150���N�L�O�̃f�W�^���X�^���v�����[��3��31���܂ŊJ�Ò��B�l���X�^���v���ɉ����ē����o�b�W�����炦�܂��B�܂������s��100�N������������g�݂ǂ�Ɛ�����܂��Â���h�u�����O���[���r�Y�v�Ɏ��g��ł��܂��B
��������
HP�Fhttps://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index041.html
2024�N2��13��(��)
�u���������A�v

 �����h�[����20���̕~�n�ɖL���Ȏ��R���L����A23����ōő�̖ʐς��ւ�u���������v���Љ�܂��B
�����h�[����20���̕~�n�ɖL���Ȏ��R���L����A23����ōő�̖ʐς��ւ�u���������v���Љ�܂��B�����́u���^�Z�R�C�A�̐X�v�ɂ͍���20m�ȏ�A�����2m�قǂ̑����̃��^�Z�R�C�A����1500�{������܂��B���ă��^�Z�R�C�A�͓��{�ʼn�����������A��ł������Ǝv���Ă��܂����B���̌�1945�N�ɁA�����Ő������̂��������ꂽ���Ƃ���g���������h�ƌĂ�Ă��܂��B���������ɂ�1971�N����ɐA�����܂����B
�����ł͂��܂��܂Ȗ쒹�����邱�Ƃ��ł��܂��B��s���́u�S�C�T�M�v�́A�����͖̎}�Ɏ~�܂肶���Ƃ��Ă��邱�Ƃ������A�c���Ɛ����̐F�̈Ⴂ�Ȃǂ��ώ@���邱�Ƃ��ł��܂��B�u�I�I�o���v��u�q�h���K���v�Ȃǐ��ӂɐ������邳�܂��܂Ȑ������Əo����Ƃ��ł���̂����������̖��͂̂ЂƂł��B
��������
HP�Fhttps://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index041.html
2024�N2��14��(��)
�u����a�����v

 �Ȃ��炩�ȋN���������u�˒n�����������A���R�L���ȁu����a�����v���Љ�܂��B
�Ȃ��炩�ȋN���������u�˒n�����������A���R�L���ȁu����a�����v���Љ�܂��B���R�̌i�ς����ɓ`���邱�̏ꏊ�ɁA���ďZ��n�J���̌v�悪���Ă��܂����B�������A�ߗׂ̏Z���������u�n��̎G�ؗт���т���肽���v�Ɠ����s�ɓ������������Ƃɂ��A�s�������ōŏ��́u�u�˒n�����v�Ƃ���1979�N�ɊJ�����܂����B
���������J���̌o�܂�����A����a�����ł͗��R����邽�߂̃{�����e�B�A����������ɍs���Ă��܂��B
�ߔN�A�͂����Ă���̂��u�A�J�}�c�v�̕ۑS�ł��B�g���͂�h�Ƃ����a�C�ŁA��������̃A�J�}�c���͂�Ă��܂������߁A�������������蔰�̂�������Ɨl�X�ȕۑS�������s���܂����B���̌��ʁA�����ɐV���ȃA�J�}�c���a�����Ă��܂��B����1200�{�قǂ̃A�J�}�c�̗c������A���ɂȂ�ɂ�30�N�قǂ�����܂��B
����ȃA�J�}�c���Z�݉Ƃɂ��Ă���̂��u�n���[�~�v�B�t�ɂȂ�Ɖ����ł͓Ɠ��Ȗ������������Ă��邻���ł��B���N�A�\���̂��������Ȃ��Ƃ����n���[�~�ł����A�A�J�}�c������Ă��邨�����ň��肵�Đ��炵�Ă���̂��m�F����Ă��܂��B
����a����
HP�Fhttps://sayamaparks.com/kouen/higashiyamato/
2024�N2��15��(��)
�u����a�����A�v

 �u�˒n�������������R�L���ȁu����a�����v�́A�~�Ȃ�ł͂̊y���ݕ����Љ�܂��B
�u�˒n�������������R�L���ȁu����a�����v�́A�~�Ȃ�ł͂̊y���ݕ����Љ�܂��B�~�͎G�ؗт̗t�������āA�����₵�����тɂȂ�܂����A�����t�̉��ɂ��܂��܂Ȑ������������邱�Ƃ��ł��܂��B�u�G�m�L�v�Ƃ����̍����ɂ́A�u�S�}�_���`���E�v�̗c�������܂��B�G�m�L�̗t��H�ׂĐ������A�t�������邱��ɂȂ�ƁA�̍����ɂ��܂��������t�̉��œ~���z���܂��B�đO�ɂ͐����ɂȂ�A�N�k�M��R�i���Ȃǂ̎��t�����ߔ�щ��l�q�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�����̖쒹������̂����̌����̖��͂̂ЂƂB20��ނ��̓~�����ώ@���邱�Ƃ��ł��A�u�V���n���v�A�u�R�Q���v�A�u�A�J�Q���v�A�u�����r�^�L�v�Ȃǂ̒��Əo��܂��B�����r�^�L�̃I�X�͑N�₩�ȐF�A���X�͒n���ȐF�����ŁA�G�߂ɂ���ĕW�����̂���G���A���ړ����܂��B
����a����
HP�Fhttps://sayamaparks.com/kouen/higashiyamato/
2024�N2��16��(��)
�u�m�����v

 ���}�c���s�s���p��w����k����20���A�s�S�ł���Ȃ��玩�R����������u�m�����v���Љ�܂��B
���}�c���s�s���p��w����k����20���A�s�S�ł���Ȃ��玩�R����������u�m�����v���Љ�܂��B���̗��j�́A1940�N�Ɂg��Βn�h�Ƃ��Čv�悳��A�펞���́g�h��Βn�h�ƂȂ�A���͖�10�N�ԃS���t��Ƃ��Ďg�p����Ă��܂����B�����Ƃ��Đ����ɊJ�������̂�1957�N�ł��B
�������U��Ƒ��炫�̃E�������J�ɂȂ��Ă��܂����B�����͗�N2�����{�܂łł��B�i������̓V��ɂ���ĕς��\��������܂��j
�����ɂ͑�����̎x���u�J�ː�i��Ƃ���j�v������Ă��邽�߁A�݂苴���܂�5�̋����˂����Ă��܂��B
�q�ǂ������ɑ�l�C�̏ꏊ���u�݂�Ȃ̂Ђ�v�ł��B���̍L���X���[�v���ݒu����Ă���̂ŁA�Ԃ����̐l�����p�ł��܂��B�܂��P�K�̃��X�N�����炷���߁A�V��̎��ӂ̓N�b�V�������ɗD�ꂽ�S���`�b�v�ܑ��ɂȂ��Ă��܂��B
�m����
HP�Fhttps://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index004.html
�����s�s�s�������x����150���N�L�O���݃T�C�g
HP�Fhttps://www.tokyo-park.or.jp/Tokyopark150years/
�s�������J��150���N�L�O �����߂���f�W�^���X�^���v�����[
HP�Fhttps://www.tokyo-park.or.jp/Tokyopark150years/info/001.html
�@







