 |





|
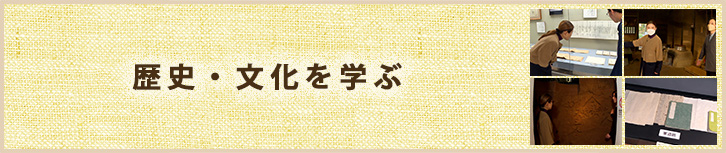
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2024年1月8日(月)
「あきる野市五日市郷土館」

 1995年に秋川市と五日市町が合併して誕生したあきる野市。あきる野市五日市郷土館を訪ね、この地域の歴史や文化を学びました。
1995年に秋川市と五日市町が合併して誕生したあきる野市。あきる野市五日市郷土館を訪ね、この地域の歴史や文化を学びました。五日市地域は山と里の中間にあったため、山からは炭や木材、里からは穀類などの食料や生活物資が「市(いち)」に出されていました。山から切り出した木材を筏(いかだ)に組み、そのまま川に流して輸送していた当時の写真も展示されています。筏の長さは約15mで、筏乗りが巧みに操作しながら多摩川を下っていたそうです。この輸送方法は江戸時代からトラック輸送が始まる大正時代まで続きました。
東京都指定無形文化財の伝統技術「軍道紙(ぐんどうがみ)」は、あきる野市の山間部の集落「軍道」が名前の由来となっています。伝統的な手漉きの和紙で、原料は丈夫な「楮(こうぞ)」などが使われていました。軍道紙はかつて庶民向けの和紙として多く利用され、現在でも地域の小中学校の卒業証書に使用されています。また郷土館の敷地にある古民家「旧市倉家(きゅういちくらけ)住宅」の障子にも、軍道紙が使われています。
あきる野市五日市郷土館
HP:https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000001285.html
2024年1月9日(火)
「羽村市郷土博物館」

 1991年に町から市となった羽村(はむら)市は、多摩川と玉川上水が流れる豊かな自然と史跡が見られる土地です。
1991年に町から市となった羽村(はむら)市は、多摩川と玉川上水が流れる豊かな自然と史跡が見られる土地です。羽村市郷土博物館を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。
玉川兄弟が1653年に完成させた「玉川上水」は長さ約43km。その起点は多摩川にある羽村堰(はむらぜき)の取水口です。玉川上水は水不足に悩む江戸の町や武蔵野台地の村々へ、生活用水を供給するために造られました。郷土博物館の館内には、実物大の「江戸時代の水門」が再現・展示されています。
多摩川と羽村堰の模型展示「玉川上水の取水口模型」を見ると、この羽村が玉川上水の起点に選ばれた理由がわかります。多摩川がこの付近で一度曲がり、流れの勢いが緩んでいるため、川の水をコントロールしやすい場所だったということです。
羽村市郷土博物館
HP:https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000005474.html
2024年1月10日(水)
「杉並区立郷土博物館」

 杉並区にある杉並区立郷土博物館を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。
杉並区にある杉並区立郷土博物館を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。「井草式土器(いぐさしきどき)」は、杉並区上井草の遺跡で1940年に初めて発掘された土器で、約11000年前のものと推定され、当時は日本最古の土器として注目されました。表面に糸を撚(よ)ったようなもので付けた模様、「撚糸文(よりいともん)」が施されています。
この郷土博物館では他にも、江戸時代の宿場だった「高井戸宿(たかいどじゅく)」の模型展示も見ることができます。高井戸宿の住民は、主に農業をしながら宿場も営んでいました。そのため街道沿いに外便所を設置して旅人に利用してもらい、肥料を手に入れていたそうです。
さらに博物館の敷地には、杉並区有形文化財に指定されている「旧篠崎家住宅主屋」も展示されています。
杉並区立郷土博物館
HP:https://www.city.suginami.tokyo.jp/histmus/
2024年1月11日(木)
「めぐろ歴史資料館」

 めぐろ歴史資料館を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。
めぐろ歴史資料館を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。この資料館の床には、目黒区の航空地図が展示されています。目黒区の形は魔女がホウキに乗っている姿に似ていると言われています。ホウキの位置には目黒川が流れています。
江戸時代の目黒区は行楽地として人気があり、多くの浮世絵師が風景を描いていました。歌川広重の作品「目黒新富士」には、目黒の地に造られた「富士塚」が“目黒の富士山”として描かれています。「富士塚」とは、当時の富士信仰によって各地に造られた、富士山を模した山や塚のことです。
さらに館内には、目黒新富士があった場所の地下4mから発見された「胎内洞穴(たいないどうけつ)」の一部が再現されています。胎内洞穴とは、もともと富士山の噴火によってできた穴のことで、この穴の中をくぐり抜けると安産祈願になるとされています。また胎内洞穴の奥には祠があり、横たわった状態で「大日如来像(だいにちにょらいぞう)」が見つかっています。
めぐろ歴史資料館
HP:https://www.city.meguro.tokyo.jp/shougaigakushuu/shisetsu/bunkakouryuu/rekishi_shiryokan.html
2024年1月12日(金)
「パルテノン多摩ミュージアム」

 パルテノン多摩ミュージアムを訪ね、地域の歴史や文化を学びました。
パルテノン多摩ミュージアムを訪ね、地域の歴史や文化を学びました。都内最大の丘陵地帯が広がり、都心のベッドタウンとして発展してきた多摩市。開発前・1962年と開発後・1999年を比較した地形の模型展示を見ると、開発前後で景色が全く違うことが分かります。
都心の住宅難を解消するため、郊外に大規模な住宅地を造る計画が進められ、日本最大規模の「多摩ニュータウン」が誕生しました。1971年に入居が開始されると人口も急増しましたが、商店などが立ち並ぶ一方で、不便な一面もありました。入居開始当時はまだ鉄道も開通しておらず、インフラ整備が十分ではない状態でした。そんな中、住民たちが行政と協力し合い手作りの学童保育を運営したり、図書館なども未整備だったため地域文庫活動も行ったりしながら、住みよい街へと近づけていったそうです。
パルテノン多摩ミュージアム
HP:https://www.parthenon.or.jp/museum







