 |




|
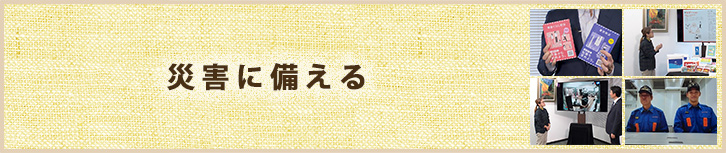
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2023年12月25日(月)
「命を守る防災ブック」
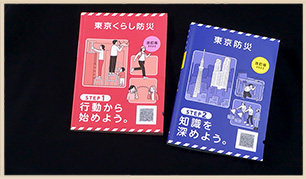
 今週は災害への備えについて紹介します。
今週は災害への備えについて紹介します。推定マグニチュード7.9の地震が発生した1923年の関東大震災では、10万人以上の死者・行方不明者が出ました。南関東域では、今後30年以内に約7割の確率で、マグニチュード7クラスの首都直下地震が発生すると言われています。そこで東京都は、災害から命を守るための情報をまとめた「東京くらし防災」と「東京防災」という2つの冊子を、都内全世帯に配布しています(2024年3月末までに配布終了予定)。
「東京くらし防災」はステップ1として、日常生活の中で手軽に取り組める防災行動が分かる内容で、発災直後や避難生活など、状況に応じた情報をまとめています。また防災知識や備えのレベルを自己診断できるページもあり、ポイントの低かった項目から災害への備えを強化していくという使い方もできます。
「東京防災」はステップ2として、災害への備えを万全にするための情報を紹介していて、学校や地域などでの防災活動に活用することもできます。
2023年12月26日(火)
「今から始める備蓄」

 東京都では「東京くらし防災」と「東京防災」という冊子を都内の全世帯に配布し(2024年3月末までに配布終了予定)、「日常備蓄」を呼び掛けています。日常備蓄とは、日常品を日頃から少し多めに購入しておくことで、備蓄品としてストックする方法です。ストックしたものを古いものから使っていき、無くなる前にまた購入することで、常に備蓄ができるようになります。
東京都では「東京くらし防災」と「東京防災」という冊子を都内の全世帯に配布し(2024年3月末までに配布終了予定)、「日常備蓄」を呼び掛けています。日常備蓄とは、日常品を日頃から少し多めに購入しておくことで、備蓄品としてストックする方法です。ストックしたものを古いものから使っていき、無くなる前にまた購入することで、常に備蓄ができるようになります。水や食料などの備蓄は、最低3日間分が目安となっています。「東京備蓄ナビ」というウェブサイトでは、家族の人数や世代などを入力するだけで、必要な備蓄品の種類や量などが分かります。さらに、すぐに備蓄が始められるように、必要な備蓄品が表示された画面からインターネットショップにアクセスすることもできます。
東京備蓄ナビ
HP:https://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp/
2023年12月27日(水)
「マンション防災」
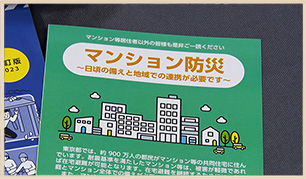
 東京都の人口約1400万人のうち、約900万人がマンションなどの共同住宅に住んでいます。東京都では「マンション防災」についてまとめたリーフレットとあわせて、「東京くらし防災」と「東京防災」の冊子を都内の全世帯に配布し(2024年3月末までに配布終了予定)、災害への備えを呼び掛けています。
東京都の人口約1400万人のうち、約900万人がマンションなどの共同住宅に住んでいます。東京都では「マンション防災」についてまとめたリーフレットとあわせて、「東京くらし防災」と「東京防災」の冊子を都内の全世帯に配布し(2024年3月末までに配布終了予定)、災害への備えを呼び掛けています。大地震が発生した際、マンションなど高層の建物では、大きくゆっくりとした揺れが長時間続く「長周期地震動」が起きます。テレビやタンスなどの家具が激しく移動するため、しっかりと固定する対策が必要です。
比較的耐震性が高いマンションでは、自宅で避難生活を送る「在宅避難」ができる可能性が高いと言われています。マンションでの在宅避難では、必要な情報を各階に伝えたり、物資を運んだり、防犯の見回りを行うなど、住民同士の協力が大きな力になります。
マンションでの在宅避難では注意点もあります。排水管の損傷に気が付かずトイレを使用すると、下の階で汚水があふれる恐れがあるため、排水管の復旧が確認できるまでは携帯トイレや簡易トイレを代用してください。また故障や停電でエレベーターが緊急停止し「閉じ込め」にあう恐れがあるため、エレベーターを使用してはいけません。
2023年12月28日(木)
「地域を守る消防団」

 東京都が配布している「東京くらし防災」「東京防災」(2024年3月末までに配布終了予定)では、消防団の活動についても紹介しています。
東京都が配布している「東京くらし防災」「東京防災」(2024年3月末までに配布終了予定)では、消防団の活動についても紹介しています。消防署員とは違い、普段は別の仕事を持つ市民で構成される消防団は、消防活動だけではなく、地震などの災害が発生した際にも救助や避難誘導など重要な役割を果たします。
福生市消防団は、火災による死者が4000日間ゼロという功績が認められ、去年東京消防庁から「消防総監賞」が贈られました。普段は葬儀の仕事をしている島田豊さんが団長となり、総勢約170人の団員をまとめ、月に3、4回ほど、仕事が終わった後の午後7時半頃から10時頃まで訓練を行っているそうです。
市役所の職員として働いている入団3年目の尾澤謙吾さんは、2人の兄が消防団で活躍していることをきっかけに入団しました。消防団のみんなと目標に向かって切磋琢磨することや、自分が生まれ育った町に貢献できていることがやりがいになっていると話します。
福生市の「火災による死者ゼロ」は現在も続き、4700日以上になっています(2023年12月19日現在)。
防災ブック
HP:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028036/index.html







