 |





|
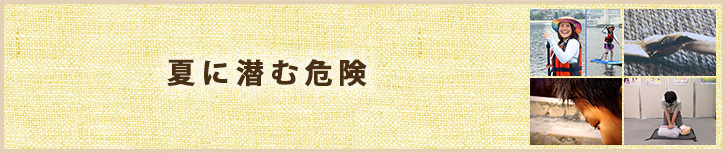
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2023年7月10日(月)
「水難事故を防ぐ」

 夏に潜む危険。「水難事故」の対策について考えます。去年の夏、都内では全国最多の20人が水難事故で亡くなりました。特に夏は川での水難事故が多くなっています。遊泳禁止の場所では泳がないようにしましょう。
夏に潜む危険。「水難事故」の対策について考えます。去年の夏、都内では全国最多の20人が水難事故で亡くなりました。特に夏は川での水難事故が多くなっています。遊泳禁止の場所では泳がないようにしましょう。水辺のレジャーで命を守る第一歩になるのが、ライフジャケットの着用です。体との隙間ができないようにしっかりとフィットさせましょう。しかし、ライフジャケットを着ていれば絶対に安全、というわけではありません。急流で流された場合は下流に向かって足を伸ばし、浮いて救助を待つことが大切です。川は場所によって流れの速さや川底の深さが異なるため、浅い所で遊んでいるつもりでも深みにはまって流されてしまうことが多いそうです。また水際で転び、川に落ちるケースもあるため、履物は踵(かかと)で固定できて脱げにくく、滑りにくいものを選びましょう。
水辺の安全|河川財団・子どもの水辺サポートセンター
HP:https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid324.html
2023年7月11日(火)
「熱中症に要注意」

 夏に潜む危険。「熱中症」の対策について考えます。去年の夏(6〜9月)、東京消防庁管内では6013人が熱中症で救急搬送されています。特に子どもは体温調節機能が未発達なため、体に熱がこもりやすく、大人に比べて熱中症のリスクが高いと言われています。地面からの照り返し、輻射熱(ふくしゃねつ)の影響で、身長が低い幼い子どもほど暑さにさらされているという要因もあります。こまめに休憩や水分補給をとらせることが大切です。
夏に潜む危険。「熱中症」の対策について考えます。去年の夏(6〜9月)、東京消防庁管内では6013人が熱中症で救急搬送されています。特に子どもは体温調節機能が未発達なため、体に熱がこもりやすく、大人に比べて熱中症のリスクが高いと言われています。地面からの照り返し、輻射熱(ふくしゃねつ)の影響で、身長が低い幼い子どもほど暑さにさらされているという要因もあります。こまめに休憩や水分補給をとらせることが大切です。高齢者の場合は、住まいで熱中症になるケースが最も多くなっています。高齢者は温度変化に気付きにくく、汗をかく機能の低下に伴い体に熱がたまりやすいと言われています。また、喉の渇きを感じにくいとも言われます。脱水症状になる前に、こまめな水分補給が大切です。エアコンなどを活用し、28℃を目安に室温を調整しましょう。
熱中症の症状には、めまいや手足のしびれ、筋肉の硬直、吐き気、頭痛、倦怠感、大量の発汗などがあります。症状が出た場合は涼しい場所に移動し、保冷剤などで冷やしたタオルを脇の下や首などの太い血管が通る場所に当てて体温を下げましょう。
熱中症に注意!|東京消防庁
HP:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/season/heat.html#top
2023年7月12日(水)
「思わぬ事故にご用心」

 夏場、東京消防庁では119番通報が増加します。この通報を受けている「災害救急情報センター」に、特別に入らせてもらいました。取材中、通報者が慌てている様子の電話が入りました。電話を受けた担当者は通報者に落ち着くよう促し、救急車を向かわせる住所を慎重に聴き取っていました。
夏場、東京消防庁では119番通報が増加します。この通報を受けている「災害救急情報センター」に、特別に入らせてもらいました。取材中、通報者が慌てている様子の電話が入りました。電話を受けた担当者は通報者に落ち着くよう促し、救急車を向かわせる住所を慎重に聴き取っていました。夏に起こりがちなことに、手持ち花火等による火災や事故があります。手に持ったライターで花火に火をつけると、手に火傷をしたり、服に燃え移ったりする恐れがあります。また遊び終えた花火は、必ず水に浸けてから片付けるようにしましょう。
近年、家電製品などから出火する「電気火災」が多くなっています。電子レンジで肉まんを長時間加熱した実験では、加熱し過ぎたことで肉まんから可燃性のガスが発生し、爆発的に火が出ました。電源コードから出火するケースも多いそうです。折り曲げたり束ねたりすることで電源コードが劣化し、火災につながることがあります。東京消防庁は、コードの小さなこげ跡でも迷わず119番通報するよう呼びかけています。
電気火災を防ごう|東京消防庁
HP:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/camp/2022/202208/camp3.html
2023年7月13日(木)
「蚊の発生を防ぐ」
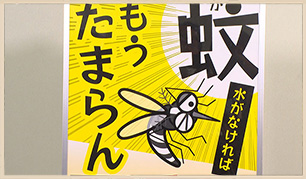
 様々な感染症を媒介する蚊の対策について紹介します。
様々な感染症を媒介する蚊の対策について紹介します。蚊が媒介する「デング熱」や「ジカウイルス感染症」には有効なワクチンがありません。東京都は蚊がウイルスを保有しているか調べるため、都内25施設に蚊の捕獲装置を設置しています。2014年、代々木公園でウイルスを持った蚊に刺された人がデング熱に感染した事例がありましたが、それ以降ウイルスを持った蚊は都内では確認されていません。
また東京都は、家の周りの蚊の発生を防ぐ呼びかけも行っています。蚊は、バケツや植木鉢などの園芸用品、タイヤの内側、空き缶、空き瓶、雨除けのシートなどにたまった水に産卵するため、不要なものは片付けるようにしましょう。卵から成虫になるまで約10日かかると言われているため、1週間に1回以上を目安にたまった水を掃除することが、蚊の発生を減らすことにつながります。
感染症媒介蚊対策について|東京都保健医療局
HP:https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/baikaikataisaku/
2023年7月14日(金)
「もしもの時の救命処置」

 東京消防庁で、もしもの時のための「救命処置」について教わりました。
東京消防庁で、もしもの時のための「救命処置」について教わりました。心臓が止まっている状態では、救命処置を開始する時間が遅れるほど救命率が低下するため、その場に居合わせた人による一刻も早い行動が重要です。心臓が止まっている人に電気ショックを与える「AED(自動体外式除細動器)」の使用による心拍再開率を見ると、救急隊が現場に到着してからAEDを使用する場合に比べ、救急隊到着前に市民が使用した場合、2.5倍以上の割合で病院到着前に心拍が再開しています(東京消防庁調べ)。
街で倒れた人を見つけた場合、まずは周囲の安全を確認し、反応があるか呼びかけます。反応がない場合は大声で助けを呼び、119番通報をしたりAEDを持って来たりする人の役割分担をします。倒れた人が呼吸をしていない場合は、「胸骨圧迫(心臓マッサージ)」を行います。1分間に100〜120回のテンポで、胸が5cm沈むほど強く圧迫します(成人の場合)。AEDが届いたら、電気ショックを与えるためのパッドを右胸と左わき腹に貼り、音声案内に従います。1回の電気ショックで蘇生するとは限らないため、引き続き胸骨圧迫(心臓マッサージ)を継続して下さい。
心肺蘇生の手順|東京消防庁
HP:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu-adv/life01-2.html東京消防庁公式アプリ
HP:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/inf/app/index.html







