 |





|
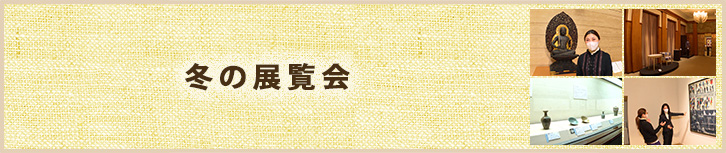
2023�N2��13��(��)
�u�������郂�_�� �@�\�Ƒ����̃|���t�H�j�[�v
 ���N�Ŋ�������90�N���}���鋌�����{�@���A���p�قƂ��Ċ��p���Ă��铌���s�뉀���p�فB������ō��A�u�������郂�_���@�@�\�Ƒ����̃|���t�H�j�[�v���J�Â���Ă��܂��B���̓W����ł́A�������100�N�O�̃��[���b�p�Ɠ��{�̃t�@�b�V������G��ȂǁA���L���W�������̍�i���Љ�Ă��܂��B����ɁA�������{�@���W����i�Ɠ�����̌����ł��邽�߁A��i�ƌ����̗������y���ނ��Ƃ��ł��܂��B
���N�Ŋ�������90�N���}���鋌�����{�@���A���p�قƂ��Ċ��p���Ă��铌���s�뉀���p�فB������ō��A�u�������郂�_���@�@�\�Ƒ����̃|���t�H�j�[�v���J�Â���Ă��܂��B���̓W����ł́A�������100�N�O�̃��[���b�p�Ɠ��{�̃t�@�b�V������G��ȂǁA���L���W�������̍�i���Љ�Ă��܂��B����ɁA�������{�@���W����i�Ɠ�����̌����ł��邽�߁A��i�ƌ����̗������y���ނ��Ƃ��ł��܂��B20���I�O���A�|�p�Ƃ����͍���W���������Ďh���������A���_���Ȃ��̂����グ�Ă����܂����B�t�����X�̃t�@�b�V�����f�U�C�i�[�A�|�[���E�|�����́A�����A�����̊Ԃň�ʓI�������E�G�X�g����ߕt����R���Z�b�g���g��Ȃ��A�v�V�I�ȃf�U�C���̃h���X�\���āA�傫�Ȓ��ڂ��W�߂܂����B
�����ē��{�ł��A���_���ȃf�U�C������������Ă����܂��B�|�p�ƁE�֓����O(������)�́A���[���b�p���w�̌o���œ������z����i�Ɏ�����܂����B�E�B�[���ł̑̌����g�h�Ɍ����ĂāA�S����N���オ���Ă���悤�ȓ������f�U�C���������̂��A�u�\�����߁@�۔[�i�E�B���i�j�̉v�ł��B�����̓��{�l�̕����͘a�������S�ł������A�֓����O�́A�a���̒��Ƀ��_���ȗv�f��������悤�Ƃ����l���ł����B
�u�������郂�_���@�@�\�Ƒ����̃|���t�H�j�[�v�́A3��5���܂ŊJ�Â���Ă��܂��B
�����s�뉀���p�فu�������郂�_���@�@�\�Ƒ����̃|���t�H�j�[�v
����F2023�N3��5���i���j�܂��Z���F�����s�`�攒����5-21-9
�d�b�F050-5541-8600�i�n���[�_�C�����j
�J�َ��ԁF�ߑO10���`�ߌ�6���i���ق͕ق�30���O�܂Łj
�x�ٓ��F���j
���ٗ��F��ʁ@1,400�~�@65�Έȏ�@700�~�i�����w�萧�j
���ŐV�̊J�ُ��͓W����HP�ł��m�F��������
HP�Fhttps://www.teien-art-museum.ne.jp/
2023�N2��14��(��)
�u�����ɖ����@���N�����v

 �ˌI���p�قŊJ�Â���Ă�����ʓW�u�����ɖ����@���N�����v���Љ�܂��B�u�ɖ����āv�́A1610�N��ɓ��{���̍��Y����Ƃ��Ēa�����܂����B���ł������̑f�p�ȍ앗�́u�����ɖ����v�ƌĂ�Ă��܂��B���������`����Ă���A�P�F�g���̃V���v���ȏ����ɖ����̎M�́A���ʂ�������֖����Ă���̂��킩��܂��B�����������E�l�̎�̉����݂���������Ƃ��낪�����ɖ����̖��͂ł��B
�ˌI���p�قŊJ�Â���Ă�����ʓW�u�����ɖ����@���N�����v���Љ�܂��B�u�ɖ����āv�́A1610�N��ɓ��{���̍��Y����Ƃ��Ēa�����܂����B���ł������̑f�p�ȍ앗�́u�����ɖ����v�ƌĂ�Ă��܂��B���������`����Ă���A�P�F�g���̃V���v���ȏ����ɖ����̎M�́A���ʂ�������֖����Ă���̂��킩��܂��B�����������E�l�̎�̉����݂���������Ƃ��낪�����ɖ����̖��͂ł��B���݂̈ɖ����Ă̓J���t���ʼn₩�ȐF�G�����͂ł����A�����ɖ����͘c�݂�L�Y�ȂǁA���n���炵���Z�p�̖��n�����\��Ă���Ƃ���ɓ���������܂��B�Ă��Ă��邤���ɒ�̕������ό`���Ă��܂�����M�̏����ɖ����́A����Ȃ珤�i�ɂȂ�܂��A���̎���ɂ͎�����Ă��܂����B�����Ƃ��Ă͍Ő�[�̋Z�p�ō������ł������A�܂����s���낵�Ă�������ł��邱�Ƃ������܂��B
�ˌI���p�ق̑n�ݎ� �ˌI���i�Ƃ���Ƃ���j���������u���N�����v�̍�i���W������Ă��܂��B���N�����́A���ɖ����Ă̑c���Ƃ������Ă��܂��B�ˌI�����A�ƂĂ��D��ł����̂����I�ȕU�^�̚�ł��B���̊G���`����A���R舒B�ȕM�����̒��ɗ͋������������܂��B
���ʓW�u�����ɖ����@���N�����v�́A3��26���܂ŊJ�Â���Ă��܂��B
�ˌI���p�فu�����ɖ����@���N�����v
����F2023�N3��26���i���j�܂��Z���F�����s�a�J�揼��1-11-3
�d�b�F03-3465-0070
�J�َ��ԁF�ߑO10���`�ߌ�5���i���َ�t�͌ߌ�4��30���܂Łj
�����j�E�y�j�͌ߑO10���`�ߌ�8���i���َ�t�͌ߌ�7��30���܂Łj
�x�ٓ��F���j�E�Ηj�@��3��21���i�E�j�j�͊J��
���ٗ��F��ʁ@1,200�~
���ŐV�̊J�ُ��͓W����HP�ł��m�F��������
HP�Fhttp://www.toguri-museum.or.jp/
2023�N2��15��(��)
�u���{�̕��i��`���v
 �R����p�قł́A���ʓW�u���{�̕��i��`���\�̐�L�d����c���r�v�܂Ł\�v���J�Â���Ă��܂��B�]�ˎ��ォ�猻��܂ł̉�Ƃ��`�������{�̕��i�A��60�_���W������Ă��܂��B
�R����p�قł́A���ʓW�u���{�̕��i��`���\�̐�L�d����c���r�v�܂Ł\�v���J�Â���Ă��܂��B�]�ˎ��ォ�猻��܂ł̉�Ƃ��`�������{�̕��i�A��60�_���W������Ă��܂��B�܂��́A�̐�L�d�̖���u���C���\�E�O���v����Љ�Ă��炢�܂����B���s�̎O��勴�Ⓦ�R�A�������Ȃǂ��`���ꂽ��i�ł��B�]�ˎ���ɂȂ���{�����N�_�Ƃ���܊X������������Ă����ƁA�܂����ʏꏊ�ւ̓��ꂪ�l�X�̊ԂłƂĂ����܂�A�����G�̓K�C�h�u�b�N�I�Ȗ������S���Ă��܂����B
�����ẮA���{�ߑ�m��̋����E���c���P�̍�i�B��������̊C�����̗l�q���`���ꂽ��i�ł����A�l���j���ł���p�͕`����Ă��܂���B�����̊C�����͉j���Ŋy���ނ��̂ł͂Ȃ��A�C�ɓ����ĕa�C�×{����̂��ړI�����������ł��B���c���P������������������ɂ��Ă���Ƃ��낪�A�ƂĂ��V������i�ł��B
����ƂƂ��ɕς���Ă������{�̌Â��ǂ����i�́A�����̉�Ƃ����ɂ���ĕ`���ꑱ���Ă��܂��B1980�N��̏a�J��`������i�ɂ́A�G����l��҂��Ă���悤�Ȑl�X�̒��Ɂu�����C���v���`����Ă��܂��B����̈ڂ�ς��i�Ƃ������_���猩�����i�ł��B
���ʓW�u���{�̕��i��`���\�̐�L�d����c���r�v�܂Ł\�v�́A2��26���܂ŊJ�Â���Ă��܂��B
�R����p�فu���{�̕��i��`���\�̐�L�d����c���r�v�܂Ł\�v
����F2023�N2��26���i���j�܂��Z���F�����s�a�J��L��3-12-36
�d�b�F050-5541-8600�i�n���[�_�C�����j
�J�َ��ԁF�ߑO10���`�ߌ�5���i���ق͌ߌ�4��30���܂Łj
�x�ٓ��F���j
���ٗ��F��ʁ@1,300�~
���ŐV�̊J�ُ��͓W����HP�ł��m�F��������
HP�Fhttps://www.yamatane-museum.jp/
2023�N2��16��(��)
�u�������p�̐��v

 ������~���[�W�A���ł́A�����Ɋւ�����p�i�̓��W�W���u�������p�̐��@�ω������g��(����̂�����)���܂����āv���J�Â���Ă��܂��B�W���i�̈�A��������ɕ`���ꂽ�|�����́A����̐��E�ς��\�����ꂽ��i�ł��B����̐��E�ōٔ������Ă���܊����i�������j�̎p���`����Ă��܂��B�߂�Ƃ��Ƌ��낵���ڂɂ����Ƃ������Ƃ�\�����邱�ƂŁA�l�X�ɍ߂�Ƃ����Ȃ��悤�ɂ����ƌ����Ă��܂��B
������~���[�W�A���ł́A�����Ɋւ�����p�i�̓��W�W���u�������p�̐��@�ω������g��(����̂�����)���܂����āv���J�Â���Ă��܂��B�W���i�̈�A��������ɕ`���ꂽ�|�����́A����̐��E�ς��\�����ꂽ��i�ł��B����̐��E�ōٔ������Ă���܊����i�������j�̎p���`����Ă��܂��B�߂�Ƃ��Ƌ��낵���ڂɂ����Ƃ������Ƃ�\�����邱�ƂŁA�l�X�ɍ߂�Ƃ����Ȃ��悤�ɂ����ƌ����Ă��܂��B�肢�ɉ�����33�̎p�ɂ��̐g��ς��A�l�X���~���Ƃ���Ă���ω���F�B�p��ς��������̂ЂƂł���u�O�\�O�����g���� �����g(���イ���������イ���� �ڂ�̂�����)�v���W������Ă��܂��B���q���㍠����n�܂����\�����@�ŁA�����̑���c��܂��A�߂̒��ɕ����C���܂�ł��邩�̂悤�ȕ\���ő����Ă��܂��B
�����ẮA���q���㏉���̕��t�E�^�c���������Ƃ����u����@������(�����ɂ��ɂ�炢������)�v�BX���ʐ^�ŎB�e����ƁA�����ɂ͕����̍��ł���u�S���ցi�������j�v��u�ܗ֓��i�����̂Ƃ��j�`�̖؎D�v�ȂǁA�����̐��E�ς������A�l�X�Ȃ��̂��[�߂��Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B����ɁA���̕����̎��ɊJ���Ă����E�i���ȁj��������ׂ�ƁA�̓��ɂ͋�����������A�ܗ֓������ɂ͐F���h���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B
���W�W���u�������p�̐��@�ω������g�����܂����āv�́A3��12���܂ŊJ�Â���Ă��܂��B
������~���[�W�A���u�������p�̐��@�ω������g�����܂����āv
����F2023�N3��12���i���j�܂��Z���F�����s���c���Ԓ�25
�d�b�F03-3263-1752
�J�َ��ԁF�ߑO10���`�ߌ�5��30���i���ق͌ߌ�5���܂Łj
�x�ٓ��F���j�E�Ηj
���ꖳ��
���ŐV�̊J�ُ��͓W����HP�ł��m�F��������
HP�Fhttps://www.hanzomonmuseum.jp/
2023�N2��17��(��)
�u�k�ւ�����S�l���v
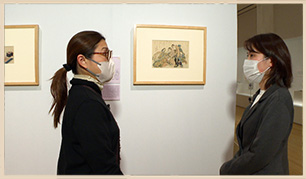 ���݂��k�֔��p�قł́A�u�k�ւ�����S�l���v���J�Â���Ă��܂��B�����G�t�A�����k�ւƂ��̖�l�������`����
���݂��k�֔��p�قł́A�u�k�ւ�����S�l���v���J�Â���Ă��܂��B�����G�t�A�����k�ւƂ��̖�l�������`�����u�S�l���v�ɂ܂����W�ł��B�]�ˎ���A�S�l���͈�ʋ��{�₩�邽�V�тƂ��čL���e���܂�܂����B
�k�ւ��`�����u�S�l�����ꂩ��(������)�Ƃ��v�́A��l���̂̈Ӗ����q�ǂ��ɐ��������|�Ŋ�悳�ꂽ��i�ł��B�k�ւ́A���ƕ��́w�瑁�U(���͂�Ԃ�)�@�_���������(��)�@���c��(��������)�@���炭��Ȃ�(��)�Ɂ@�����T(��)��Ƃ́x�Ƃ����a�̂��ނɕ`���Ă��܂��B���̘a�̂́A�Ñ�̐_�̎���ɂ����������Ƃ��Ȃ��قǁA��ɗ���Ă���g�t���������Ƃ����Ӗ��̉́B�̂ł́A�g�t������闳�c��Ɏ�Ⴊ�u����Ă��܂����A�k�ւ͐l���̕\��⓮���ɏœ_�ĂĊG��`���Ă��܂��B�k�ւ́u�S�l���v�́A�Ǝ��̔��z�荞�݂��������Ƃ�����A���̊G�͂ǂ̉̂��ƍl�������������̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂������߁A100�}�̂͂���27�}�ɂȂ��Ă��܂����ƌ����Ă��܂��B
����ɖk�ւ́A�g�␠(����)�h�ƌĂ��A��̕��𐠁i���j�荞�ދZ�@�Ȃǂ��g���āA�u�S�l���v�̉̐l������т₩�ɕ`���܂����B���W�u�k�ւ�����S�l���v�́A2��26���܂ŊJ�Â���Ă��܂��B
���݂��k�֔��p�فu�k�ւ�����S�l���v
����F2023�N2��26���i���j�܂��Z���F�����s�n�c��T��2-7-2
�d�b�F03-6658-8936
�J�َ��ԁF�ߑO9��30���`�ߌ�5��30���i���ق͌ߌ�5���܂Łj
�x�ٓ��F���j
�ϗ����F��ʁ@1,000�~�@65�Έȏ�@700�~
���ŐV�̊J�ُ��͓W����HP�ł��m�F��������
HP�Fhttps://hokusai-museum.jp/
�@







