 |





|
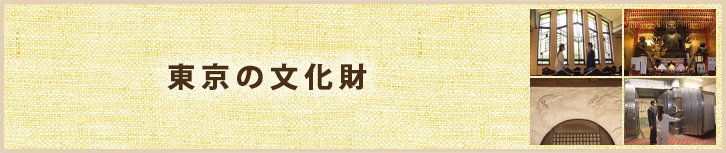
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2022年10月31日(月)
「木造大日如来坐像」

 「東京文化財ウィーク2022」では、通年公開されているものに期間限定の特別公開も加えた、約480の文化財を楽しむことができます。
「東京文化財ウィーク2022」では、通年公開されているものに期間限定の特別公開も加えた、約480の文化財を楽しむことができます。昭島市の拝島駅からバスで約15分の「大日堂(だいにちどう)」は、平安時代の952年創建と伝えられています。言い伝えによると、平安時代に多摩川上流から中州の島に1体の仏像が流れ着き、村人たちがこの島を拝み始めたことから、このあたりは「拝む島」、すなわち「拝島(はいじま)」という地名になったとされています。
その言い伝えをもとに造られたのが、堂内の「木造大日如来坐像」です。平安時代後期に作られたと言われ、東京都の有形文化財に指定されています。普段は見ることのできない秘仏ですが、文化財ウィークで特別に公開されます。この大日如来は2020年からの修復補修を終え、今年が初公開。平安時代の古い彫刻の様子がよくわかるように復元された衣や台座を、間近で見ることができます。
また特別公開では、大日如来の両脇に安置されている都指定有形文化財の「釈迦如来坐像」と「阿弥陀如来坐像」も見学できます。
大日堂
住所:東京都昭島市拝島町1-10-14電話:042-541-1009(普明寺)
特別公開
11月3日(祝・木)午前11時・午後1時・午後3時
2022年11月1日(火)
「自由学園明日館」

 国の重要文化財に指定されている「自由学園明日館(みょうにちかん)」を紹介します。
国の重要文化財に指定されている「自由学園明日館(みょうにちかん)」を紹介します。明日館は1921(大正10)年に女学校の校舎として建てられました。設計は、旧帝国ホテルなども手がけたアメリカの建築家、フランク・ロイド・ライト。草原住宅をイメージした「プレーリースタイル」と呼ばれる建築手法で建てられていて、軒(のき)を低く抑え、水平な線が強調されているのが特徴です。現在、この建物は通年で見学することができます。
館内に入ると、入り口は暗く、天井高2m10cm。圧迫感のある空間になっています。あえて低くした天井を抜けた先には、天井高5m40cmの開放的なホールがあり、空間の広がりを演出しています。そしてもう一つの見どころは、大きな窓に木枠で施された幾何学模様です。このデザインは校舎の至るところに見られ、建物全体の統一感を生み出しています。
かつて生徒たちが利用していた食堂は現在、見学者の喫茶スペースになっています。団らんの象徴として作られた暖炉や実際に生徒たちが使っていた机も一部残され、今もここで使用されています。
自由学園明日館
住所:東京都豊島区西池袋2-31-3電話:03-3971-7535
開館時間:午前10時〜午後4時 ※夜間・休日見学日あり
休館日:月曜(祝日の場合は翌日)※不定休あり
見学料:500円
コーヒー・紅茶&焼き菓子付見学料:800円
HP:https://jiyu.jp/
2022年11月2日(水)
「日本銀行本店本館」

 国の重要文化財に指定されている「日本銀行本店本館」を紹介します。
国の重要文化財に指定されている「日本銀行本店本館」を紹介します。ここは、1896(明治29)年に竣工した明治期の洋風建築を代表する建物です。設計は、東京駅丸の内駅舎も手がけた「日本近代建築の父」辰野金吾。日本人建築家が手がけた最初の国家的近代建築で、石積み煉瓦(れんが)造りという耐震性の高い構造になっています。
建物の内部は通年で公開されています。地下金庫への現金搬入ルートでもあった中庭は、セキュリティ面から閉鎖的な空間となっています。旧営業場の天井は、現在は照明が入っていますが、建築当初はガラス天井・ガラス屋根で自然光が降り注ぐような設計になっていました。そして建物の最深部、地下金庫の入り口にあるのが、重さ25t、厚さ90cmの大金庫扉。金庫内では、建築当初から2004年まで使われていた扉や白い釉薬(ゆうやく)を塗った煉瓦の壁などを見ることができます。
日本銀行本店本館
住所:東京都中央区日本橋本石町2-1-1電話:03-3277-2815
見学日:月〜金曜(祝日・年末年始を除く)
料金:無料
※事前予約制
予約サイト:https://www5.revn.jp/bojtour/
2022年11月3日(木)
「小机家住宅」

 東京都の有形文化財に指定されている「小机(こづくえ)家住宅」を紹介します。
東京都の有形文化財に指定されている「小机(こづくえ)家住宅」を紹介します。小机家は江戸時代後期に山林業などで財を成しました。この住宅は、第7代目当主の三左衛門が1875(明治8)年頃に建てたとされています。土壁・土蔵造りの伝統的な技法の中に、西洋風の丸い柱や2階のバルコニーなどを取り入れた外観が特徴です。
現在、建物は喫茶室として使用され、内部も一部が通年で公開されています。西洋風の外観とは異なり、玄関は土間で、内部は昔ながらの和風な造り。壁には「こて絵」と呼ばれる、漆喰(しっくい)を使った左官の彫刻が施されています。
さらに、文化財ウィークで特別に公開されるのが、通常は入ることができない和室です。畳の落ち着いた雰囲気の中にガラス窓の扉を取り入れたところに、西洋への憧れが感じられます。また特別公開では、宝船などの繊細な彫り細工が施された螺旋(らせん)階段を使って2階に上がることもできます。
小机家住宅
住所:東京都あきる野市三内490電話:042-596-4158
小机邸喫茶室 安居
営業日:月・金・土・日曜・祝日
営業時間:午前11時〜午後4時
特別公開
11月6日(日)まで午前11時〜午後4時
2022年11月4日(金)
「弁才天十五童子像」
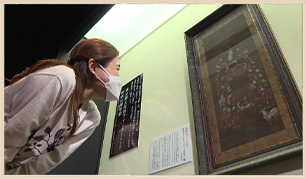
 日野市にある関東三大不動の1つ、「高幡不動尊」の文化財を紹介します。
日野市にある関東三大不動の1つ、「高幡不動尊」の文化財を紹介します。境内正面の重要文化財「仁王門」や、室町時代前期に建立されたとされる「不動堂」のほか、古文書を中心に1万点以上の文化財が残されています。
様々な文化財を通年で公開している奥殿には、本尊の「不動明王坐像」が安置されています。平安時代後期の作で、高さは約3m。向かって右側に「矜羯羅童子(こんがらどうじ)像」、左脇に「制吒迦童子(せいたかどうじ)像」が安置され、3体で国の重要文化財に指定されています。
文化財ウィークで特別に公開されるのが、都指定有形文化財の「絹本着色弁才天十五童子(けんぽんちゃくしょくべんざいてんじゅうごどうじ)像」です。制作は室町時代と推定され、中央に弁才天、その下には弁才天に仕える十五童子、そして大黒天が描かれています。七福神の弁才天と大黒天が一枚の絵に描かれていることが貴重だと言われています。七福神信仰は江戸時代に広まりましたが、この絵は室町時代に描かれたとされているため、七福神信仰の原型を示す資料として注目されています。
高幡不動尊金剛寺
住所:東京都日野市高幡733電話:042-591-0032
HP:https://www.takahatafudoson.or.jp/
奥殿
拝観時間:午前9時〜午後4時
休館日:月曜(1月・祭り期間中を除く)
拝観料:300円
特別公開
11月6日(日)まで
東京文化財ウィーク2022
電話:03-5320-6862(東京都教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当)
HP:https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/week.html







