 |





|
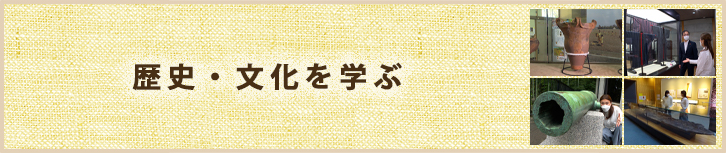
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2022年10月17日(月)
「清瀬市郷土博物館」

 「清瀬市郷土博物館」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。
「清瀬市郷土博物館」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。多摩北部に位置し、広大な農地が広がる清瀬市には、農村地帯ならではの文化財が残されています。
その一つが明治から昭和初期まで織られていた「清瀬のうちおり」と呼ばれる衣類で、国の重要有形民俗文化財に指定されています。家で織られたため「うちおり」と呼ばれ、農家の女性たちが自分や家族のために織って着ていたもので、商品にならない屑繭(くずまゆ)や余った木綿糸をつなげて織った反物から作られています。戦時中に作られたうちおりの中に、銀の糸が一本だけ織り込まれているものが展示されています。戦時中は銀の糸はぜいたく品とされ、使用が禁止されていましたが、当時の女性たちのセンスや政府に対する反骨心から反物に織り込まれたものだろうと言われています。古くなったうちおりはオムツや雑巾などにして使い、最後は燃やして、その灰を畑の肥料に利用しました。
博物館のもう一つの見所が、清瀬市の文化や伝統を伝えるために江戸時代の農家を再現した伝承スタジオ。きく姫さんは江戸時代に実際に使われていた道具「火のし」を体験しました。火のしは今でいうアイロンです。熱した炭を金属製の器に入れ、その熱を使って布を伸ばします。この伝承スタジオでは、それ以外にも郷土料理づくりや季節の行事を体験することができます。
清瀬市郷土博物館
住所:東京都清瀬市上清戸2-6-41電話:042-493-8585
開館時間:午前9時〜午後5時
休館日:月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始
入場料:無料(一部の特別展を除く)
HP:http://museum-kiyose.jp/
2022年10月18日(火)
「江東区中川船番所資料館」

 「江東区中川船番所資料館」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。
「江東区中川船番所資料館」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。江東区はかつて、江戸時代に作られた水路によって発展し、水運の要所となっていました。
資料館では、江戸時代に実際にあった「中川番所」という“川の関所”のジオラマを展示しています。中川番所は、江戸に入って来る船とその積荷を検査していました。その時に使われた当時の通行手形(複製)も見ることができます。鉄砲などの武器類は江戸に絶対に入れてはいけない決まりがあったため、積荷は非常に厳しく検査されたそうです。中川番所には、関所ならではのシンボルとして槍が並べられていました。遠くからでも番所の場所をわかりやすくする目的と、幕府が取り締まっている場所として威嚇する目的があったと言われています。
明治維新以降は蒸気船が往来するようになり、川沿いは工場が立ち並ぶ景色へと変わっていきました。豊かな水資源を利用して、1875(明治8)年には日本初の国産セメント工場である浅野セメント工場、1895(明治28)年には日本精製糖株式会社などが設立されました。
江東区中川船番所資料館
住所:東京都江東区大島9-1-15電話:03-3636-9091
開館時間:午前9時30分〜午後5時
休館日:月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始
観覧料:一般 200円 小・中学生 50円
HP:https://www.kcf.or.jp/nakagawa/
2022年10月19日(水)
「板橋区立郷土資料館」

 「板橋区立郷土資料館」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。
「板橋区立郷土資料館」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。高島平団地など数多くの団地が建てられた東京のベッドタウンの一つ、板橋区。
資料館でまず目に留まったのは、江戸時代に作られたモルチール砲です。江戸時代後期はアヘン戦争などが起こり、政情不安になっていたため、幕府の直轄地だった現在の高島平周辺では、西洋流の砲術訓練が行われました。その訓練で使われたのがモルチール砲です。使用された弾丸も保存されています。
天保12(1841)年に行われた大砲や鉄砲の訓練の様子を描いた『高島四郎太夫砲術稽古業見分之図(たかしましろうだゆうほうじゅつけいこわざけんぶんのず)』からは、当時の砲術調練の様子がわかります。この訓練で指揮をとったのが、長崎で砲術を学んだ高島秋帆(しゅうはん)でした。弟子99人を引き連れ、一斉射撃などを披露しました。このことから高島秋帆の名前が、今の高島平の地名の由来となりました。
資料館には、江戸時代に建てられた茅葺の農家「旧田中家住宅」も展示されており、中を自由に見学できます。4つの部屋が上から見ると田んぼの「田」の字に見える、「田の字型造り」の農家です。農家のカマドには現在も毎週1度火がくべられ、茅葺き屋根をいぶして、保存のための防虫対策を行っています。
江戸時代の板橋は農業が盛んで、大根の品種の名前に板橋の地名「徳丸」が付けられるほど大根を大量に栽培していました。資料館の一隅には、大根が4000本ほど入る漬物樽(つけものだる)も残されています。
板橋区立郷土資料館
住所:東京都板橋区赤塚5-35-25電話:03-5998-0081
開館時間:午前9時30分〜午後5時
休館日:月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始
入場料:無料
HP:https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyodoshiryokan/
2022年10月20日(木)
「西東京市郷土資料室」

 「西東京市郷土資料室」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。
「西東京市郷土資料室」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。2001年に、田無市と保谷市が合併してできた西東京市。西東京市の東部には、2015年に国の指定史跡になった下野谷(したのや)遺跡があります。
下野谷遺跡は縄文時代に約1000年間続いた集落の遺跡で、南関東最大級の集落だったと考えられています。この遺跡から出土した土器などが展示されている「西東京市郷土資料室」を訪ねました。
下野谷遺跡から発見された土器の中には、この遺跡ならではのものがあります。土器の体の部分は関東の土器の特徴を備え、頭の部分は4つの突起を付けた甲信越の土器の特徴を備えるという、2つの地域の特徴を兼ね備えた土器です。これは下野谷に複数の地域から縄文人が集まってきた証拠の一つだと考えられています。
さらに、この遺跡の土器からは「圧痕(あっこん)」も見つかっています。「圧痕」とは、土器に種子などが付着してできた窪みのこと。この窪みの型を取り、種子を特定することで、当時の食文化を知る手がかりが得られます。土器に付着していた大豆が野生のものよりも大きいことから、当時既に栽培が行われていたことがわかり、縄文人の豊かな食文化が浮かび上がってきました。
下野谷遺跡では縄文時代を感じ取れる最新システムを導入し、西東京市の公式アプリ「VR下野谷縄文ミュージアム」を使うと、VR(仮想現実)によって下野谷遺跡での縄文時代の生活を体感できます。
西東京市郷土資料室
住所:東京都西東京市西原町4-5-6電話:042-467-1183
開室時間:午前10時〜午後5時
正午〜午後1時は閉室
休室日:月曜、火曜、年末年始
利用料:無料
HP:https://www.city.nishitokyo.lg.jp/sisetu/other/kyodo.html
2022年10月21日(金)
「北区飛鳥山博物館」

 「北区飛鳥山博物館」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。
「北区飛鳥山博物館」を訪ね、地域の歴史や文化を学びました。北区にある飛鳥山は、徳川吉宗が愛した場所の一つで、吉宗が1270本もの桜を植えさせたことから、江戸の人々が集まる行楽の場所になったと言われています。博物館では、将軍専用の休憩場所「御膳所(ごぜんしょ)」を再現して展示しています。吉宗以降の将軍はこの御膳所から飛鳥山の眺望を楽しんでいましたが、やがて庶民も飛鳥山を訪れるようになり、日帰りで楽しめる行楽地となりました。この行楽の最大の楽しみが「花見弁当」。館内には江戸時代の料理本から再現したお弁当が展示されています。
もう一つの見所が、北区で発掘された国内最大規模の縄文時代の貝塚である「中里貝塚」。長さ約700m・幅約100m・深さ4.5m(最大)という規模で、およそ800年かけて作られた貝塚です。2000年に国の史跡に指定されました。この貝塚の調査によって、縄文人がハマグリや牡蠣に熱を加え、大量に加工していたことがわかってきました。さらに、貝塚に捨てられたハマグリがどれも成長しきったサイズであることから、縄文人のルールの中に、ある程度の大きさになるまではハマグリを採らず、資源を確保する考えがあったこともわかってきました。
貝塚からは、全長5.79mの丸木舟も発見され、その実物が展示されています。
北区飛鳥山博物館
住所:東京都北区王子1-1-3電話:03-3916-1133
開館時間:午前10時〜午後5時
休館日:月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始
観覧料:一般300円 65歳以上150円
HP:https://www.city.kita.tokyo.jp/hakubutsukan/







