 |





|
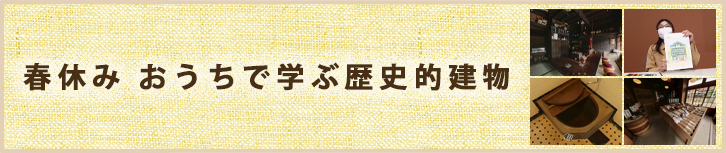
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2022年3月28日(月)
「昭和の居酒屋『鍵屋』」

 小金井市にある「江戸東京たてもの園」には、江戸時代から昭和にかけて建てられた建物、30棟が移築・復元されていますが、ホームページでも「360度パノラマビュー」で、自宅にいながら園内の建物を鑑賞することができます。
小金井市にある「江戸東京たてもの園」には、江戸時代から昭和にかけて建てられた建物、30棟が移築・復元されていますが、ホームページでも「360度パノラマビュー」で、自宅にいながら園内の建物を鑑賞することができます。幕末に酒問屋として台東区下谷に建てられたとされる「鍵屋」は、昭和24(1949)年に居酒屋として営業を始めました。建築当初は1階建てで、2階は大正初期に家族の住居として増築。その時に新たに作られた1階の屋根の部分は、瓦の庇(ひさし)と板の庇が二重になっているのが特徴です。
店内は昭和45年頃の様子に復元され、壁のメニューには当時の酒のつまみの一品料理が書かれています。天井は「根太(ねだ)天井」と呼ばれ、2階の床板とそれを支えるための「根太」という木材が露出していて、そのまま天井になっています。
このパノラマビューでは、建物の間取り図も見ることができます。「鍵屋」1階の客席は2部屋あり、座敷の個室も用意されていました。さらにホームページからは、園内の建物について、ダウンロードして印刷することで、ペーパークラフトを作ることもできます。
2022年3月29日(火)
「昭和の看板建築『植村邸』」

 「江戸東京たてもの園」のホームページにある「360度パノラマビュー」では、自宅にいながら園内の建物を見ることができます。
「江戸東京たてもの園」のホームページにある「360度パノラマビュー」では、自宅にいながら園内の建物を見ることができます。昭和2(1927)年に中央区に建てられた「植村邸」は、時計や貴金属を扱う商売をしていた店舗兼用住宅で、家主の植村三郎さんがデザインしたとされる看板建築の名作です。看板建築とは、関東大震災以降、防火のために外壁を銅板やタイルなどで覆った建築様式のこと。建物正面をキャンバスに見立てて、自由にデザインを施したのも特徴の一つです。
この植村邸の2階の8畳の座敷は、通常は見学できない非公開エリアですが、パノラマビューでは、このような非公開エリアも見ることができます。床の間は伝統的な書院造りですが、地袋が斜めの形にデザインされていて、家主の遊び心が伺えます。竹が描かれた豪華な襖もあり、これは植村さんがお気に入りの職人に描いてもらったと伝えられています。
さらに、ホームページからは、園内の建物について楽しく学ぶことができる塗り絵もダウンロードできます。
2022年3月30日(水)
「昭和の乾物屋『大和屋本店』」

 「江戸東京たてもの園」のホームページにある「360度パノラマビュー」では、自宅にいながら園内の建物を見ることができます。
「江戸東京たてもの園」のホームページにある「360度パノラマビュー」では、自宅にいながら園内の建物を見ることができます。昭和3(1928)年に港区白金台に建てられた「大和屋本店」は、鰹節などを扱う商店を営んでいました。看板建築でありながら、出桁(だしげた)造りという建築様式も持ち合わせた建物です。出桁造りは、屋根の垂木(たるき)を水平に支える桁が外から見えるのが特徴。軒を大きく丈夫にするための工夫だったそうです。
店内は、大豆などの豆類やスルメの他、鰹節を並べて販売する昭和初期の乾物屋の様子が再現されています。
そしてパノラマビューでは、通常は見学できない非公開エリアの2階も見ることができます。10畳の和室には床の間があり、床柱には装飾品などに使用される銘木「黒檀(こくたん)」が使われています。さらにホームページには、大和屋で扱っていた乾物についてのクイズもあって、親子で楽しみながら勉強することができます。
2022年3月31日(木)
「台所の歴史」

 「江戸東京たてもの園」のホームページで公開している『「昔のくらし」たんけんマップ』では、生活に欠かせない3つの水回りについて時代ごとに紹介しています。自宅にいながら建物を見ることができる「360度パノラマビュー」を使って、様々な建物の「台所」を見学しました。
「江戸東京たてもの園」のホームページで公開している『「昔のくらし」たんけんマップ』では、生活に欠かせない3つの水回りについて時代ごとに紹介しています。自宅にいながら建物を見ることができる「360度パノラマビュー」を使って、様々な建物の「台所」を見学しました。江戸中期に建てられたとされる農家「綱島家」の台所には、座って作業する「座り流し」があります。家の北側の、薄暗くて寒い場所にあるのが、この時代の台所の特徴です。
大正時代になると主婦の役割が向上し、台所が家庭の重要な場所として大きく変わり始めます。大正14(1925)年に建てられた「小出邸」の台所は、ガラス窓から光を多く取り入れています。また、水道やガスが少しずつ家庭に普及し始めたことから、日常の家事を楽にするため、立ったまま作業できる台所へと改善されていきました。
そして、昭和17(1942)年に完成した「前川國男邸」では、日本の現代建築の発展に大きく貢献した建築家・前川國男が設計した台所を見ることができます、昭和30年代を再現し、戦後復興から高度成長へ向かっていく時代が感じられます。白を基調に清潔感があり、電気冷蔵庫やガスコンロも備えるなど、台所が家庭の重要な場所になってきたことが伺えます。
2022年4月1日(金)
「お風呂の歴史」

 「江戸東京たてもの園」のホームページで公開している『「昔のくらし」たんけんマップ』では、生活に欠かせない3つの水回りについて時代ごとに紹介しています。自宅にいながら建物を見ることができる「360度パノラマビュー」を使って、様々な建物の「お風呂」を見学しました。
「江戸東京たてもの園」のホームページで公開している『「昔のくらし」たんけんマップ』では、生活に欠かせない3つの水回りについて時代ごとに紹介しています。自宅にいながら建物を見ることができる「360度パノラマビュー」を使って、様々な建物の「お風呂」を見学しました。幕末から明治初期に建てられたとされる「万徳旅館」のお風呂は、当時の宿屋に多かった五右衛門風呂。明治初期を再現して、屋外に設けられています。
大正時代になると、一部の住宅ではお風呂を屋内に備えるようになります。製糸業で財を成した西川伊左衛門によって建てられた「西川家別邸」は、大正11(1922)年に完成しました。建築当時を再現したお風呂は、熱気が冷めないように、釜が鉄でできています。
大正14(1925)年に建てられた「田園調布の家(大川邸)」は、郊外の住宅地に分譲されたモダンな家です。建築当時を想定して再現したお風呂の浴槽には、大正後期から昭和初期に最先端の素材だった白いタイルが使用されています。
江戸東京たてもの園
住所:東京都小金井市桜町3-7-1(都立小金井公園内)
電話:042-388-3300(代表)
HP:https://www.tatemonoen.jp/
※最新情報はホームページをご確認下さい
360度パノラマビュー:https://www.tatemonoen.jp/restore/intro/







