 |





|
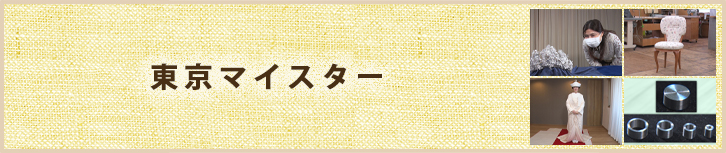
<1週間分の動画はこちら>
※ここから先はYouTubeです
2022年2月14日(月)
「貴金属細工加工の匠」

 貴金属細工加工工の片桐毅幸さんは、この道27年。デザイン画を基にティアラやネックレスなどのジュエリーを作る優れた技術が評価され、令和3年度の東京マイスターに選ばれています。
貴金属細工加工工の片桐毅幸さんは、この道27年。デザイン画を基にティアラやネックレスなどのジュエリーを作る優れた技術が評価され、令和3年度の東京マイスターに選ばれています。片桐さんが制作に携わったバラがデザインされたネックレスは、ホワイトゴールドの地金にダイヤモンドや真珠が飾られています。片桐さんが携わったのは平面に描かれたデザイン画を、立体的な地金に仕上げていく作業。デザイン画には描かれていない、ネックレスの繋ぎの部分も形作ることができるのが、片桐さんの匠の技です。
バラの葉のパーツは、葉に立体的な丸みをつけ、自然な風合いになるように一枚一枚に変化をつけながら仕上げました。片桐さんは、「立体的にした時にきれいな形、360度回した状態で違和感のないラインを常に心がけています」と話しています。
ミキモト装身具
電話:03-3463-9221HP:https://www.mikimoto-jf.co.jp/
2022年2月15日(火)
「椅子張りの匠」

 椅子張り職人の鈴木宗彦さんは、この道27年。これまでに迎賓館や三菱一号館美術館などにある椅子の修復や復元に携わっています。また、様々な椅子張りの技術を駆使して、オーダーメイドの椅子も制作しています。
椅子張り職人の鈴木宗彦さんは、この道27年。これまでに迎賓館や三菱一号館美術館などにある椅子の修復や復元に携わっています。また、様々な椅子張りの技術を駆使して、オーダーメイドの椅子も制作しています。鈴木さんが手がけた椅子にきく姫さんが座らせてもらうと、程よい硬さと柔らかさを合わせ持つ座り心地の良さがありました。その秘密は、鈴木さんが現代的な技法と伝統的な技法を使い分けて座面作りをしている点にありました。座面のふちは、馬の毛を使った伝統的な技法を用いて形と硬さを保ち、座面の中央部分はウレタンのクッション材を重ねる現代的な技法で効率よく仕上げて、価格を抑えています。鈴木さんは、こうした伝統技法と現代技法を使い分ける優れた技術などが評価され、令和3年度の東京マイスターに選ばれています。
鈴幸装備
住所:東京都足立区入谷5-11-8電話:03-3857-6731
HP:http://www.koshikake.com/index.html
2022年2月16日(水)
「着付けの匠」

 衣装着付師の鈴木由喜枝さんは、この道50年。着物やドレスの着付けの幅広い知識と優れた技術などが評価され、令和3年度の東京マイスターに選ばれています。
衣装着付師の鈴木由喜枝さんは、この道50年。着物やドレスの着付けの幅広い知識と優れた技術などが評価され、令和3年度の東京マイスターに選ばれています。今回は、特に高い技術が求められる「白無垢の着付け」を見せてもらいました。ここで重要なのは打掛を羽織る前の着付け。ドレープの幅や裾の長さを左右対称に仕上げられるかどうかで、足元のシルエットの美しさが決まるそうです。全身の美しいシルエットは、帯の高さでも変わってきます。鈴木さんが最も気を遣っているのは、帯結びを支える帯枕をつける時。背中との間に隙間ができないように、ぴったりとつけることが大切です。わずかな隙間が空いてしまうだけで印象が変わってしまうそうです。
「着付けが仕上がってお客さんに喜んでもらえる時に、一番やりがいを感じます」と鈴木さんは話しています。
チェリー美容室
住所:東京都板橋区南町30-4電話:03-3955-2543
HP:https://ameblo.jp/cherry-bellwood/
2022年2月17日(木)
「旋盤の匠」

 旋盤工の小池孝広さんは、この道23年。内視鏡の身体に入れる先端の部分の部品などを作っています。その高精度な金属加工の優れた技術が評価され、令和3年度の東京マイスターに選ばれています。
旋盤工の小池孝広さんは、この道23年。内視鏡の身体に入れる先端の部分の部品などを作っています。その高精度な金属加工の優れた技術が評価され、令和3年度の東京マイスターに選ばれています。小池さんが旋盤で加工したステレンスの筒の厚さは、わずか0.05mm。お札の半分の薄さです。このような加工ができる秘密は、使っている刃物にあります。完成品の形や大きさに合わせて刃先を自分で作ることで、どんな加工にも対応できるようにしています。今回は実際に直径6mmの部品を作ってもらいました。まずコンピュータ制御の旋盤にデータを入力し、オリジナルの刃先も使いながら外側と内側を削ります。この時、音の変化によって削り方を微調整します。さらに、刃物の当て具合を手動で操作する旋盤で、筒の長さも微調整。こうして作ってもらった部品を計測すると、その誤差わずか0.001mm。この精度の高さが小池さんの匠の技です。
小池製作所
住所:東京都八王子市下恩方町 1104-1電話:042-651-8129
HP:https://www.koike-s-s.com/
2022年2月18日(金)
「建築塗装の匠」

 建築塗装工の橋口俊行さんは、この道27年。マンションやビルなどの外壁や内装の塗装を手掛ける職人です。その優れた技術が評価され、令和3年度の東京マイスターに選ばれています。
建築塗装工の橋口俊行さんは、この道27年。マンションやビルなどの外壁や内装の塗装を手掛ける職人です。その優れた技術が評価され、令和3年度の東京マイスターに選ばれています。建築塗装で重要な下地作業では、一般的に金ベラという道具を使いますが、橋口さんは左官職人が使っている“コテ”も利用しています。コテを扱うには力加減などの感覚が大切で、橋口さんは、いまでは数少ない、コテも扱える建築塗装職人なのです。
また橋口さんは、鉛筆で下書きされた模様に沿って、色をはみ出すことなく塗り上げていきます。実際の現場では、塗る部分以外はテープなどで覆っていることが多いそうですが、それがなくてもきれいに仕上げられるのが橋口さんの匠の技です。さらに、橋口さんは塗装によって別の素材のように表現する特殊塗装も得意としています。例えば“鉄製の扉”を、長年使用された“木製の扉”のように塗装したり、べニヤ板を違う木目模様に仕上げたりすることもできます。
「自分が経験したものや自分の技術を後輩に伝えていきたい」と橋口さんは話してくれました。
佐藤興業(本社)
住所:東京都千代田区神田駿河台2-10電話:03-3294-1981
HP:https://www.p-sato.co.jp/







