 |





|
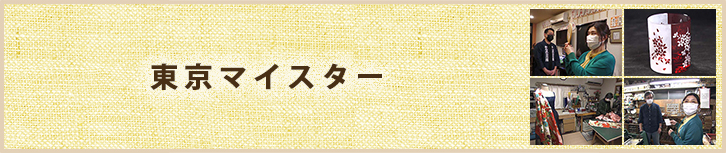
2021年3月1日(月)
「かざりかんざしの匠」

 かざりかんざし職人の三浦孝之さん(53歳)は、この道28年。
かざりかんざし職人の三浦孝之さん(53歳)は、この道28年。三浦さんが作る“かざりかんざし”は、金や銀、真鍮(しんちゅう)などの金属で作られていて、動植物や縁起を担ぐ意匠などをモチーフとしています。
三浦さんは、江戸時代のものを復刻する技術に優れ、歌舞伎や日本舞踊などに使われる伝統的なかんざしづくりが高く評価されています。また、和装以外でも日常生活で使いやすいものも制作しています。
桜のパーツを作る時には、花びらに丸みをつけ立体的にすることで本物のように仕上げます。硬い金属で表現するため、自然な風合いになるように工夫をしているそうです。桜や葉などのパーツを作ったら、完成図を想像しながらバーナーで溶接、花束を生けていくようにひとつに組み合わせます。
三浦さんは、デザインから完成まで一人で行う技術などが評価され、令和2年度の東京マイスターに認定されています。
かざり工芸三浦
住所:東京都墨田区東駒形3-22-7電話:03-6751-8858
HP:https://kazashi.exblog.jp/
2021年3月2日(火)
「ガラス研磨の匠」

 ガラス研磨工の松浦健二さん(47歳)は、この道32年。ガラス製品に圧縮した空気で砂を飛ばして彫刻する、サンドブラストと呼ばれる加工技術のスペシャリストです。
ガラス研磨工の松浦健二さん(47歳)は、この道32年。ガラス製品に圧縮した空気で砂を飛ばして彫刻する、サンドブラストと呼ばれる加工技術のスペシャリストです。1mmよりも細い線で描かれる図柄や文字を正確に彫刻することができ、立体的なものを仕上げる技術にも優れています。松浦さんは、その技術などが評価され、令和2年度の東京マイスターに認定されています。
ガラスを削るのに使う砂は6種類を使い分けています。細かい砂だと手の皮脂の跡が付きにくくなるので、使う人の立場を考えて使い分けているそうです。砂の種類が変わると、砂を当てる時間や角度も変わってきます。砂を自分の思い通りに扱えるのは松浦さんならではの技だそうです。
葛飾区伝統産業館
電話:03-5671-82882021年3月3日(水)
「洋裁の匠」

 婦人・子供服 注文仕立職の佐藤順子さん(61歳)は、この道33年。
婦人・子供服 注文仕立職の佐藤順子さん(61歳)は、この道33年。着物を洋服にリメイクする技術などが評価され、令和2年度の東京マイスターに認定されています。
佐藤さんの手によって洋服へ生まれ変わった作品は、和服を劇的に変化させながらも、着物の柄をしっかりと生かしています。お客さんの多くは、自分や母親などの着られなくなった着物を形を変えて、もう一度着たいとリメイクを依頼してくるそうです。
祝いの席で着る着物を裁断し、ピンで留めてドレスの形を作っていく作業を見せてもらいました。およそ1時間半で、あでやかなドレスに様変わりしました。華やかな柄を引き立たせるために紺色の下地を取り入れたり、柄が途切れた部分を隠すためにリボンを付けたり、様々な工夫が凝らされています。
J フローラ
住所:東京都新宿区富久町34-6電話:03-3357-7283
2021年3月4日(木)
「活版印刷の匠」
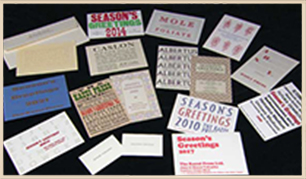
 活版印刷職人の髙岡昌生さん(63歳)は、この道38年。
活版印刷職人の髙岡昌生さん(63歳)は、この道38年。活字を読みやすく美しく並べる技術などが評価され、令和2年度の東京マイスターに認定されています。
活版印刷は、金属でできた印鑑のような“活字”を一つ一つ組み合わせ、インクを付けて紙に押し付けて印刷する技術です。
髙岡さんは特にアルファベットなど欧米諸国で使われる文字を使った印刷技術に優れています。全体のバランスが整えられ、読みやすく美しいと英国王立芸術協会など海外からも高く評価されています。
所有している活字の書体は約300。文字の大きさなどの違いで約1000種類の活字があるそうです。きく姫さんのイメージにあった書体を選んでもらい、ネームカードを作ってもらいました。
文字と文字の間が詰まって見えるところや広がって見えるところを均一に調整するために、厚さ約0.3mmと約0.15mmの金属片を使います。この金属の有無で、わずかな差でも仕上がりを左右するそうです。文字の隙間を調整し、より読みやすくできるのが髙岡さんの匠の技です。
嘉瑞工房
住所:東京都新宿区西五軒町11-1電話:03-3268-1961
HP:https://kazuipress.com/
2021年3月5日(金)
「左官の匠」

 左官職人として、代々伝わる江戸の伝統工法を引き継ぐ木村一幸さん(62歳)は、この道45年。
左官職人として、代々伝わる江戸の伝統工法を引き継ぐ木村一幸さん(62歳)は、この道45年。現代では珍しい伝統的な壁塗りの技術を持つ職人として、令和2年度の東京マイスターに認定されています。木村さんはこれまでに、土壁塗りや磨き仕上げなどの様々な技術を駆使し、茶室などを手掛けています。国会議事堂内の部屋の天井は、伝統的な漆喰(しっくい)塗りで制作したそうです。
壁を塗る時に一番気をつけていることは、“ちり周り”を汚さないことだといいます。ちり周りとは、木枠と壁の境目のことで、隅々まで塗り上げる際に木枠を全く汚さないことが大事だといいます。実際の現場では、柱や梁などをビニールテープなどで保護していることが多いそうですが、それがなくても汚さずに仕上げられるのが、木村さんの匠の技です。
さらに木村さんは、今では知識や技術を持つ人が少なくなった伝統的な壁塗りについて、次世代への指導や育成も行っています。
木村左官工業所
住所:東京都文京区水道2-3-17電話:03-3811-8480
HP:http://www.kazuu.co.jp/







