 |




|
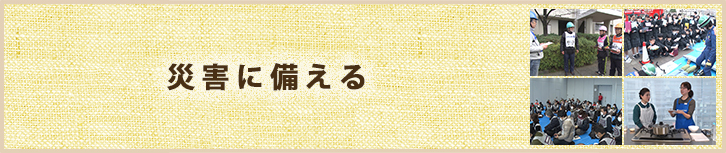
2020年3月9日(月)
「住民同士の組織づくり」

 約1400世帯が暮らす「昭島つつじが丘ハイツ北」は、65歳以上の住民が全体の4割以上を占めています。
約1400世帯が暮らす「昭島つつじが丘ハイツ北」は、65歳以上の住民が全体の4割以上を占めています。災害発生後15分以内に住民全員の安否を確認できる住民同士の組織化された防災活動が注目され、総務省が行う「防災まちづくり大賞」を受賞しました。
マンションに住む世帯を細かくグループ分けし、それぞれのグループが同時に安否確認をすることで、短い時間で情報が集まりやすくなります。
また安否確認をスムーズに行うため、「無事」か「救助が必要」か一目でわかるマグネット製ステッカーを全世帯に配布、災害時に玄関ドアに貼り付けます。
毎年、約9割の世帯が参加する安否確認の訓練を繰り返し行うほか、お花見会や芋煮会など、住民同士の交流の場を積極的に設け、名前で呼び合える関係づくりにも力を入れています。
昭島つつじが丘ハイツ北住宅団地
管理組合電話:042-546-1977
2020年3月10日(火)
「中学生が担う地域防災」

 港区立港南中学校では、生徒を地域防災の担い手として育てる取り組みを10年ほど前から続けています。2月には地域の防災設備など自分たちの住む町を知る「防災まち歩き」が行われました。
港区立港南中学校では、生徒を地域防災の担い手として育てる取り組みを10年ほど前から続けています。2月には地域の防災設備など自分たちの住む町を知る「防災まち歩き」が行われました。港南中学校は運河に囲まれた高層マンションが建ち並ぶ住宅地にあり、平日の日中は住民の多くが地域の外に働きに出ているため、もし災害で橋が使えなくなり孤立してしまった場合、中学生が地域を守る要になります。
港南中学校は「区民避難所」に指定され、避難所の設営や運営に中学生が主体的に関わることが期待されています。避難所生活を想定した宿泊訓練や炊き出しの訓練など毎月のように防災の授業が行なわれ、秋の総合防災訓練では、中学生が地域の人に防災の指導を行っています。
港区立港南中学校
電話:03-3471-02382020年3月12日(木)
「帰宅困難者の受け入れ」

 首都直下型の大地震が起きた場合、都内では会社など身を寄せる場所がない、「行き場のない帰宅困難者」が多数発生すると想定され、公共施設や民間企業でそのような帰宅困難者を受け入れる取り組みが広がっています。
首都直下型の大地震が起きた場合、都内では会社など身を寄せる場所がない、「行き場のない帰宅困難者」が多数発生すると想定され、公共施設や民間企業でそのような帰宅困難者を受け入れる取り組みが広がっています。複数の企業や飲食店が入る品川シーズンテラスでは防災備蓄倉庫を設置し、300人が3日間とどまれる水や食料などを保管しています。
先月、品川駅周辺で帰宅困難者対策訓練が行われ、品川シーズンテラスでは実際の地震を想定し、限られた人数で大勢の帰宅困難者を受け入れる体制づくりに重点を置き、受入場所の設営や運営を行いました。
今後の課題として、清掃や警備スタッフの協力や、プライバシー保護のためのパーテーションなど、食料品以外の備蓄の見直しが検討されています。
帰宅困難者訓練について
HP:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kitaku_portal/index.html2020年3月13日(金)
「もしもの時の調理術」

 東京ガスでは、災害時、電気やガスが使えなくてもカセットコンロで調理ができ水も節約できるというレシピを紹介しています。
東京ガスでは、災害時、電気やガスが使えなくてもカセットコンロで調理ができ水も節約できるというレシピを紹介しています。高密度ポリエチレンと呼ばれる、耐熱性の袋に食材を入れて袋ごと湯煎する「お湯ポチャ」という調理法で「ごはん」や「おかゆ」の調理を実践しました。一つの鍋で同時に調理でき、袋ごと器に盛りつけることで、食器を洗う水も節約できます。
また「スープパスタ」「麻婆高野豆腐」「パンケーキ」の3つを一つの鍋で同時に作ることもできます。
東京ガスでは、いつも食べ慣れている食材を災害時にも活用することが大切だと提案しています。
東京ガス 防災レシピ公開サイト
HP:https://www.tokyo-gas.co.jp/scenter/hibimoshi/







