 |





|
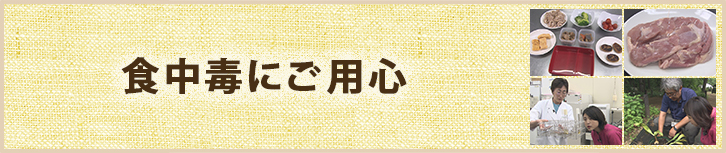
2019年6月24日(月)
「食中毒予防3原則」

 去年全国では1万7282人の食中毒患者が発生しました。高温多湿の季節は細菌が増えやすく、食品が傷みやすくなります。
去年全国では1万7282人の食中毒患者が発生しました。高温多湿の季節は細菌が増えやすく、食品が傷みやすくなります。調理して数時間後に食べる弁当は特に注意が必要です。
細菌やウイルスを「つけない」「ふやさない」「やっつける」。
この3つが食中毒予防に必要です。
調理を始める前にやることは「つけない」。石けんを使って指の間や爪の間など、手をキレイに洗いましょう。
「ふやさない」ためには、水分が出ないようにすることが大切です。おかずやご飯は、湯気が出なくなるまで冷ましてから弁当箱に詰めましょう。
「やっつける」ためには、肉のおかずの場合は中心部を75℃以上で1分以上加熱すること。卵焼きは中が半熟にならないようにしっかり火を通しましょう。弁当を持ち運ぶときは、保冷剤や保冷バックを活用し、なるべく低温で持ち運ぶことが大切です。
2019年6月25日(火)
「アニサキスの食中毒予防」

 アニサキスによる食中毒の報告件数が、去年468件と急増し、食中毒の原因第1位でした。
アニサキスによる食中毒の報告件数が、去年468件と急増し、食中毒の原因第1位でした。アニサキスは、サバやアジ、サケなど約160種の魚に寄生しているとされています。症状は激しい腹痛、吐き気、おう吐など。
アニサキスは内臓などに寄生するため、魚を生で食べる場合は、最初に内臓を取り除くことが大事です。さらに内臓周りの筋肉を切り落とすことも効果があります。アニサキスは、酢でしめても死にませんが、「冷凍」と「加熱」で防げます。
家庭の冷凍庫で48時間以上冷凍、もしくは60℃で1分以上加熱するとアニサキスは死滅します。
2019年6月26日(水)
「カンピロバクターの食中毒予防」
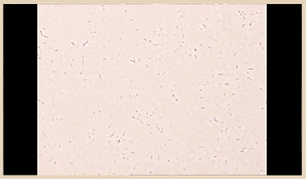
 去年、都内で発生した細菌性の食中毒は、カンピロバクターによるものが、およそ6割を占めていました。
去年、都内で発生した細菌性の食中毒は、カンピロバクターによるものが、およそ6割を占めていました。カンピロバクターの食中毒は、鶏肉やレバーなどを生の状態や加熱不十分で食べると発症する可能性があります。症状は下痢、腹痛、発熱などです。
予防のポイントは、「十分に加熱して食べること」。加熱の目安は、中心部を75℃で1分以上です。肉の中の色が白くなるまで、しっかり加熱しましょう。
2019年6月27日(木)
「サルモネラの食中毒予防」

 サルモネラは、鶏や牛などの腸管内や河川、土壌など自然界に広く生息していて、食中毒の症状は、高熱や下痢、腹痛などです。
サルモネラは、鶏や牛などの腸管内や河川、土壌など自然界に広く生息していて、食中毒の症状は、高熱や下痢、腹痛などです。サルモネラは高温の環境だと増殖するという特徴があるため、肉などの生鮮食品は冷蔵庫で保存することが大切です。
ニワトリから鶏肉に加工する段階でサルモネラが肉についてしまうこともあるため、調理をする時も注意が必要です。まず先に生野菜を切って、その後に肉を切る。または野菜と肉で調理器具を使い分けるようにしましょう。さらに、鶏肉は75℃で1分以上中心部を加熱しましょう。
卵を生で食べる時は、賞味期限内に食べるようにして、卵の殻にヒビが入っているものは、十分に加熱して食べるようにしましょう。
2019年6月28日(金)
「身近にある有毒植物」

 2009年から2018年の10年で、全国では780人が有毒植物による食中毒になり、そのうち12人が亡くなっています。
2009年から2018年の10年で、全国では780人が有毒植物による食中毒になり、そのうち12人が亡くなっています。誤食事故が一番多いのがニラと間違えてスイセンを食べるケース。
ニラとスイセンは見た目がそっくりで、スイセンを食べるとおう吐や下痢などを引き起こします。
見分けるポイントは、葉をちぎった時のにおい。ニラと違ってスイセンにはにおいがありません。
ギョウジャニンニクと間違えやすいイヌサフランは、食べるとおう吐や下痢などを引き起こし、重症の場合は死亡してしまうケースもあります。見分けるポイントは、やはり葉をちぎってつぶした時のにおい。イヌサフランには、においがありません。さらに、イヌサフランの球根はタマネギによく似ているため、注意が必要です。
有毒植物か食用の植物かもし迷ったら、絶対に採らない、食べない、人にあげないようにしましょう。
東京都薬用植物園
住所:東京都小平市中島町21-1電話:042-341-0344
開園時間:午前9時〜午後4時30分(10〜3月は午後4時まで)
休園日:月曜(祝日の場合は翌日、4・5月とイベント開催日は開園)、12月29日〜1月3日
入園料:無料
HP:http://www.tokyo-eiken.go.jp/lb_iyaku/plant/
東京都健康安全研究センター
電話:03-3363-3231
HP:http://www.tokyo-eiken.go.jp







