 |





|

2018年7月9日(月)
「高齢者の熱中症対策」
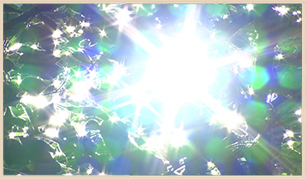
 去年夏、都内では3,167人が熱中症で搬送されており、その約半数が65歳以上の高齢者です。若い人に比べ体内の水分量が少ない高齢者は体の冷却能力が低下し、熱中症になりやすいそうです。はじめは二日酔いのような気分の悪さや、めまいといった症状ですが、重くなると吐き気や意識障害、重症になると死に至ることもあります。暑さの続くこの季節、「水分はもちろん塩分も取る」「アイシング」など、熱中症への対策を紹介。
去年夏、都内では3,167人が熱中症で搬送されており、その約半数が65歳以上の高齢者です。若い人に比べ体内の水分量が少ない高齢者は体の冷却能力が低下し、熱中症になりやすいそうです。はじめは二日酔いのような気分の悪さや、めまいといった症状ですが、重くなると吐き気や意識障害、重症になると死に至ることもあります。暑さの続くこの季節、「水分はもちろん塩分も取る」「アイシング」など、熱中症への対策を紹介。江東病院
住所:東京都江東区大島6-8-5電話:03-3685-2166
HP:http://www.koto-hospital.or.jp
2018年7月10日(火)
「蚊の発生防止」

 2014年に約70年ぶりに蚊を媒介とするデング熱の国内感染が確認され、蚊の対策の重要性が浮き彫りとなりました。東京都では今年度「蚊もなく孵化(ふか)もなし!!」という標語のもと、蚊が媒介する感染症の予防を目指しています。蚊に卵を産ませない、孵化させない、蚊の幼虫ボウフラが発生しやすい「たまり水」をなくすことが大切です。一般住宅でボウフラが発生しやすいポイントとは?
2014年に約70年ぶりに蚊を媒介とするデング熱の国内感染が確認され、蚊の対策の重要性が浮き彫りとなりました。東京都では今年度「蚊もなく孵化(ふか)もなし!!」という標語のもと、蚊が媒介する感染症の予防を目指しています。蚊に卵を産ませない、孵化させない、蚊の幼虫ボウフラが発生しやすい「たまり水」をなくすことが大切です。一般住宅でボウフラが発生しやすいポイントとは?東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課
電話:03-5320-4394HP:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/baikaikataisaku/index.html
2018年7月11日(水)
「水辺の危険」

 東京消防庁管内では水辺での事故が毎年200件以上起きています。小岩水難救助隊が有事に備え定期的に行っている訓練を紹介。水辺での注意事項や溺れている人を発見した時の対策を教えてもらいました。事故の例としては、釣りや遊びに来て誤って転落してしまうということが多いそうです。水辺で楽しむ機会が増える夏。溺れている人を見たときの対処法や、ペットボトルに少量の水を入れて投げ入れ、浮き輪代わりにしてもらう救命法などを紹介します。
東京消防庁管内では水辺での事故が毎年200件以上起きています。小岩水難救助隊が有事に備え定期的に行っている訓練を紹介。水辺での注意事項や溺れている人を発見した時の対策を教えてもらいました。事故の例としては、釣りや遊びに来て誤って転落してしまうということが多いそうです。水辺で楽しむ機会が増える夏。溺れている人を見たときの対処法や、ペットボトルに少量の水を入れて投げ入れ、浮き輪代わりにしてもらう救命法などを紹介します。小岩消防署
電話:03-3677-0119HP:http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-koiwa/
2018年7月12日(木)
「心肺停止の応急手当」

 東京消防庁における、平成29年の救急出場件数は約78万5千件と過去最高になっています。特に夏は、熱中症や水の事故などでの救急出場が多くなります。倒れている人が意識を失っている場合、まずは呼吸の有無を確認します。呼吸がなかった場合はまず胸骨圧迫(心臓マッサージ)、そしてAED(自動体外式除細動器)を使用する必要があります。
東京消防庁における、平成29年の救急出場件数は約78万5千件と過去最高になっています。特に夏は、熱中症や水の事故などでの救急出場が多くなります。倒れている人が意識を失っている場合、まずは呼吸の有無を確認します。呼吸がなかった場合はまず胸骨圧迫(心臓マッサージ)、そしてAED(自動体外式除細動器)を使用する必要があります。いざというときに命を救う応急手当を紹介。
東京消防庁本部庁舎
電話:03-3212-2111HP:http://www.tfd.metro.tokyo.jp
2018年7月13日(金)
「レジャーでの火災事故」

 夏の人気レジャー、キャンプやバーベキュー。カセットボンベを使ったコンロの使用については注意が必要です。
夏の人気レジャー、キャンプやバーベキュー。カセットボンベを使ったコンロの使用については注意が必要です。火力が欲しいとコンロを2台並べ、鉄板を覆うように置いて使用してしまうと、コンロに熱がこもってしまい、カセットボンベが熱くなり圧力が上がり破裂して爆発してしまいます。
また、最近家庭での調理でも使われることが増えたガスバーナーや、くん製器の事故例を実験映像を交えて紹介。火を使う場合は、消火器・水の入ったバケツを用意するなどの防火対策、火を使った器具の注意を呼び掛けます。
東京消防庁本部庁舎
電話:03-3212-2111HP:http://www.tfd.metro.tokyo.jp







