 |





|
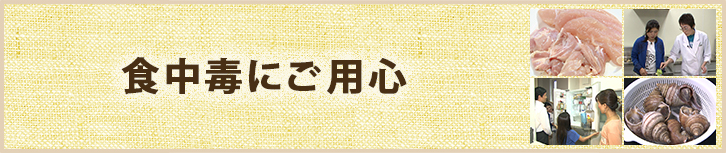
2018年6月25日(月)
「食中毒予防3原則」

 食中毒予防3原則は菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」。手洗いをしっかりし、調理するときは、肉と野菜で包丁やまな板を使い分けて菌を食材につけないようする。購入した食品は保冷し菌を増やさないように、そして肉は中心部が75℃以上で1分以上加熱し、菌をやっつける。
食中毒予防3原則は菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」。手洗いをしっかりし、調理するときは、肉と野菜で包丁やまな板を使い分けて菌を食材につけないようする。購入した食品は保冷し菌を増やさないように、そして肉は中心部が75℃以上で1分以上加熱し、菌をやっつける。買い物では、肉や魚のドリップが他の食品につかないようにポリ袋を二重にして入れ、菌をつけない工夫が必要です。
また冷蔵庫内は詰め過ぎず7割程が目安で、冷気の吹き出し口をふさがないようにしましょう。
2018年6月26日(火)
「鶏肉の食中毒予防」

 去年、全国で2315人がカンピロバクター食中毒になりました。
去年、全国で2315人がカンピロバクター食中毒になりました。カンピロバクターによる食中毒を引き起こす主な食べ物の一つは、生の状態や加熱不足の鶏肉などで、症状は下痢、腹痛、発熱など。カンピロバクターは、元々鶏や牛など家畜の胃腸の中にいて、肉を加工する過程で間違ってついてしまうそうです。更に肉の表面だけでなく中に入り込むこともあるそうです。
カンピロバクターによる食中毒を防ぐには、鶏肉をしっかり加熱すること。鶏肉の中まで白くなるように、中心部を75℃以上で1分以上加熱することで予防することができるといいます。
2018年6月27日(水)
「二次汚染の食中毒予防」

 二次汚染とは、原材料などについていた食中毒の原因菌が、包丁やトング、箸などの調理器具を介して他の食品を汚染してしまうことです。例えば、生肉を焼いたトングや箸で野菜などに触ると、肉の菌が野菜などに付着し食中毒になることがあるといいます。
二次汚染とは、原材料などについていた食中毒の原因菌が、包丁やトング、箸などの調理器具を介して他の食品を汚染してしまうことです。例えば、生肉を焼いたトングや箸で野菜などに触ると、肉の菌が野菜などに付着し食中毒になることがあるといいます。二次汚染を防ぐには、生肉を焼いたトングや箸は野菜などに使いまわさないこと。調理時には食材ごとにまな板や包丁などを変える。または、食材ごとの使用後に洗剤を使って洗い、熱湯をかけて除菌をすると安全に使うことができるそうです。
買い物のときにも注意が必要です。肉や魚のドリップには、食中毒を引き起こす菌が含まれている場合があるので、持ち帰るときは、ポリ袋で二重に包み他の食材に菌がつかないようにしましょう。
2018年6月28日(木)
「魚介類の食中毒予防」

 去年、全国では74人がヒスタミンによる食中毒になっています。
去年、全国では74人がヒスタミンによる食中毒になっています。ヒスタミンによる食中毒の原因食品は、サバやイワシ、ブリ、マグロなど青魚の赤身部分で、症状は顔面や耳たぶが赤くなる、じんましん、下痢、おう吐など。ヒスタミンとは、魚の体内にあるヒスチジンが細菌の働きで合成される化学物質で、体内に入るとアレルギーのような症状をひき起こします。
一度できたヒスタミンは、煮ても焼いても減らないため、増やさないことが大切だといいます。
魚は常温で放置せず、速やかに冷蔵庫で保冷しましょう。また解凍は冷蔵庫の中でなるべく短時間のうちに行い、一度解凍したものは、再度冷凍しないようにしましょう。
貝類では、テトラミンによる食中毒が報告されています。バイ貝の唾液腺には神経毒素のテトラミンが含まれています。これを食べてしまうと、眼のちらつき、頭痛、めまいなど二日酔いに似たような症状を引き起こします。テトラミンは加熱しても分解されないため、調理する前に唾液腺が残っていないか確認し、十分水洗いしましょう。
2018年6月29日(金)
「身近な有毒植物の見分け方」

 2008年から2017年の10年で、全国では818人が有毒植物による食中毒になり、そのうち10人が亡くなっています。
2008年から2017年の10年で、全国では818人が有毒植物による食中毒になり、そのうち10人が亡くなっています。ニラと間違えやすいスイセンは、食べるとおう吐や下痢などを引き起こします。見分けるポイントは、臭い!ニラは特有のニラの臭いがしますが、スイセンに臭いはとくにありません。
オクラとよく似たアメリカチョウセンアサガオのつぼみは、食べるとおう吐やけいれん、意識障害などを引き起こすことがあります。
ジャガイモは、発芽部分や皮が緑色になった部分は有毒で、食べるとおう吐、下痢、腹痛、頭痛、めまいなどを引き起こします。調理の際は、皮を厚めにむき、特に発芽部分は完全に除去するなど十分な注意が必要です。
またアジサイの葉は、食べるとおう吐やめまい、顔面紅潮を引き起こします。
有毒植物か食用の植物かもし迷ったら、絶対に採らない、食べない、人にあげないようにしましょう。
東京都薬用植物園
住所:東京都小平市中島町21-1電話:042-341-0344
開園時間:午前9時〜午後4時30分(10〜3月は午後4時まで)
休園日:月曜(祝日の場合は翌日、4・5月とイベント開催日は開園)、12月29日〜1月3日
入園料:無料
HP:http://www.tokyo-eiken.go.jp/lb_iyaku/plant/
■東京都健康安全研究センター
電話:03-3363-3231
HP:http://www.tokyo-eiken.go.jp







