 |





|
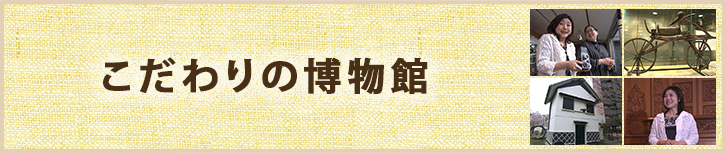
2018�N4��9��(��)
�u�����L�O�فv

 �O�c�@�����L�O�ق͋c������`�ɂ��Ĉ�ʂւ̔F�����L�߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��������قō���̑g�D��^�c�Ȃǂ�������f���ɂ���Ă킩��₷���Љ�Ă��܂��B
�O�c�@�����L�O�ق͋c������`�ɂ��Ĉ�ʂւ̔F�����L�߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��������قō���̑g�D��^�c�Ȃǂ�������f���ɂ���Ă킩��₷���Љ�Ă��܂��B�c��̌��R�[�i�[�͏O�c�@�c���̌����邱�Ƃ��ł��܂��B���ۂ�4����3�̑傫���ō���Ă��܂��B�g�p����Ă����c���Ȃɂ����邱�Ƃ��ł��A���ɂ͋L�����[�Ŏg���؎D�i���[���^���[�A�[�����Ε[�j���u����Ă��܂��B
����̑��L�R�[�i�[�ł͕��i�ڂɂ��邱�Ƃ��Ȃ����L���������邱�Ƃ��ł��܂��B
���胁�����A���z�[���͑�1��O�c�@���I������60�N�ȏ�c���߁A�쌛�^���╁�ʑI���^�����N�����A�����̐_�l�ƌĂꂽ����s�Y�Ɋ֘A���鎑����W�����Ă��܂��B1928�i���a3�j�N�ɘ^�����ꂽ����s�Y�̉������������Ƃ��ł��܂��B
�O�c�@�����L�O��
�Z���F�����s���c��i�c��1-1-1�d�b�F03-3581-1651
�J�َ��ԁF�ߑO9��30���`�ߌ�5��
�����ق͌ߌ�4��30���܂�
�x�ٓ��F��������
���ٖ���
HP�Fhttp://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kensei/kensei.htm
2018�N4��10��(��)
�u���{�J���������فv

 ���{�J���������ق͍����O�̖��@�Ⓙ�����J�����Ȃǂ�500��ȏ�A�W�����Ă��܂��B�`�F���[���Ô���1903�i����36�j�N�ɁA���{�ōŏ��ɗʎY�A�s�̂��ꂽ�J�����ł��B���̃J�����ɂ���Ĉ�ʂ̐l���J��������ɂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
���{�J���������ق͍����O�̖��@�Ⓙ�����J�����Ȃǂ�500��ȏ�A�W�����Ă��܂��B�`�F���[���Ô���1903�i����36�j�N�ɁA���{�ōŏ��ɗʎY�A�s�̂��ꂽ�J�����ł��B���̃J�����ɂ���Ĉ�ʂ̐l���J��������ɂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B���㎮�����ʐ^�e����͋@�֏e�^�̎ˌ��P���p�̃J�����ŁA�e�̈������̂悤�Ɉ����ĎB�e���܂��B
�P���ŎB�����ʐ^�̒��S�ɖڕW��������Ύˌ��̘r���オ���Ă��邱�ƂɂȂ邻���ł��B
�J�����ɐG���R�[�i�[�ł̓����Y��2������t�J�����̃��R�[�t���b�N�X�Z��̌����܂����B
1986�i���a61�j�N�ɔ������ꂽ�t�W�J���[�ʃ����ł��A�͐��E���̃����Y�t���t�B������2014�N�ɍ����Ȋw�����ق̏d�v�Ȋw�Z�p�j�����ɓo�^����Ă��܂��B
���ʓW�ł͖������ɐ��E�e���ō��ꂽ�J������W�����Ă��܂��B1909�N�A�A�����J�Ŕ̔����ꂽ�T�[�J�b�g�̓[���}�C�d�|���ʼn�]���邱�ƂŁA�p�m���}�ʐ^���B�e���邱�Ƃ��ł��A�T�[�J�b�g�ŎB��ꂽ��㖜���̎ʐ^���W�����Ă��܂��B
���{�J����������
�Z���F�����s���c���Ԓ�25�ԒnJCII��Ԓ��r���n��1�K�d�b�F03-3263-7110
�J�َ��ԁF�ߑO10���`�ߌ�5��
�x�ٓ��F���j���i�j���̏ꍇ�͗����j
���ٗ��F300�~
HP�Fhttp://www.jcii-cameramuseum.jp
���ʓW�@�u����150�N �J�����̖閾���v
6��24���i���j�܂�
2018�N4��11��(��)
�u�����Ŋցw���Ђ�x�v

 �����Ŋցw���Ђ�x�͐Ŋւ̖�����Ɩ���m�邱�Ƃ��ł��锎���قŁA�Ŋւ̐��藧����d���̓��e�ɂ��Ă̓W��������Ă��܂��B
�����Ŋցw���Ђ�x�͐Ŋւ̖�����Ɩ���m�邱�Ƃ��ł��锎���قŁA�Ŋւ̐��藧����d���̓��e�ɂ��Ă̓W��������Ă��܂��B�����Ŋւ͓����A��ʁA�Q�n�A�R���A�R�`�A�V���Ɛ�t�̈ꕔ���NJ����Ă��܂��B
�W�����͓����Ŋ֊NJ����Ŏ��ۂɍ����~�߂�ꂽ���̂��W������Ă��܂��B��ł̋��ꂪ����쐶���A����ی삷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��č��ێ�����K�����郏�V���g�����̋K���Ώۂ̂͂������v���i�Ȃǂ�W�����Ă��܂��B�W���R�E�i�l���j�A�R�R�c�i�Ս��j�A���E�^���i�F�_�j�Ȃǂ��܂܂ꂽ��������A�����֎~����Ă��܂��B
���̑��A�s���̖��A���̗l�X�Ȏ�����Љ��R�[�i�[������A�T�[�t�{�[�h�̕\�ʂ��͂����Ē������蔲���������r�[�`�T���_���̌C��������Ē��ɓ��ꂽ����Ȃǂ�W�����Ă��܂��B
����ɁA�X�[�p�[�R�s�[�ƌĂ��{����������ɍ��ꂽ�u�����h�i�̋U�����{���ƕ��ׂēW������Ă��܂��B�Ŋւ̓��[�J�[����^��̃|�C���g���A����Ɋ�Â��Č������Ă��邻���ł��B
�����Ŋցw���Ђ�x
�Z���F�����s�]����C2-7-11�d�b�F03-3599-6264�i�����ŊŊ֍L��L�����j
�J�َ��ԁF�ߑO9���`�ߌ�5��
�x�ٓ��F�y�E���j�A�j��
���ٖ���
HP�Fhttp://www.customs.go.jp/tokyo/jroom/jroom1.htm
2018�N4��12��(��)
�u���]�ԕ����Z���^�[�v

 ���]�ԕ����Z���^�[�͎��]�Ԃ��a�����Ă��猻��܂ŁA�Љ�Ƃǂ̂悤�Ɋւ�蔭�B���Ă��������Љ�Ă��܂��B
���]�ԕ����Z���^�[�͎��]�Ԃ��a�����Ă��猻��܂ŁA�Љ�Ƃǂ̂悤�Ɋւ�蔭�B���Ă��������Љ�Ă��܂��B201�N�O�Ƀh�C�c�ō��ꂽ���E�ŏ��̎��]�Ԃ́A�y�_�����������Œn�ʂ��R���đ����Ă��܂����B1861�N�Ƀt�����X�őO�ւɃy�_����t�����~�V���[���a���B�X�s�[�h���o��悤�ɂȂ背�[�X��T�C�N�����O���s����悤�ɂȂ�܂����B�i�|���I��3�����T�C�N�����O�ɏo�����������ł��B
���̌�A�C�M���X�ő�����Njy���O�ւ�傫�������I�[�f�B�i���[���ł��A1885�N�Ƀ`�F�[���Ō�ւ��Z�[�t�e�B���a�����܂����B���̎��]�Ԃ͊ȒP�ɂ܂����邽�߈�ʂɊg����܂����B
���{�̎��]�Ԃ́A���������A�O���l�������Ă������]�Ԃ𓁐E�l�Ȃǂ����悤���܂˂ō�������̂��n�܂�Ƃ���Ă��܂��B
���̌���{�ł́A���]�Ԃ͉^���̂��߂ɔ��W��������������吳�����ɐD���Ǝ҂Ȃǂ����p�����ב�O�֎Ԃ�A�T�C�h�J�[�t�����]�Ԃ����܂�܂����B
���a20�N��㔼�ɂ͉ב䂪�傫���^�C���̑����g�卑���h���o�ꂵ�܂����B�d���ו����ڂ����܂܃X�^���h���グ�����ł���悤�ɍH�v����Ă��܂��B
���݁A���{�̉ו��^���p���]�Ԃ̊��W���J�Ò��ł��B
���]�ԕ����Z���^�[
�Z���F�����s�i������3-3-1�d�b�F03-4334-7953
�J�َ��ԁF�ߑO9��30���`�ߌ�5��
���ŏI���ق͌ߌ�4��45���܂�
�x�ٓ��F���j�i�j���̏ꍇ�͗����j
���ٖ���
HP�Fhttp://www.cycle-info.bpaj.or.jp
�u���p���]�Ԃ̗��j�W�v�@7��1���i���j�܂�
2018�N4��13��(��)
�u���O���̊فv

 ����23����ŗB����ۂɎg���Ă��鉺���������Ȃ���A���̋Z�p����j���w�Ԃ��Ƃ��ł��鑠�O���̊فB
����23����ŗB����ۂɎg���Ă��鉺���������Ȃ���A���̋Z�p����j���w�Ԃ��Ƃ��ł��鑠�O���̊فB�n��3�K�W�����Ō��w�ł���������́A�n��30m�قǂ̐[���ɂ���A���a6.25m�A����5.8km�̋���ȉ������ǂł��B�䓌�悩�當����ɂ����ĕ~�݂���Ă���A�������������Ƃ��ĉJ���Ɖ��������ꂱ��ł��܂��B���̉����͑��O�|���v�����o�āA�O�͓����Đ��Z���^�[�ŏ�A���c��ɕ�������܂��B�܂��A�������́A�Z����̖������S���Ă��܂��B
�n��̉�����������ɗ��������̉������ǁu�点��ē��H���h���b�v�V���t�g�v�ɂ́A�����������V�X�e���Ƃ����H�v���{����Ă��܂��B�点���̐��̗���ŗ������鉺���̏Ռ��E�����E�L�C��h���d�g�݂ł��B
�n��1�K�W�����ł́A�J���[�����O���ꂽ�A�s�^�E�W���}���z�[���W�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�s�̉ԃ\���C���V�m�A�s�̖C�`���E�A�s���̒������J�������f�U�C������Ă��܂��B
���O���̊�
�Z���F�����s�䓌�摠�O2-1-8�@�k���������������~�n���d�b�F03-3241-0944
�J�َ��ԁF�ߑO9���`�ߌ�4��30��
�x�ٓ��F�y�E���j�A�j��
���w�����A�v�\��i1�T�ԑO�܂Łj
���������͓V��ɂ�茩�w�ł��Ȃ��ꍇ������܂�
HP�Fhttp://www.gesui.metro.tokyo.jp/living/tour/guide/s-kuramae/index.html
�@







