 |





|
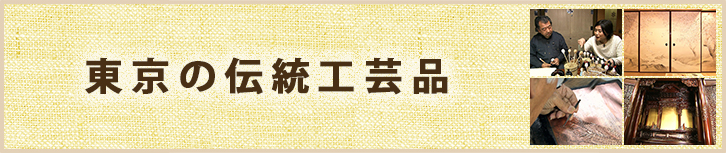
2017年1月16日(月)
「江戸衣裳着人形」
 わらなどの胴体に顔や手足をつけて衣装を着せた、江戸衣裳着人形(えどいしょうぎにんぎょう)は経済産業大臣指定伝統的工芸品であり、東京都指定伝統工芸品。江戸衣裳着人形製作40年の人形師、菊地之夫さんは日本の伝統工芸士と東京都伝統工芸士に認定されています。
わらなどの胴体に顔や手足をつけて衣装を着せた、江戸衣裳着人形(えどいしょうぎにんぎょう)は経済産業大臣指定伝統的工芸品であり、東京都指定伝統工芸品。江戸衣裳着人形製作40年の人形師、菊地之夫さんは日本の伝統工芸士と東京都伝統工芸士に認定されています。100を超える工程により製作される、江戸衣裳着人形のポイントは顔作り。主に義眼と呼ばれるガラスの目玉を入れてからご粉を塗り重ね、目を切り出して表情を作ります。
松菊
住所:東京都葛飾区青戸3-41-3電話:03-3602-1452
営業時間:午前10時〜午後6時
HP:http://www.ichimatsu.com
2017年1月17日(火)
「村山大島紬」
 江戸後期からの綿織物、村山紺絣(むらやまこんがすり)がルーツの村山大島紬(むらやまおおしまつむぎ)は、経済産業大臣指定伝統的工芸品であり東京都指定伝統工芸品。村山大島紬製作49年の田代隆久さんは、日本の伝統工芸士と東京都伝統工芸士に認定されています。
江戸後期からの綿織物、村山紺絣(むらやまこんがすり)がルーツの村山大島紬(むらやまおおしまつむぎ)は、経済産業大臣指定伝統的工芸品であり東京都指定伝統工芸品。村山大島紬製作49年の田代隆久さんは、日本の伝統工芸士と東京都伝統工芸士に認定されています。村山大島紬最大の特徴が、溝を彫った板に糸を挟んで文様を染める板締め染色。1枚の反物を作るのにたて糸用の板が47枚、よこ糸は中柄の場合、50枚ほどの板を使います。
田房染織
住所:東京都武蔵村山市三ツ木2-46-1電話:042-560-0116
HP:http://tahusa-dyeingweaving.tumblr.com
2017年1月18日(水)
「江戸からかみ」
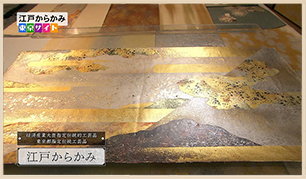 江戸の町人文化とともに発展した、ふすまやびょうぶなどに貼る装飾された和紙、江戸からかみは経済産業大臣指定伝統的工芸品であり、東京都指定伝統工芸品。木版手摺り(もくはんてずり)、渋型捺染手摺り(しぶがたなっせんてずり)、金銀箔砂子手蒔き(きんぎんはくすなごてまき)の3技法があります。
江戸の町人文化とともに発展した、ふすまやびょうぶなどに貼る装飾された和紙、江戸からかみは経済産業大臣指定伝統的工芸品であり、東京都指定伝統工芸品。木版手摺り(もくはんてずり)、渋型捺染手摺り(しぶがたなっせんてずり)、金銀箔砂子手蒔き(きんぎんはくすなごてまき)の3技法があります。日本の伝統工芸士に認定される砂子師の秋田英男さんは、金ぱくの輝きを保ちつつ、金泥の柔らかさを表現できるのが砂子の特長と語ります。
東京松屋
住所:東京都台東区東上野6-1-3電話:03-3842-3785
営業時間:午前9時〜午後5時
定休日:日曜、祝日
HP:http://www.tokyomatsuya.co.jp
2017年1月19日(木)
「東京彫金」
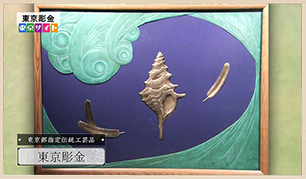 将軍家や大名家の正装に用いられた“家彫”に対して、江戸の町人に愛された“町彫”をルーツとする東京彫金は、東京都指定伝統工芸品。東京彫金製作62年の中島一華さんは、東京都伝統工芸士に認定されています。
将軍家や大名家の正装に用いられた“家彫”に対して、江戸の町人に愛された“町彫”をルーツとする東京彫金は、東京都指定伝統工芸品。東京彫金製作62年の中島一華さんは、東京都伝統工芸士に認定されています。東京彫金の技法は金属を裏からたたいて立体的に仕上げる打ち出しと、金属面に絵を描いてたがねで彫る片切彫りの2種類。片切彫りはたがねを打つ金づちの力加減が大切で、呼吸を止めて一定のリズムで打ちこみます。
中島彫金工房
電話:03-3997-0718
2017年1月20日(金)
「東京仏壇」
 黒たんや紫たんなど堅くて高級な木材を使用し、比較的装飾の少ない東京仏壇は、東京都指定伝統工芸品。東京仏壇製作48年の岩田芳樹さんは、東京都伝統工芸士に認定されています。
黒たんや紫たんなど堅くて高級な木材を使用し、比較的装飾の少ない東京仏壇は、東京都指定伝統工芸品。東京仏壇製作48年の岩田芳樹さんは、東京都伝統工芸士に認定されています。製作工程で一番重要なのは、手押しかんな盤による平面出し。平らに削って密着性を高めた面を接着剤で接合し、目地はかんなで払います。江戸指物の流れをくむ東京仏壇は、引き出しなどに気密性が表れ、作れるようになるまで10年かかるそうです。
岩田仏壇製作所
住所:埼玉県川口市前川2-32-3電話:048-269-3500
東京唐木仏壇工業協同組合
電話:03-3620-1201
■経済産業大臣指定伝統的工芸品・日本の伝統工芸士
電話:03-5785-1001(伝統的工芸品産業振興協会)
HP:http://kougeihin.jp
HP:http://www.kougeishi.jp
■東京都指定伝統工芸品・東京都伝統工芸士
電話:03-5320-4659(東京都産業労働局商工部経営支援課)
HP:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/dentokogei/japanese/
HP:http://www.dentoukougei.jp
■第60回東京都伝統工芸品展
電話:03-5320-4659(東京都産業労働局商工部経営支援課)
開催日時:1月19〜24日 午前10時〜午後8時(20・21日は午後8時30分、24日は午後6時まで)
会場:新宿高島屋11階 催会場
HP:http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/14/11.html







