 |





|
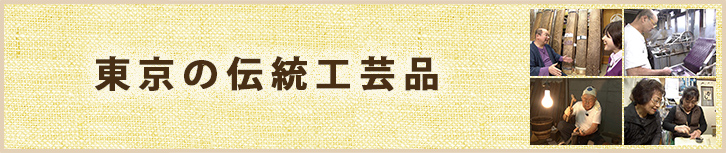
2016年1月4日(月)
「東京琴」
 江戸後期に京都の生田琴を改良し、山田琴が誕生したのがその始まりの東京琴。東京都伝統工芸品に指定されています。京間の畳のサイズと同じ6尺2寸の生田琴に対して、山田琴は江戸間の畳に合わせた6尺で、丸みと反りが少ないのが特徴です。
江戸後期に京都の生田琴を改良し、山田琴が誕生したのがその始まりの東京琴。東京都伝統工芸品に指定されています。京間の畳のサイズと同じ6尺2寸の生田琴に対して、山田琴は江戸間の畳に合わせた6尺で、丸みと反りが少ないのが特徴です。東京琴製作35年の職人、金子政弘さんは会津桐にこだわって琴を製作。丸太で購入し、約10年かけて琴に仕上げます。金子さんの作った東京琴は、柔らかい音色と余韻が特長です。
かねこ琴三絃楽器店
住所:東京都大田区千鳥3-18-3電話:03-3759-0557
営業時間:午前10時〜午後8時頃
HP:http://www.kanekogakki.jp
2016年1月5日(火)
「東京無地染」
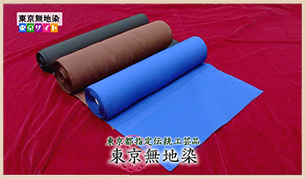 江戸紫や江戸茶、深川鼠(ねずみ)など、江戸庶民に愛用された無地染めがルーツの東京無地染。東京都伝統工芸品に指定されています。
江戸紫や江戸茶、深川鼠(ねずみ)など、江戸庶民に愛用された無地染めがルーツの東京無地染。東京都伝統工芸品に指定されています。東京無地染40年の職人、近藤良治さんは東京都伝統工芸士。赤、黄、青、紫、黒の5色の染料を配合し、あらゆる色を作り出します。染めに使うのは、80℃のお湯につけて生糸に含まれる不純物を取り除いた白生地の反物。染色しては色見本と合わせて足りない染料を足し、4〜5回繰り返して染め上げます。
近藤染工
住所:東京都江東区清澄2-15-3電話:03-3641-2135
HP:http://www.tokyo-senshoku.com/partner/member/kondo/kondosenko.html
2016年1月6日(水)
「東京打刃物」
 明治9年の廃刀令で、ほとんどの刀鍛冶(かじ)が業務用や家庭用の刃物造りに転向して誕生した東京打刃物。東京都伝統工芸品に指定されています。
明治9年の廃刀令で、ほとんどの刀鍛冶(かじ)が業務用や家庭用の刃物造りに転向して誕生した東京打刃物。東京都伝統工芸品に指定されています。東京打刃物製作50年の職人、大河原享幸さんは東京都伝統工芸士。鉄の板から金づち1本で、はさみをたたき出します。指を入れる輪の部分は、鳥口と呼ばれる特殊な台座で成形。刃の部分は、次男の康宏さんとの相づちで鋼を接合。1本のはさみをたたき出すのに要する時間は、わずか30分です。
和弘利器
住所:東京都葛飾区金町1-10-8電話:03-3607-0833
HP:http://www.hasami.tv
2016年1月7日(木)
「東京手植ブラシ」
 明治7年頃にフランス製ブラシを手本に作られ始め、明治10年の第1回内国勧業博覧会で好評を博した東京手植ブラシ。東京都伝統工芸品に指定されています。
明治7年頃にフランス製ブラシを手本に作られ始め、明治10年の第1回内国勧業博覧会で好評を博した東京手植ブラシ。東京都伝統工芸品に指定されています。父親から技術を受け継いで約60年の宇野千榮子さんは、次女の三千代さんとともに東京手植ブラシの職人。製品によって密度を変えて開けられた一穴一穴に、1本のステンレス線を切らずに連続して通して毛材を手植えしていくため、抜けずに長持ちするそうです。
宇野刷毛ブラシ製作所
住所:東京都墨田区向島3-1-5電話:03-3622-9078
2016年1月8日(金)
「多摩織」
 八王子は古くから養蚕と織物業が盛んで、様々な織物が織られてきました。その基本形となるのが多摩織。日本の伝統的工芸品であり東京都伝統工芸品です。
八王子は古くから養蚕と織物業が盛んで、様々な織物が織られてきました。その基本形となるのが多摩織。日本の伝統的工芸品であり東京都伝統工芸品です。多摩織はよこ糸に節のある紬織(つむぎおり)、強いよりをかけたお召織、薄いレース状の捩り織(もじりおり)、リバーシブル構造の風通織、しなやかさと張りを併せ持つ変り綴(つづれ)の総称。多摩織67年の職人で伝統工芸士の吉水壯吉さんは、後継者の育成にも力を入れています。
八王子織物工業組合
住所:東京都八王子市八幡町11-2電話:042-624-8800
HP:http://www.hachioji-orimono.jp
経済産業大臣指定伝統的工芸品・伝統工芸士
電話:03-5785-1001(伝統的工芸品産業振興協会)HP:http://kougeihin.jp
東京都伝統工芸品・東京都伝統工芸士
電話:03-5320-4659(東京都産業労働局商工部経営支援課)
HP:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/dentokogei/japanese/
HP:http://www.dentoukougei.jp
江戸から伝わる一筋の道 第59回東京都伝統工芸品展
電話:03-5320-4659(東京都産業労働局商工部経営支援課)
開催日時:1月13〜18日 午前10時〜午後8時(15・16日は午後8時30分、18日は午後6時まで)
会場:新宿高島屋 11階催会場
HP:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/dentokogei/japanese/event/calendar/calendar-2801.html







