 |
     |
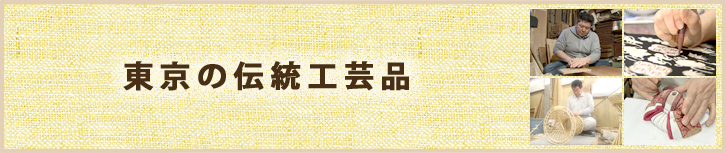
2014年1月6日(月)
江戸筆
 今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。
今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。東京都伝統工芸品に指定される江戸筆は、江戸時代中期に商人の台頭や寺子屋の急増などにより庶民の間で普及しました。
関西では筆先の半分ほどを崩すのに対し、江戸筆は根元まで崩して墨を付けるので、はねや払いをきれいに書くことが出来ると言います。筆の用途や使う人の技術によって、毛先が柔らかくまとまりやすい中国産の山羊毛や硬くてこしのある馬毛など、使う毛の種類や配合を変えるそうです。
筆工房 亀井
住所:東京都練馬区石神井町5-14-2電話:03-3996-5046
HP:http://www.edofude.co.jp/
2014年1月7日(火)
江戸指物
 今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。
今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。東京都伝統工芸品に指定される江戸指物は、ケヤキや桐など木目の美しい材料を生かし、金釘などを使わずに組み立て、漆塗りを施すのが特徴。木材の端に“ほぞ”と呼ばれる突起を作って組み合わせ、接合部は表から見えません。
指物作りで重要なのが道具の手入れだと言います。中でも作業台の“あて台”は削った板が平らかどうかを確認する物差しでもあり、あて台の調整は基本となるものです。
井上木芸
住所:東京都荒川区東日暮里4-18-5電話:03-3807-3426
2014年1月8日(水)
東京手描友禅
 今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。
今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。東京都伝統工芸品に指定される東京手描友禅は、江戸時代の中頃に京都から江戸に染師が移り住んだことで友禅の技法が伝わり、町民文化とともに発展してきました。
京友禅の高度に様式化された文様や、加賀友禅の加賀五彩と呼ばれる基本となる色調に対し、東京手描友禅は題材や色調が自由なのが特徴。フリーハンドで細やかに手描きされた東京手描友禅は、江戸の粋を現代に伝えています。
アトリエ小倉染芸
住所:東京都新宿区高田馬場3-25-8電話:03-3361-2366
HP:http://ogurasengei.com/
2014年1月9日(木)
東京籐工芸
 今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。
今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。東京都伝統工芸品に指定される東京籐工芸は、江戸時代後期から生活用品として普及し始め、明治期以降はいすやかごなどの人気が高まりました。
籐はインドネシアなど熱帯地方に生えるヤシ科の植物で、軽くて弾力性に優れ、中に繊維が詰まっていてとても丈夫なのが特徴。いすの座面などに適した “目積編み”や“四つ目編み”、“あじろ編み”など製品やパーツによって様々な編み方を使い分けます。
木内籐材工業
住所:東京都文京区千石4-40-24電話:03-3941-4484
HP:http://www.kiuchi-tohzai.co.jp/
2014年1月10日(金)
江戸木目込人形
 今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。
今週のテーマは『東京の伝統工芸品』。東京都伝統工芸品に指定される江戸木目込人形の原点は、約270年前に京都の上賀茂神社で作られていた賀茂人形だと言われています。木目込人形とは胴体に溝を彫って布の端を押し込み、衣装を着ているように仕立てた人形で、江戸時代の中頃に京都から江戸に伝わりました。
一般的な雛人形はわらで作った胴体に綿で肉付けしますが、木目込人形は胴体を型で作るので、自由な動きをつけることが出来ます。
柿沼人形
住所:埼玉県越谷市七左町2-174-4電話:048-964-7877
HP:http://www.kakinuma-ningyo.com/
〜江戸から伝わる一筋の道〜第57回東京都伝統工芸品展
Made in Tokyoのプライドと伝統と〜染め、描き、彫り、磨く 匠の技〜
開催日時:1月24日(金)〜29日(水) 午前10時〜午後8時(24・25日は午後8時半まで、29日は午後6時まで)
会場:髙島屋新宿店11階催会場
東京都産業労働局
電話:03-5320-4783







