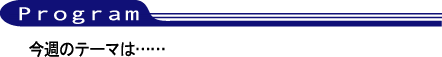
![]()
| 2006年 7月31日(月) 放送分 |
|
|
||||
|
夏場は気温や湿度が上昇し、菌が増えやすくなるため食中毒が多く発生します。しかし、食中毒になっても自分では判断が難しく、自己判断で対処した結果、重症になってしまうケースもあるようです。そこで、食中毒の症状と対処法をご紹介します。
|
||||
| 2006年 8月1日(火) 放送分 |
|
|
||||
| 生鮮食品やキッチンには食中毒を起こす菌以外にも多くの菌がいます。そこで、ごく普通のお宅のキッチンにどのくらいの菌が繁殖をしているのか、拭き取り調査を行いました。そして、食中毒にならないための三原則をご紹介します。
|
||||
2006年 8月2日(水) 放送分 |
|
|
||||
夏場、時間が経って食べるお弁当などでは食中毒が発生しやすくなります。そこで、お弁当を作る際に気をつけたいポイントや、家庭で食中毒を未然に防ぐ簡単な方法をご紹介します。
|
||||
|
2006年 8月3日(木) 放送分
|
|
|
||||
| 東京都では飲食店や、食品を取り扱う業者が衛生管理を積極的に行っていることを、我々消費者が目で見て分かるように「食品衛生自主管理認証制度」を設けました。月に一度、この制度に関するセミナーも行われています。
食品衛生自主管理認証制度についてはこちら! http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/anzen/sonota/nin_shou/index.html |
||||
|
2006年 8月4日(金) 放送分 |
|
|
||||
|
「食品衛生自主管理認証制度」で認証された店舗では、実際にどんな取り組みを行っているのか、そして、この制度の認証を取得しようときっかけなどを、実際に認証を取得した飲食店でお聞きしました。
食品衛生自主管理認証制度についてはこちら! http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/anzen/sonota/nin_shou/index.html |
||||
Copyright(C) tv asahi All Rights Reserved