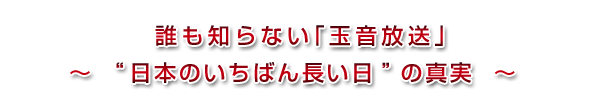
■アメリカ取材後記
 日本に和平を呼びかける放送を行った
日本に和平を呼びかける放送を行ったエリス・ザカライアス海軍大佐
昭和天皇とザカライアス放送
「これは、父がもらった昭和天皇の結婚披露宴の招待状」です。ジェラルド氏の言葉を聞いた時、「やった!」と思った。ジェラルド氏は、戦時中に日本へ和平を呼びかけるラジオ放送を行っていたザカライアス米海軍大佐の次男。当時の放送原稿や写真などを大切に保管していた。そんな資料の数々を見せてもらっているうちに、ザカライアスが日本のアメリカ大使館に勤務していた時にもらったという「昭和天皇の結婚披露宴への招待状」が出てきたのだ。結論を言えば、それは別の皇族のものだったが我々は失望することはなかった。山のような皇室行事への招待状や1928年に昭和天皇が「即位の礼」を行った時のアルバム、さらには昭和天皇の弟、高松宮との親交を示すプレゼント類など、ザカライアスと昭和天皇の関係を示す数々の“証拠”が出てきたからだ。
今回の番組は、昭和天皇とラジオを主役に終戦に至るドラマを描くというねらいでスタートした。ザカライアス放送は、そうした中で浮上したひとつの要素だ。1945年5月から、ザカライアスは日本に対し、ストレートに和平を訴えかけてきた。幾分たどたどしい日本語で「私は常に日本人に好意をもって、朋友として交際し…」といった具合である。それは謀略放送がほとんどだったアメリカの対日ラジオ放送の中で異色の存在だった。しかも、戦後に発表した著書の中で「放送のターゲットは、降伏を唯一決断できる天皇だった」と記している…。
しかし取材を始めた時点では、ザカライアスと天皇を結びつける糸は決して太くはなかった。高松宮が新婚旅行で訪米した際のエスコート役をザカライアスが務めたという情報しかない。なぜザカライアスは天皇をターゲットにしたのか?著書に書かれた理屈ではなく、実感できる何かが欲しかった。そうした中で出会ったのが、ジェラルド氏が出してくれた“証拠”だった。
ザカライアスが残した皇室からの招待状やアルバムは、大正末期から昭和初期にかけてのもの。もう90年近く前のものだ。もちろん皇室の行事に参加したからといって、ザカライアスが天皇と言葉を交わすことはなかっただろう。だが、異国の冷静な目で天皇をじっと見つめるザカライアスの姿がそこからイメージできた。
日米は「降伏を決断できるのは天皇だけだった」という点で一致していた
番組における最大の課題は、天皇が終戦に果たした役割を浮かび上がらせることだった。もし日本国内の動きを追いかけるだけだと、それは難しかったと思う。アメリカ側も「天皇しか降伏を決断できる人間はいない」と考えていた事実を明らかにすることで初めて天皇の存在感が増してきた。ザカライアス放送に加え、2003年に「ザ・スクープ」で取材した広島原爆投下部隊のポール・ティベッツのインタビューがその事実を裏付けてくれた。
あの時、終戦を決断できる人間は世界にたった1人しかいなかった。それは日米共通の認識だったのだ。そして、終戦当時44歳だった天皇にかかるプレッシャーとは、どれだけ凄まじいものだったのかーそんなことに思いを馳せながら御前会議の再現場面を撮影した。
玉音放送は世界に向けたメッセージ
玉音放送は英訳され、ラジオトウキョウから放送された。この事実は新鮮だった。それまで玉音放送とは日本国民に終戦を知らせるためのものだと思い込んでいたからだ。実はそれは世界に向けたメッセージでもあったのだ。詔書の作成が困難を極めたのも、原爆の投下に言及したのも、世界を意識したからだと思う。
担当ディレクター 島 岳志
■元近衛兵取材後記
 昭和天皇と近衛兵
昭和天皇と近衛兵「軍隊当時の戦友が亡くなって葬儀に行くと、音楽を流して軍歌を歌うんですよ。」
昭和20年8月15日未明に起きた、玉音盤を巡るクーデター。いわゆる「宮城事件」。
終戦を受け入れられない陸軍の青年将校があくまでも本土決戦に持ち込むため、皇居を守る近衛兵を偽の命令で動かし、玉音盤を奪取。天皇に聖断を変更してもらおうと目論んだこの事件。
結局、玉音盤は見つからず、クーデターは未遂に終わった。しかしこの事件は後年、ある人たちに大きな傷を残した。
それは他でもない事件の当事者である、近衛兵だ。
日本全国から選抜された陸軍の精鋭であり、天皇を守護するという誇り高い志を持った近衛兵にとって、例え偽の命令だったとはいえ、クーデターの片棒を担がされた事で、近衛兵の名誉は大きく傷つけられたという。
宮城事件に関わった元近衛兵を取材する中で、ほとんどの方々が口をそろえ語ってくれた。
「我々は騙されのだ。軍隊は命令を受ければ、それに従うしかない」と。
そんな中、意外な言葉を漏らす、元近衛兵もいた。
近衛歩兵第二連隊の第三中隊の上等兵だった和久田正男さん。和久田さんの朝は、大正天皇の写真に拝礼する事から始まる。大正12年生まれの和久田さんにとって、大正天皇は特別な存在なのだという。
和久田さんは、昭和20年8月15日の未明、近衛師団長を反乱軍が銃殺した際の銃声を耳にしている。
ご自宅での取材時、和久田さんは近衛兵時代の思い出の品々を見せてくれた。軍帽や防寒外套、出征時に地域の方々が寄せ書きをしてくれたという日の丸の国旗や、和久田さん自身の「遺髪」も大事に保管されていた。
和久田さんは、とても印象に残ることを語ってくれた。
それは、近衛兵を騙し、偽の命令を出した反乱軍の気持ちも理解できる、というものだった。
「当事、日本国民として当然考えることですよ。無条件降伏をしたら日本国がどうなってしまうのか、天皇制が無くなってしまうのではないか。彼ら反乱軍の気持ちは、純粋なもので、日本人としての伝統的な日本精神だと思う。」
「天皇陛下を守る」事が、唯一にして最大の任務だった近衛兵にとって、無条件降伏を受け入れては「国体の存続」ができないと考えクーデターを起こした反乱軍の心情は、重なるところがあったのだと思う。
戦後何十年が過ぎても近衛兵同士の絆は深くて厚い。和久田さんが所属していた近衛歩兵第二連隊。そのメンバーが集まり、戦後に結成された近歩二会。毎年1月23日に行われる軍旗祭には多くの近歩二会のメンバーが集まり、旧交を温めていた。北は北海道から南は鹿児島まで。
「軍隊当時の戦友が亡くなって葬儀に行くと、音楽を流して軍歌を歌うんですよ。
今日こうして戦争がなく、平和の中で暮らしているのはありがたいことですが、戦友というのは良いものですよ。命を共にした連中ですからね。」
微笑を浮かべつつ、涙を流しながら語ってくれた和久田正男さんの表情がとても印象に残っている。
選抜されるだけで、家族はもとより、地域の人々までもがお祝いし、送り出してくれたという程に名誉な部隊だった近衛兵。
一方で反乱軍という汚名を着せられた事で、逆に近衛兵内部の結束は高まったという側面もあるように思えた。
元近衛兵の方々の絆は、歴史に翻弄される中で生まれたものだったのかもしれない。
担当ディレクター 中村洋三