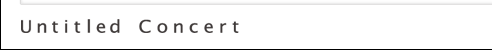1797年作曲。この第2楽章は、神聖ローマ皇帝フランツ2世に捧げた「神よ、皇帝フランツを守り給え」の変奏曲です。そもそも「神よ〜」を作曲した経緯は、ハイドンが約30年勤めたエステルハージ家の楽団長を解雇された後、イギリスに渡りますが、そこで国王を讃える国歌の存在を知り、オーストリアにも同様の曲が必要と強く感じ、作曲しました。その後、この弦楽四重奏の第2楽章にもメロディーが取り上げられたため、タイトルが「皇帝」となっています。現在この曲はドイツ国歌となっています。
1790年作曲。第1ヴァイオリンが高音域でひばりの旋律を奏でます。この作品は、まだ第1ヴァイオリンがメロディを担当し、他の楽器が伴奏する、というスタイルで書かれています。これは当時の演奏家が第1バイオリン以外あまり上手くなかったという、演奏家事情を反映させてのことだったようです。
ベートーヴェンは生涯で全17曲の弦楽四重奏曲を作曲しましたが、いずれも各時期の特徴をよく示す作品として、ベートーヴェンを語る上ではずせないジャンルです。
1805年頃、ベートーヴェンはラズモフスキー伯爵からの依頼を受け、1806年に「ラズモフスキー弦楽四重奏曲」を3曲作曲しました。その3番目の作品がこちらで、3曲中最も明るく力強い作品です。特に今回演奏された第3番第4楽章は、当時のベートーヴェンの構成力を最高度に示したものとして有名で、「英雄四重奏曲」とも呼ばれています。
作曲 : L.v.ベートーヴェン
編曲 : 青島広志 |
ベートーヴェンが楽曲の構想を温め始めたのは、まだ「交響曲第1番」も作曲していない1792年22歳の頃でした。ただ着手はしていなく、1817年、ロンドンのフィルハーモニック協会から交響曲の作曲の委嘱を受け、これをきっかけに本格的に作曲を開始したものと見られています。この作品は、交響曲の金字塔となり、以後の作曲家はみな意識せざるを得なかった代表曲です。
このような「THE 交響曲」を、番組でおなじみの青島広志さんにより、弦楽四重奏の作品に仕上げました。
旧ソ連の作曲家ショスタコーヴィチが1960年に作曲しました。「ファシズムと戦争の犠牲者の想い出に」捧げられた作品ですが、ショスタコーヴィチ自身のイニシャルが音名「D-S(Es)-C-H」で織り込まれ、自身の書いた曲の引用が多用されることにより、密かに作曲者自身をテーマにしていることを暗示させています。15曲あるショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲の中で、最も重要な作品でもあります。
本来、全5楽章を続けて演奏するため、今回の抜き出し演奏は、少々唐突な終わり方となっていました。
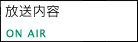
|