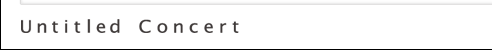| 作曲: ブラームス |
指揮: 村中 大祐
演奏: 米元響子(Vn)
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 |
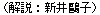
ドイツの作曲家ヨハネス・ブラームスは、ロマン派全盛の時代にあって、ドイツ古典派の伝統にのっとった重厚で構築的なスタイルを守りぬきました。その作品は堅固な構成を持ちながら美しい情感と詩情にあふれています。
ブラームスは、コントラバス奏者の父のもとハンブルクに生まれました。幼少から音楽の才能を発揮し、十代半ばで最初のピアノ・リサイタルを開催。1853年にハンガリー出身のヴァイオリン奏者レメーニと演奏旅行に出かけ、その旅先で、当時のヨーロッパを代表するヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒム(1831〜1907)と知り合います。ヨアヒムもまたブラームスと同じ古典主義音楽の信奉者で、二人はすっかり意気投合し、その後ブラームスは彼のために数多くのヴァイオリン作品を作曲しました。
ブラームス唯一のヴァイオリン協奏曲であるこの作品も、ヨアヒムに捧げられたものです。45歳の夏、ブラームスは、オーストリアの避暑地ヴェルター湖畔のペルチャッハに滞在し、ヴァイオリン協奏曲の作曲に取り掛かりました。そして大体の構想ができあがったところでヨアヒムに楽譜を送り、アドバイスを求めています。古典的なものを好むブラームスとヨアヒムの協力によって完成したこの協奏曲は、当然のことながら、派手なテクニックを誇示するコンチェルトのスタイルではなく、確固たる構成のなかに内省的な抒情を湛えた味わい深い作品となっています。当初この曲は全4楽章制をとっていましたが、試行錯誤を重ねた末、伝統的な3楽章の協奏曲となりました。初演は1879年に、ライプツィヒ・ゲヴァントハウスでヨアヒムの独奏によって行われましたが、好評を得ることができませんでした。しかしヨアヒムはこの曲の優れた価値を信じて各地で何度も演奏を重ね、一方ブラームスもヨアヒムからのアドバイスに従って曲の一部を改定。やがてこの作品は、音楽史上最高のヴァイオリン協奏曲の一つに数えられるに至ったのです。
第1楽章はオーケストラの壮大な響きによって始まり、音楽の緊張感が高まった頂点でソロ・ヴァイオリンが激しく情熱的に登場。第一・第二主題ともにヴァイオリンの魅力を活かした旋律で、特に第二主題にはブラームスらしい歌謡性があふれています。
第2楽章は管楽器だけの長い前奏でオーボエが印象的な旋律を歌い、そこにヴァイオリン独奏が加わって、憧れと不安を行き来しながら音楽は進んでいきます。
第3楽章はハンガリーの民族音楽的なヴァイオリンの主題を持つ、活気にあふれた楽章。クライマックスではその主題がより速いテンポで提示され、華やかに全曲が閉じられます。
| 作曲: 小出稚子 |
指 揮: 村中 大祐(第11回受賞)
演 奏: 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 |
(解説:小出稚子)
ケセランパサランが本当のところ一体何なのか?― それは誰も知りません。ただ、巷では「白いフワフワした毛でできている生物」であるとされ、「持っていると幸せになる」「笑いながら飛んでくる」「桐の箱に入れておしろいを食べさせると増殖する」などと言い伝えられています。
以前からその存在は知っていましたが、一昨年の夏休みに行った東北地方の博物館にてケセランパサランを偶然にもこの目でみることができました。(博物館なのできっとあれは死骸ですね・・・)ちなみに名前の語源は「なんだろう?何が起こるんだろう?」という意味のスペイン語「QUE SERAN PASARAN」だという説があるのですが、この説は非常にワクワク感があり素敵ですよね。
さて、この作品の中で私がやりたかったことは、1.規則性を持って流れていくものと、規則的な流れの中に在りながらもある程度自由に動けるものを共存させること。 2.オーケストラという編成上の特性を活かした視覚的、聴覚的な仕掛けを随所に散りばめ、それによって立体的な音響空間を作り出すこと。 3.いくつかの異なった性格をもったブロックが乱立しながらも、それらが相互に有機的な繋がりをもつこと。 の3点です。
またこれらを音楽を形成する要素として具体化していく際に、音色やリズムの変化によって発生する微妙な空気の色合いにアンテナを張り、その合間合間に遊び心とユーモアを忍ばせることにしました。
この作品は私の書いた初めてのオーケストラ作品です。高校時代オーケストラ部に所属していたこともあり、常々オーケストラという編成には他の様々な編成にはない、独特の生活感と親近感を感じていました。たくさんの遊びなれた遊具がある近所の公園のようなイメージです。
その公園に作曲家という立場で改めて入ってみると、以前から密かに感じてきた「これをこうしたら絶対おもしろいだろうな」「あれをこうしたらどんな音がなるんだろう?」といった願望や好奇心を、実際に作品の中に実現させてみたくなり、自分で自分の妄想にどきどきしながら書き進めていきました。
| ♪3:ギター協奏曲第3番「悲歌風協奏曲」第3楽章より |
| 作曲: ブローウェル |
指 揮: 村中 大祐
演 奏: 大萩 康司 (Gt)
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 |
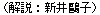
レオ・ブローウェルは、キューバの首都ハバナで生まれた作曲家、ギタリスト、指揮者です。
アメリカに留学し、名門ジュリアード音楽院とハートフォード大学に学びました。彼の作品の大部分はギターのために書かれたもので、キューバの民謡のメロディを取り入れたものから、20世紀の作曲家ルイジ・ノーノやヤニス・クセナキスの影響を受けた前衛的な作品、ロマンティックな映画音楽作品、と幅広いスタイルを見せています。それらの作品は、映画音楽界の巨匠ジョン・ウィリアムズ、ギタリストのジュリアン・ブリーム、古楽の名指揮者フランス・ブリュッヘンなどによってレコーディングされ、また優れたギタリストとして世界各地の音楽祭に招かれています。
指揮者としての活動も旺盛で、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、スコティッシュ・ナショナル管弦楽団、BBCコンサート・オーケストラなど世界の一流楽団を指揮。さらにキューバ国立交響楽団の総支配人を10年間勤め、スペインのコルドバ管弦楽団の指揮者としても活躍、1998年にはマヌエル・デ・ファリャ音楽賞、99年にはキューバの国民音楽賞を受賞しました。またハバナ国際ギターコンクールの主催者でもあります。
ブローウェルのギター協奏曲は現在、第1番から第12番まであり、今回の第3番「悲歌風協奏曲」は1985〜86年にかけて作曲されたものです。ギターの楽器の特性が充分に活かされたソロ・パート、そしてオーケストラは打楽器群と弦楽合奏のみというユニークな編成で書かれています。
第1楽章は、タイトルにあるように「悲歌」的なメロディを歌うギターソロに始まり、そこに弦楽器がユニゾン(同音)で鋭いアクセントを持つメロディを奏で、両者が対比を作り出します。やがて弦楽器のシンプルなメロディにアラベスク模様をつけるようにギターが細かいパッセージで動き出し、音楽の頂点に向かって次第に切迫していきます。
第2楽章は、多数の映画音楽を手がけたブローウェルならではの緩やかでロマンティックな音楽。弦楽合奏がギターの開放弦の響きを模倣するように低音から高音に向かって重なり、その上でギターがレチタティーヴォ風に自由なメロディを歌います。第2楽章と第3楽章は切れ目なくつながり、突然テンポの速いギターの連打が始まります。「トッカータ」と題された第3楽章は速いパッセージに貫かれ、クライマックスに向かって一気に駆け上がっていきます。終結部で第1楽章の主題が静かに回想されますが、すぐに激しい調子に戻り、エネルギッシュに全曲が閉じられます。
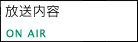
|