| ■井出耕也の朝生ライブ中継ルポ! | |

「日本の社会の50年勤続疲労をどうにかしたい」 |
| 午前4時のCMタイムが終わって、いよいよ残すところ、あと1時間。副調整室のモニターテレビに映っている東京の街も明るくなりつつある。 |
|
蜷川 日本の民主主義50年勤続疲労 「何年前だったか、政治改革が盛んに言われていた頃、後藤田正晴さんから政界も金属疲労を起こしているというお話を聞いて、なるほどと思ったんですが、戦後50年たって、政界だけでなく日本のあらゆるシステムが疲労を起こしているんじゃないか。だから、国民投票という話も出てくるわけです。この疲労の部分を変えることを考えないといけないと思うんですがね」 |
|
今井 マイナスの回転に入ってしまう危険 「もし、このままの日本だったら、日本はマイナスの回転に向かうんじゃないかという気がするんです。国民が拒否権を発動できない、提案権もない、大事なことについての決定権もない。しかも官僚のみなさんが賢い。そしたら、ますます投票に行かなくなって、原発や安保について話し合うこともやめてしまって、どんどんマイナスの回転に向かっていくんじゃないか。それが心配なんです。それだったら、プラスの回転になるようにしていったほうが、多少の間違いはあっても、国民にとって、もっと良くなると思う」 玉城 リーダー論が通用しない状況 「今日の議論の中で、あるべきリーダー論みたいな話も出ましたが、そういうものがないのが現状だと思う。そういう人がいなくなってしまった。むしろ、場合によっては市民のほうが前のほうに行っていて、政治家はうしろのほういるということだってあるような状況です。リーダー論が通用しなくなったところにも昏迷や閉塞状況の原因がある」 堀 モノトーンのマスコミと国民投票 「日本の政治と会社の経営を同じレベルで論じるつもりはないが、私は会社の中では常に少数意見ですよ。いや、会社の中だけでなく、どこに行っても少数意見ということが多いんですがね。少数意見だから、結果としてはみんなの言う方向で物事が決まることが多い。でも、僕のような人間がいると、決まりかたが違ってくるんです。 みんなと違う意見や少数意見を出すことによって、みんなが僕の案のメリット、デメリットを考えて、大袈裟に言えば最初の案を修正して、みんなの意見を通す。それによって、間違いも少なくなるわけです。しかし、今のようなモノトーンのマスコミがあるところでは、国民投票と言ってもどうなのか。何を国民投票にかけるか、よく考えないといけないと思う」 |
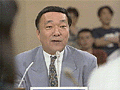 |
 |
高野 国民を馬鹿にした話 「こんどの住専問題でも、国会では本当に国民が息を呑んで見つめるような議論はいっさいなかった。そういうのではなくて、国会では活発な議論があって、また、国会テレビなんかもあって、何が論点か国民にもわかっているという中で、いくつかの案を国民投票にかけるという、そういうやり方もあると思う。確かに消費税に賛成か反対かという聞き方をするのは、まったく国民を馬鹿にした話であって…」 堀 国会でもできないのに… 「何が論点で、何と何がトレードオフでと、そういうことがはっきりした状態で国民投票が行われるのなら、僕も大賛成です。しかし、国会でもそれができないのに、1億2400万人のレベルでそれができるという保障があるんですかと、そういうことを僕は言いたいんです」 高野 「もちろんですよ。そんな保障はありませんよ。だから、どうするかということを話しているんです」 |
|
竹花 議員は全国民の代表 「学生さんの意見にもありましたが、議員は自由委任されているというのが議会制民主主義の原点なんです。つまり、いったん選挙された以上は、選挙区の代表ではないんです。全国民の代表なんですよ。だから、国会においても、自らの信念に基づいて主体的に判断することになっている。ところが選挙民のほうは選挙区の代表だと思っているんですね。それでお葬式に出るとか、お祭りの御祝儀がどうとかいう話が出てくる。このあたりのことをもう一度、考えないといけない。これは憲法の43条にも書いてあります」 八幡 国民投票の結果は無視できない 「国民投票の結果はどうなっても、それはあくまでも参考だという考え方をおっしゃっていた方もいましたが、私はそれはちょっとおかしいと思う。国民が最終的にこれだと判断したことを無視するのは、やはりちょっとできないでしょう。 かつて、ドゴールが大統領を直接選挙で選ぶように国民投票で決めたことがあるんです。それに対して、フランスの憲法裁判所は憲法違反だと指摘した。そして、その上で国民が決めたことを覆すことはできないという判断を示した。ですから、何かの問題を国民投票にかけるとしたら、その結果には必ず従うということを国会が責任を持って判断できない限りは、それはやってはいけないと思うんですね」 高野 知的水準にふさわしいイニシアチブを 「国民の知的水準は、実はかなり高いんですよ。しかし、それにふさわしい知的なイニシアチブがいまの政治にあるだろうか。命令でもなければ権限でもない知的なイニシアチブがね」 |
| モニターテレビに映っている街の風景がどんどん明るくなっていく。土曜日の朝の東京が動き出そうとしている。 |
|
竹花 直接民主制の元祖スイスでは反省も 「スイスでは国民投票に反省が起きています。10年ぐらい前に『スイスはどこに行く』という本が出版されてベストセラーになった。フリブル大学のウィットマン教授が書いた本です。その中でこう書かれている。『原子力発電から妊娠中絶、税金まで、ありとあらゆる問題が国民投票の対象となり、しかも、少なからずノンの判定を受け、行政は停滞している。直接民主制は重大な決定を拒むために存在している』と非常に厳しい言葉を使っています。 さらに『無知で保守的な大衆の意思によって改革を断行できない政治体制が続けば、スイスの前途は絶望的である。だから、国民投票制など直接民主制的な制度を廃して、議会制民主主義に一本化すべきである』と言っている。この主張がかなりうけているところがあるんです』 高野 「しかし、それはやってみて、そこまで行ったということで、やってもいない日本とは違う」 志村 民主主義と心中 「日本は本当に民主主義が大切で、全国民がそういうことで動くのなら、どんな欠陥があろうが、それを甘んじて受け入れるべきですよ。だけど、国会議員には国を導くリーダーとしての義務があるはずだし、多少は民主主義にも遠慮してもらなわないといけない場面があると思う」 |
 |
|
蜷川 「ここまでのお話を聞いていると、民主主義は面倒くさいとか、もっとすごいリーダーがほしいというような話になっているようです。しかし、その一方には、今井さんや左近さんが言っているように、多少能率が悪くても、民主主義はいいんじゃないかという意見もあるわけですね」 |
|
今井 もっと国民に情報を 「国民が賢いとか賢くないとか言いますが、大事なのはどれだけ国民に情報が与えられるかということだと思う。そういう意味では、日本はあまりにも貧しいですよ。情報が国民に与えられていない。それでは官僚のほうが勝つに決まっていますよ。マスコミの一言、一言で、国民が右往左往する可能性も否定しませんが、充分な情報があれば、そういうことに対しても、抵抗力がつくと思うんですがね」 八幡 国民投票でマスコミのレベルも上がる 「選挙だけでなく国民投票みたいなものがあれば、マスコミのレベルも上がると思いますよ。住専の問題にしても、どうすればいいのか、その選択肢が他にないと言いますが、政府が出した案の他にどんな選択肢があるかというような議論は、もっと前にマスコミでどんどん議論されていて当然なんです。ところが、実際には、政府案が出てきたところで、それはおかしいと騒いだだけなんですね」 高市 「私が前から空しいと思っているのは、最高裁の裁判官の国民審査です。顔も見たいこともないような裁判官の審査をしろと言われてもねえ」 高野 既存の制度の活用を 「同じような制度がアメリカにあったら、どんなことが起きるかというと、市民グループみたいなところが、インターネットなどを利用して、この裁判官はこういう人物だということをどんどん流すでしょう。だから、市民のほうで、こういう制度をもっと活用すればいいんですよ」 |
 |
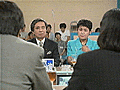 |
蜷川 「日本の民主主義はどうなっているのか、それを、いま、議論しているわけです。国会があり、審議会があり、いろいろな委員会があり、あるいはマスメディアがあり、市民運動があるわけで、そういう中に国民投票があってもいいというのが今井さんたちの言っていることですよね」 坂東 唯一の無謬のシステムはない 「そうなんです。官僚が情報を握っていると言いますが、だから、失敗がないなどということはありえないわけですよ。もちろん、政治家もそうです。どんな制度があっても、絶対に間違いがないということはないと思います。ですから、間違いをチェックする機構は二重三重にあったほうがいいわけで、どこもオールマイティではないということを大前提において、日本のシステムを考えていかないといけないと思います」 柿沢 誰が国民投票を発議するのか 「間接民主主義を補完する制度として、諮問型の国民投票を導入することは、確かにひとつの考え方だと思います。ただし、その際、発議が議会で行われるのか、それとも国民の何割の要求みたいな形で行われるのかで、性格がだいぶ違ってくる。議会が発議するということになれば、議会としては判断することをやめて国民にお任せするということになる。一方、国民が請求するということになれば、むしろ、議会の判断を信頼できないということになる。このあたりははっきりさせないといけない」 |
| あと15分弱で5時。ここで最後のCMに入る。パネリストたちは、このCMの間に、何か言い忘れていたことはないか、最後に言うべきことは何か、もう一度、今夜の議論を反芻していることだろう。そして、CMが終わり…。 |
|
蜷川 「さあ、もうひと踏ん張りです。日本の政治にもいろいろ問題点はあるけど、まあ、頑張って欲しいということで政治改革も始まったんですが、まだ残された問題もあるわけで、今後はどういうことになると見ていますか」 |
|
堀 小選挙区で議員がますますサラリーマン化 「これからも政治改革が進めばいいと思いますが、今のやり方では難しいかもしれませんね。小選挙区ですから党の幹部の力が強くなり、議員のサラリーマン化が進むんじゃないですか。サラリーマンで言うと、会社のためにやる人よりは、上司の引っ越しの時にはカミさんを連れてお手伝いに行くというような人のほうが課長、部長になっていくような感じでね」 柿沢 比例はいらない 「小選挙区比例代表の並立というのが矛盾しているんです。どちらかに徹したほうがいい。たとえば、小選挙区一本にしてアメリカの民主党、共和党のように党議拘束をはずして、議員個人の判断に委ねるとかね。今の制度では衆議院は300の小選挙区と200の比例代表ということになっていますが、比例代表分は削って、衆議院の議席は小選挙区の300議席だけにしてしまって、そのかわりに政策秘書を増やすという形にしてもらう。これがいいと思いますね」 左近 シガラミ選挙を脱して制度を生かす 「この選挙制度は本来は政党の争いになるはずなんですが、実際には、高市さんのお話にあったようにシガラミ選挙になってしまっている。シガラミ選挙から開放されないと小選挙区比例代表並立制が生きてこない」 高市 近い将来の政界再編は避けられない 「新しい制度のもとでの選挙が行われる前に、保守対リベラルといった形で政策による政界再編が終わっていれば、政策選挙になると思います。ところが先に選挙が来てしまった。ですから、次の選挙が終わったら、今の政党の枠組みはガラガラポンになるべきだと思いますよ。私自身も次の選挙は新進党で戦うことになったとしても、その次の選挙はどこの党で戦うことになるのか、今から約束することはできないですよ。必ず再編されるべきだと思いますしね」 玉城 「政界の離合集散みたいな話はどうも空しい。そういう話がこのテレビを見ている人の気持ちとどこまで合うか、それを自己検証しながら話す必要があると思う」 八幡 民主主義の根幹が危うい 「投票率が落ちていると批判されますが、これは世界的な傾向なんです。選挙にばかり関心を持たなくっているんです。だから、国民投票がいいかどうかはともかくとして、国民がどういう風に政治や行政に関わっていくか、その幅を広げていかないと民主主義の根幹が危なくなる恐れがあるし、そういう意味で、国民投票や住民投票が評価されるところがあるということじゃないでしょうか」 |

 |
|
蜷川 「そう。だから、今日のテーマは、国民投票を導入するかどうかということだけでなく、今の日本のシステムはどうなのかということだったんです」 |
|
午前5時。すっかり夜が明けた。副調整室に「お疲れ様」の声が響く。 テレビ朝日の食堂では今日のパネリストが談笑している。 長くて、そして短い4時間が終わった。 日本がまた少し見えてきた。 |
 |
|
井出耕也 ide koya インターネット・パイロット(ルポライター) 1945年11月生まれ 新聞社勤務からフリーのジャーナリストへ。 専門分野は?と質問されたら「ジャーナリスト」と答えることにしている。 八百屋さんが「八百屋です」と答えるように。魚屋さんが「魚屋です」と答えるように。 |
| |表紙|6月のテーマ| |
All documents, images and photographs included in this site are owned by TV-Asahi. |