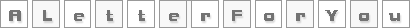
| |
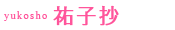
|
 |
Vol.74 「楓」
(2004/10/21) |
 |
先日、8年ぶりに母校を訪れた。
中学校から大学までが一つの山の中に位置しているため、
たどり着くまでには最寄り駅から30分近くを要する。
私が高校3年間を過ごした寮も、その敷地内にあった。
コロッケのおいしい駅前のパン屋さんは健在だったが、坂道沿いのコンビニがなくなっていた。
寮から駅前に出かけることを「下山」と呼んでいた程、なかなか過酷な坂道である。
何往復もしたはずの地面の感覚を必死に思い出そうとするが、
自分の靴音は何だか他人のように響く。
登下校時は中高生の短いプリーツスカートで溢れかえるこの坂道も、
昼前とあって閑散としていた。
下りのエスカレーターを必死に駆け上がろうとする子どものように、
歩めど歩めど、気持ちは過去に巻き戻される。
冷えた大気を包み込む楓の中を歩きながら、かつての学び舎を横切っていく。
山頂にある寮は、ひっそりと佇んでいた。
大きな銀杏の木の陰に隠れ、相変わらず日当たりは悪い。
「ただいま帰りました」とは、言えない。
「ごめんください」とも、言わない。
気が付けば、無言で扉を開けていた。
入り口には小さなカウンターがあって、昔のままの内線電話と外出簿が置かれていた。
その奥には、寮生たちの名札が下がっている。
裏表で色が異なるそれは、在寮時は白で、出かける際にひっくり返すと黄色になる。
玄関先には、ダンボールが数個置かれていた。
きっと、それぞれの実家からの宅配便だろう。
帰寮時刻に間に合うように、夕闇を全速力で駆けたこと。
玄関先で、靴についた四季折々の草花を払ってからスリッパに履き替えたこと。
テレホンカードを何枚も握り締め、夜中にこっそり公衆電話から実家に電話したこと。
そういうことが、今もこの場所で繰り返されているのだろうか。
当時の寮監の先生は数年前に退職されていて、新しい先生が私を迎えてくれた。
「玄関先もなんだし、中に入られたら?」
せっかくのお誘いだが、断ってしまった。
「あの…これ、皆さんで召し上がって下さい」
ガトーショコラをおずおずと差し出して、寮を後にした。
「行ってきます」と「行ってらっしゃい」の繰り返し。
そこには「お帰りなさい」という幸せが隠されていることに、今になって気付く。
やわらかな記憶は、時と共に凝固する。
当時の日々は結晶となってそこにあり、決して風化されることはない。 |
|
|
|
| |
|