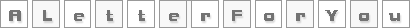
| |
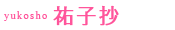
|
 |
Vol.39 「ミッシェル」
(2003/07/07) |
 |
季節の移り変わりに線は引けない。
花の咲く瞬間や、雨の上がる瞬間がそうであるように。
ただ、梅雨明けだけはいつも突然だ。紙芝居の場面がさっと変わるように、
その次には夏が待っている。十五年前の初夏、私と妹が体験したことだ。
1.
梅雨時の下校は幼ながらに物憂いものだが、雨上がりの公園は好きだった。
友達がランドセルを投げ置いて、滑り台やブランコに駆け出すこともない。
その日も同じように公園を横切ると、子供たちが濡れた遊具を囲んでいた。
「死んでるの?」
「ううん、動いてる」
水溜りには、黄緑のインコが横たわっていた。誰かが連れて帰らないと
この状況から抜け出せない。間の悪い、静止画の解除ボタンを押したのは妹だった。
帰宅すると案の定母は顔色を変え、社宅で飼えないことを理由にインコを返すよう促した。
「でも、このままだと死んでしまう」
首はだらり垂れ、半目開きで小さく震えている。
私たちは、タクシーに乗った。
ペットショップでは「病気の鳥は受け取れません」とあっさり断られ、
今度は動物病院へ向かった。栄養失調と怪我でかなり衰弱してはいるものの、
薬を与えたら数週間で元気になるという。
その時の困惑とも安堵ともつかない母の表情は、今も忘れられない。
「ミッシェル」という名前は妹がつけた。
酸欠を防ぐため穴の開けられた段ボール箱で、
体を冷やさないようバスタオルとカイロに包まれている。餌は朝晩二回、
スポイトで栄養剤を与える。明らかに名前負けしている病弱さが、かえって愛らしかった。
晴れた日のベランダには家族とミッシェルのバスタオルが並び、妹も私も、
毎日急いで下校した。帰宅を告げる父からの電話にも、ミッシェルの名前が
頻繁に登場するようになった。
2.
梅雨が明けたら突然夏になっていた。
そして、ミッシェルもカラリと元気になってしまった。
まるでここから出してくれと懇願するかのように、日増しに羽音が大きくなる。
「いや、絶対に返さない」
妹は頑として聞かなかった。
「ミッシェルはお母さんに会いたいのかもしれないよ」
決め台詞は父だった。
次の日曜日、とうとう近所の池上本門寺に放すことになった。
ミッシェルは梅雨の約一ヶ月を、我が家で暮らしたことになる。
「飛ばない…」
ミッシェルはきょとんとして地面に佇んでいる。家の中ではあんなにばさばさと
羽音を響かせていたのに。
やり切れなくなり両手で抱えて空に放すと、上下にバランスを崩しながら
ふわりと浮いた。そして、鬱蒼とした木々の中へ消えた。
「大丈夫かなぁ」
言ってみたものの、出来れば戻って来て欲しかった。しゃくり上げる妹を横目に、
私は完全に泣くタイミングを失っていた。もうミッシェルはいない。そのことだけが、
ただ寂しかった。
もしかしたら、きちんと飛べていないのかもしれない。
でも、もう振り返ってはいけない気がした。
3.
家のベランダの前には大きな枇杷の木がある。ミッシェルにもう一度会えたのは、
枇杷の実が朽ちかけの頃だった。
ふと気配を感じてベランダを見ると、黄緑のインコが数十羽、枝に止まっていた。
「ミッシェルだ」
母と妹と私は急いでベランダに出た。インコの群れは、驚くほど静かだった。
じっと、こっちを見ている。
私たちも、黙っていた。
彼らは、その後も何度かやってきた。
今になって思う。
たぶんあの群れは、野生化したインコたちだろう。彼らはただ、枇杷の実を
食べに来ただけかもしれない。
記憶がねじれていても、勘違いでも。
私たちは、家族を連れてありがとうを言いに来たミッシェルを覚えている。
それだけは、本当だ。
今年も、もうすぐ梅雨が明ける。 |
|
|
|
| |
|